東京校の講義レポート
平成26年(2014)【7月4日(金)】 温故知新エネルギー学/永尾彰先生(科学者)
2014/07/04
コメント (0)
 ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------●1日の流れ
9:30 新聞アウトプット
1面「厚生年金、加入逃れ阻止」
なぜ、厚生年金に加入させるのか議論。
1面「中韓FTA年内妥結目標
日本にどう影響を与えるか。
9面「アップル、中国にテコ入れ
なぜ、内陸部?、日本企業はどう反応すべき?
・15面:未上場ベンチャー大型増資
日本が米国よりも企業に出資するお金が少ないのはなぜか?
12:00 温故知新エネルギー/永尾彰先生(科学者)
----------------------------------------------------------------------
●温故知新学/気付きの博士
永尾彰先生は、物理学やエネルギー関係に詳しい博士。
お話は、まずは原子力発電の真実、石炭火力発電とCO2半減、といった
ご専門に関する話題から始まった。
先生はお話の中で何度も、「ここでこういう商売をすれば売れるよね」といった
アイデアを与えて下さった。
私はそれを聞いて、先生は「気付き」の達人であると思った。
すなわち、世界の見聞を広めることで、「こういうものがあれば」という気付きを得て、
それを商売に生かす、ということが必要なのだということを教えて下さったのである。
別に日本に限る必要もなく、市場も何もないところに売り込んでいけば成功するだろう、
というのも、夢があって素敵だと思った。
そのためには、日本のことをよりよく知らなければならないと改めて思う。
先生は「日本文化を身につけよ」とおっしゃった。
先生自身も空手などの日本武道を修め、自身の道場を持っていたこともあるという。
世界のどこかに需要があって、それに対して日本からどんな技術や商品を紹介できるか、
それを考えるためには日本にどんなものがあるかを知らなければ話にならない。
その意味で、私たちが日本の文化や歴史を知ろうと学んでいるのも必ず役に立つと思う。
歴史の知恵から提案できるものがあるはずだからだ。
永尾先生は、博士であるという以上に一流のビジネスパーソンだという印象を受けた。
私も先生のように、敏感にチャンスに気付き、それをしっかり生かせるような力を身につけたいと思った。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
 ●温故知新エネルギー
●温故知新エネルギーものすごいエネルギーを感じる方で、お話が大変面白かったです。
お話の内容は、海外へ行ったお話、メディアについて、
永尾先生の過去のお話。
・海外へ
永尾先生は、たびたび、海外へとお仕事で行かれることが多く、
特に印象に残っていたのが、インドネシアへ行かれたお話です。
インドネシアは2020年以後に、GDP(国内総生産)が
日本を上回る世界5位の経済国になると教えて頂きました。
なぜかというと、石油などの資源が豊富であるからだといいます。
やはり、資源というのは、あるだけでその国の価値が上がるようになっている
のだなと感じました。
そしてインドネシアのトイレは、日本とだいぶ違うそうです。
「インドネシアは、宗教の関係もあり、済ました後、手で汚れを落とす」
と伺いました。ですから、必ずやティッシュは必須アイテムとして持って
いた方がよいと仰っていました。さらに、そこで日本のトイレを
ビジネスとして売れば、儲かるだろうというお話も聴かせていただきました。
つまり、永尾先生は研究者でありながら、ビジネス者でもある人なんだ、と思いました。
そこは、私も見習わなければいけないところであるので
どこにビジネスが転がり込んでいるかを、常に考える工夫をしていこうと決意しました。
・永尾先生の過去
永尾先生は、過去にアメリカで空手の道場を開いていたと伺いました。
そこで、空手を通じて多くの弟子を輩出した。先生曰く、海外に出て
仕事をするときは、日本の文化を2・3知っておくと良いと伺いました。
何故なのか?
それは、海外の方は自分の国に誇りを持つ人が多くいるからです。
自分の国には、他の国とどう違いがあるのかを認識することができ、
そこでも何か気付きを得てビジネスへと発展していきます。
これを続けてきたのが永尾先生である。本当にすごい方であるなと感じました。
ちょっとした気づきに気付けた人間こそ現代に求められている。
こうした人間になれるように日々の生活を見直し、
些細な事から気づきを得られる人間を目指します。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
--------------------------------------------------------
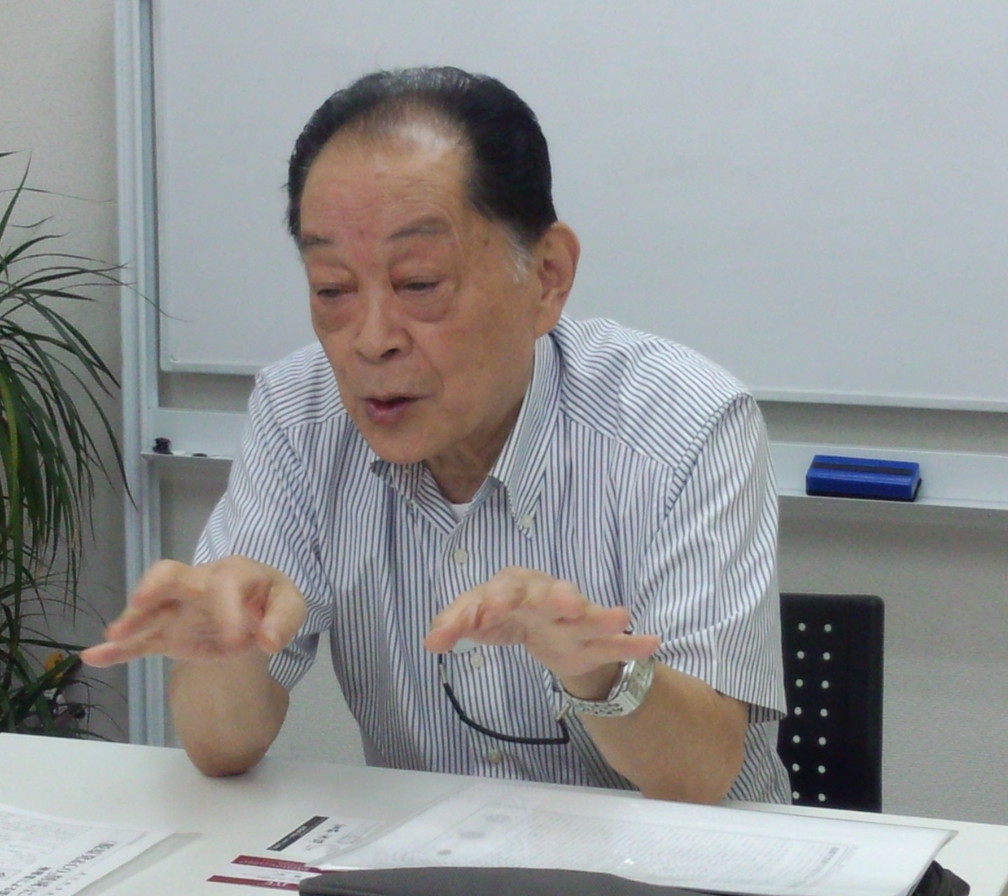 ●発想力=エネルギー
●発想力=エネルギー永尾先生は、ウランやプルトニウムを使う原子力や火力発電など
電力に関する研究をされていて、詳しい電力の発電方法を
ご説明されていましたが、私はその分野に疎いためかほとんど理解できませんでした。
そのため、次回の永尾先生の講義ではお話が分かるように
エネルギーに関してもっと勉強して準備をしておこうと痛感しました。
そして、永尾先生のお話で特に印象に残ったのは、濃縮ウランのお話す。
原発の燃料である濃縮ウランは、1g当たりの放射線で1000万人が死亡する程の
威力を持つという事をはじめて知り、驚きと同時に恐怖も感じました。
更に、作ろうと思えば、3日で日本は核を作れる程の原子力の技術があるので、
IAEAから厳重に監視されていうお話も驚きました。
また、「なぜ永尾先生がこのようなエネルギーの研究をしているのか」
という質問をした時、明確お答えは返ってきませんでしたが、
私が感じたこととしては、永尾先生は長崎の原爆を体験していて、
そこでの悲惨な光景を目の当たりにしたことで、原子力というものに
関わろうとしたのだと思います。
そして今回のお話を聞いて、原子力というものは、使う方法によって
色々な結果になるということを感じました。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
平成26年(2014)【7月3日(木)】 「東京国際ブックフェア」見学
2014/07/03
コメント (0)
----------------------------------------------------------------------
●1日の流れ
9:00 東京ビッグサイト集合
9:05 朝礼
9:20 新聞ディスカッション
1面「東芝、東欧で原発受注」
11面「ネット通販基盤 統合」
10:00 東京国際ブックフェア見学
----------------------------------------------------------------------
●東京国際ブックフェア、紙の価値を高めるには
電子書籍関連のブースが大きな位置を占めており、様々な知らない企業が、
自社のサービスを売り込んでいた。
もはや電子書籍が一つの部門として認められるほどに、
電子書籍の存在は当たり前になってきている、という時代の移り変わりを感じた。
一方、紙の書籍のほうのブースも十分色々あった。
こちらでは、ほとんどの書店が20%オフで自社の書籍を販売していた。
印象としては、紙媒体のほうはあまり売り込む気がないのかな、という感じだった。
今までと同じやり方ではいずれ行き詰ってしまうことは認識していると思うのだが…。
マンガ・アニメの売り上げに大きく関わる「一番くじ」のブースや、
「書籍復権」を掲げる出版社グループなどもあった(あの岩波書店がごく小さなブースで
営業しているのには驚いた)ものの、
多くが今まで通り自社の新刊や特集を押し出すばかりで
目新しさがないのが気になった。
私は紙の本が好きだから、東京国際ブックフェアをもっと創造的なイベントにして、
紙の本を盛り上げて欲しい。
例えばブースの配置にしたって、適当にジャンル分けしてあとは無造作に(成約順に)
ブースを並べていくよりほかに、もっとストーリー性を持たせるやり方はなかったのか。
そういう所への意識があまり感じられないところが、日本の紙の書籍が斜陽と
言われている一つの象徴的な光景となってしまっていると感じた。
ちなみに、今回購入したのは書籍ではなくノートである。
N社の製品で、レトロな外観を持ちながら、
高度な綴じの技術を採用し、反対側まで大きく開いてしまっても紙が剥がれることがない。
なにより、「くたくたになるまで使ってやってください!」という店員さんの言葉に
惹かれて購入を決断した(800円)。
使い込むことが望まれているノートとは、何とも素敵ではないか。
私はこういうストーリー性を求めているのだ、と思った次第である。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●1日の流れ
9:00 東京ビッグサイト集合
9:05 朝礼
9:20 新聞ディスカッション
1面「東芝、東欧で原発受注」
11面「ネット通販基盤 統合」
10:00 東京国際ブックフェア見学
----------------------------------------------------------------------
●東京国際ブックフェア、紙の価値を高めるには
電子書籍関連のブースが大きな位置を占めており、様々な知らない企業が、
自社のサービスを売り込んでいた。
もはや電子書籍が一つの部門として認められるほどに、
電子書籍の存在は当たり前になってきている、という時代の移り変わりを感じた。
一方、紙の書籍のほうのブースも十分色々あった。
こちらでは、ほとんどの書店が20%オフで自社の書籍を販売していた。
印象としては、紙媒体のほうはあまり売り込む気がないのかな、という感じだった。
今までと同じやり方ではいずれ行き詰ってしまうことは認識していると思うのだが…。
マンガ・アニメの売り上げに大きく関わる「一番くじ」のブースや、
「書籍復権」を掲げる出版社グループなどもあった(あの岩波書店がごく小さなブースで
営業しているのには驚いた)ものの、
多くが今まで通り自社の新刊や特集を押し出すばかりで
目新しさがないのが気になった。
私は紙の本が好きだから、東京国際ブックフェアをもっと創造的なイベントにして、
紙の本を盛り上げて欲しい。
例えばブースの配置にしたって、適当にジャンル分けしてあとは無造作に(成約順に)
ブースを並べていくよりほかに、もっとストーリー性を持たせるやり方はなかったのか。
そういう所への意識があまり感じられないところが、日本の紙の書籍が斜陽と
言われている一つの象徴的な光景となってしまっていると感じた。
ちなみに、今回購入したのは書籍ではなくノートである。
N社の製品で、レトロな外観を持ちながら、
高度な綴じの技術を採用し、反対側まで大きく開いてしまっても紙が剥がれることがない。
なにより、「くたくたになるまで使ってやってください!」という店員さんの言葉に
惹かれて購入を決断した(800円)。
使い込むことが望まれているノートとは、何とも素敵ではないか。
私はこういうストーリー性を求めているのだ、と思った次第である。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●東京国際ブックフェア
ブックフェアへ學びに行かせていただきました。
1Fが国際ブックフェア、電子出版やコンテンツ制作・配信の3つのブース
になっており、2Fはクリエイタ―、プロダクションやキャラクター&ブランド
ライセンス展となっている。
そして、私が印象に残ったのは以下の3つである。
・『印刷技術はここまで進化している』
J社へ訪れました。この企業は、
コンテンツ業界・エンタメ業界へ特化した印刷ビジネスをしている。
この企業で、「スゴイ」と思ったのが、やはり印刷技術である。
それは何かというと、「ハイパーグロスコート」や「トリックプリント」、
「エンボスコート」などと呼ばれる技法である。
1つの印刷物なのに触ると手触りが異なる。
思わず触れずにはいられないまでにハマってしましました。
そして、これだけではなく、近年普及してきた「オンデマンド印刷」
というものが少ない部数での製作が可能になったことで、
転送したデータをおよそ4分10秒という短い時間でポスターが
できることを実演されていました。
さらに、その技術はCDジャケットやDVDなどに応用されているということも学びました。
まさに、これこそ、印刷物とデジタルの融合であるなと感じ、
日常だとなかなか学べないものを学ぶことができたことが非常に良かったです。
しっかり、自分の糧にします。
・『隙間産業』
次に、F社へ訪れました。
ここはどういうものなのかというと…「ねこガール」、「日本ニ―ソックス協会」、
「○○さんちのカレー」など一見くだらなそうに見えるが面白そうなことをしている企業である。
中でも、「これいいな~」と思えたものは、「放課後物語」と「UNIDOL]である。
まず、「放課後物語」というのは、人気の読者モデルをキャスティングしたり
実際の高校生もキャスティングするなど、平均10,000 PVを記録する
人気のサイトである。私もどういうものなのかということで検索して、実際に見てみました。
すると、女の子の妄想が再現ストーリーを写真で切り抜いたようなものでした。
ハマらないかと思いきや結構キュンキュンきました。
常に新しいものが生まれているんだなと感じました。ですので、今後は、視野を広くして
中高校生の流行も押さえておきます。
つぎに、「UNIDOL」である。これは、何かというと各大学を代表する
"アイドルダンスサークル"が出場するコンテストのことである。
出場大学は、青山学院大学、フェリス女子大学や東京理科大学など、
皆さんが知っている大学がエントリーされている。
現在は、AKB48など、様々なアイドルユニットがたくさんいますが、
大学のサークルで活動されているところがいっぱいあるんだなと知れました。
実際に、時間があるときでも一度は訪れていきたいである。
・『独創的クリエイタ―』
最後に、ドールアーティスト「臺木敦子」さんである。この方は、古着をリメイク
した手作りのぬいぐるみ"DouDou 森のプティ"を設立された方である。
そして、そのぬいぐるみは、青山テルマさんやTEEさんなど、
著名人の方にも好評だと伺いました。さらには、デザイナーだけでなく
歌手活動もされている。本当に幅広く活動されている方であるなと感じました。
実際にユーチューブで彼女の歌声を聴きましたが、
透き通った声と何か寂しさみたいなものが伝わってきて感動しました。
「臺木敦子」さんは、チャーミングな方であるが、歌手の「yonoa」はまた違った
印象を抱く方であるなと感じました。こんな方に出会えたのも何かのご縁であるので
これからも注目し、応援していきます。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
--------------------------------------------------------
ブックフェアへ學びに行かせていただきました。
1Fが国際ブックフェア、電子出版やコンテンツ制作・配信の3つのブース
になっており、2Fはクリエイタ―、プロダクションやキャラクター&ブランド
ライセンス展となっている。
そして、私が印象に残ったのは以下の3つである。
・『印刷技術はここまで進化している』
J社へ訪れました。この企業は、
コンテンツ業界・エンタメ業界へ特化した印刷ビジネスをしている。
この企業で、「スゴイ」と思ったのが、やはり印刷技術である。
それは何かというと、「ハイパーグロスコート」や「トリックプリント」、
「エンボスコート」などと呼ばれる技法である。
1つの印刷物なのに触ると手触りが異なる。
思わず触れずにはいられないまでにハマってしましました。
そして、これだけではなく、近年普及してきた「オンデマンド印刷」
というものが少ない部数での製作が可能になったことで、
転送したデータをおよそ4分10秒という短い時間でポスターが
できることを実演されていました。
さらに、その技術はCDジャケットやDVDなどに応用されているということも学びました。
まさに、これこそ、印刷物とデジタルの融合であるなと感じ、
日常だとなかなか学べないものを学ぶことができたことが非常に良かったです。
しっかり、自分の糧にします。
・『隙間産業』
次に、F社へ訪れました。
ここはどういうものなのかというと…「ねこガール」、「日本ニ―ソックス協会」、
「○○さんちのカレー」など一見くだらなそうに見えるが面白そうなことをしている企業である。
中でも、「これいいな~」と思えたものは、「放課後物語」と「UNIDOL]である。
まず、「放課後物語」というのは、人気の読者モデルをキャスティングしたり
実際の高校生もキャスティングするなど、平均10,000 PVを記録する
人気のサイトである。私もどういうものなのかということで検索して、実際に見てみました。
すると、女の子の妄想が再現ストーリーを写真で切り抜いたようなものでした。
ハマらないかと思いきや結構キュンキュンきました。
常に新しいものが生まれているんだなと感じました。ですので、今後は、視野を広くして
中高校生の流行も押さえておきます。
つぎに、「UNIDOL」である。これは、何かというと各大学を代表する
"アイドルダンスサークル"が出場するコンテストのことである。
出場大学は、青山学院大学、フェリス女子大学や東京理科大学など、
皆さんが知っている大学がエントリーされている。
現在は、AKB48など、様々なアイドルユニットがたくさんいますが、
大学のサークルで活動されているところがいっぱいあるんだなと知れました。
実際に、時間があるときでも一度は訪れていきたいである。
・『独創的クリエイタ―』
最後に、ドールアーティスト「臺木敦子」さんである。この方は、古着をリメイク
した手作りのぬいぐるみ"DouDou 森のプティ"を設立された方である。
そして、そのぬいぐるみは、青山テルマさんやTEEさんなど、
著名人の方にも好評だと伺いました。さらには、デザイナーだけでなく
歌手活動もされている。本当に幅広く活動されている方であるなと感じました。
実際にユーチューブで彼女の歌声を聴きましたが、
透き通った声と何か寂しさみたいなものが伝わってきて感動しました。
「臺木敦子」さんは、チャーミングな方であるが、歌手の「yonoa」はまた違った
印象を抱く方であるなと感じました。こんな方に出会えたのも何かのご縁であるので
これからも注目し、応援していきます。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
--------------------------------------------------------
●東京国際ブックフェア
集英社や講談社など有名な出版社をはじめ多くの出版社が出展しており、
今、出版業界が縮小傾向にある中、各出版社が生き残りをかけて
様々なアピールをしているという印象を受けました。
イベントの中でも多くの出展をしてるのは、電子書籍のブースで
これからは紙と電子がどうお互いの良さを発揮していくかが
今後の課題だと感じました。
他にも様々なイベントが行われており、出版業界だけでなく、
アニメやゲーム業界、さらにはクリエーターの出展ありました。
その中で私が印象に残ったのは、個人でゲームのイラストを書いていた
jitariさんという方です。
とても個人が書いたイラストに見えないほど上手く、更に迫力があり、
私とは違う感性の持ち主で話していて、とても新鮮さを感じました。
他にも最先端のアプリ技術を体感出来て、今回、とても良い刺激と経験になったので
今後この學びを生かしてゆきます。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
集英社や講談社など有名な出版社をはじめ多くの出版社が出展しており、
今、出版業界が縮小傾向にある中、各出版社が生き残りをかけて
様々なアピールをしているという印象を受けました。
イベントの中でも多くの出展をしてるのは、電子書籍のブースで
これからは紙と電子がどうお互いの良さを発揮していくかが
今後の課題だと感じました。
他にも様々なイベントが行われており、出版業界だけでなく、
アニメやゲーム業界、さらにはクリエーターの出展ありました。
その中で私が印象に残ったのは、個人でゲームのイラストを書いていた
jitariさんという方です。
とても個人が書いたイラストに見えないほど上手く、更に迫力があり、
私とは違う感性の持ち主で話していて、とても新鮮さを感じました。
他にも最先端のアプリ技術を体感出来て、今回、とても良い刺激と経験になったので
今後この學びを生かしてゆきます。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
平成26年(2014)【7月2日(水)】 京都1週間研修の心得(第1回)
2014/07/02
コメント (0)
 ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------●1日の流れ
9:30 新聞アウトプット
1面『エコ船舶にLNG燃焼』
13面『衣料セール 絞り込み』
7面 『米ファンドと交渉探る』
7面『香港民主派デモ「51万人参加」』
10:35 京都研修の映像鑑賞(4期生)
11:50 昼休憩
12:50 京都研修の映像鑑賞(5期生)
14:30 小林諒也さん(4期生)よりルール説明
15:00 今元事務局長の京都研修の心得
----------------------------------------------------------------------
●京都研修のオリエンテーション
先輩方の過去の様子を、4期生・5期生の映像を観て予習した。
やはりハイライトは宿交渉で、辺りが暗くなる中、お寺に「非常識だ」といって
追い返されたり、橋の下に座り込んだりしている姿が印象的だった。
次に、それを踏まえて小林さんからルール説明とアドバイスを頂いた。
ここでは、お金を極力使わないこと、無理はしないこと、
そして報告や連絡は欠かさないこと、などが強調された。
要するに、基本的なことを、気を緩めずしっかり実行することが重要なのだと理解した。
最後に、今元局長から。
印象的だったのは、別に京都でサバイバルするのが本来の目的ではなく、
自分たちの全身で、等身大で学ぶ本当の「修学旅行」なのだ、というお言葉であった。
自らの足で街を知り、歴史を知ることが、とても楽しみになってきた。
しっかり準備して臨みたい。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●京都研修の心得
本日は、7月25日からの京都研修に向けての心得を学びました。
京都は、高校の修学旅行以来になります。
本日は4期生と5期生のDVDを観て勉強させていただきました。
その中で、宿交渉や食費を節約するために飲食店で働かせてもらい、
その分、ご飯を御馳走になったり、さらには河原で野宿を経験するなど、
たくさんのことが一度に学べる。この様な経験ができるのは、
ベンチャー大學だけだなと感じました。
そして、それが私がベンチャー大學に入った理由の一つになるくらい
楽しみな研修です。
また、4期生の小林さんからアドバイスをいただきました。
行く前に必ずルートやテーマなど下調べをしておいた方がよいということ。
さらに、水道がある場所であったり、タコ足配線など必要な備品を教えていただきました。
しっかり、京都研修までに準備を整いておき、人間力を磨いて本当の自分を
探して参ります。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
--------------------------------------------------------
●京都研修のDVD鑑賞•ルール説明
今回、7/25からの京都研修に向けてて、過去のベン大の先輩方の映像を観ました。
そこでは先輩達が、過酷な環境にも関わらずとても生き生きとしていて、
私はカッコいいという印象を受けました。
そして、各チームのプレゼンでは、それぞれコントをしたり、
その場にいる方に自分のチームのテーマを振ったりするなど
様々な発表をしていていました。
私達がチームの発表をする時にぜひ参考にしたいです。
また、4期生の小林諒也さんから、京都研修で事前に
自分達が決めたテーマに沿ったルートを調べた方が良いことや、
京都研修の際に持っていくと役に立つ物などを教えてもらいましたので、
そのアドバイスを参考に京都研修に備えます。
●今元局長の京都研修の意義のご説明
そして最後に、「京都研修になぜ行くのか?』という、
京都研修の意義についてお話をしていただきました。
私は今まで、京都研修になぜ行くのかがよく
分かっていませんでした。
しかし、今元局長のお話から、「京都研修は今までの学校の修学旅行とは違い、
自分の人間力を磨くための修学旅行」ということを教えて頂きました。
私達が京都研修に行った時には、ベン大の先輩方のように
京都で何かを掴みたいです。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
本日は、7月25日からの京都研修に向けての心得を学びました。
京都は、高校の修学旅行以来になります。
本日は4期生と5期生のDVDを観て勉強させていただきました。
その中で、宿交渉や食費を節約するために飲食店で働かせてもらい、
その分、ご飯を御馳走になったり、さらには河原で野宿を経験するなど、
たくさんのことが一度に学べる。この様な経験ができるのは、
ベンチャー大學だけだなと感じました。
そして、それが私がベンチャー大學に入った理由の一つになるくらい
楽しみな研修です。
また、4期生の小林さんからアドバイスをいただきました。
行く前に必ずルートやテーマなど下調べをしておいた方がよいということ。
さらに、水道がある場所であったり、タコ足配線など必要な備品を教えていただきました。
しっかり、京都研修までに準備を整いておき、人間力を磨いて本当の自分を
探して参ります。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
--------------------------------------------------------
●京都研修のDVD鑑賞•ルール説明
今回、7/25からの京都研修に向けてて、過去のベン大の先輩方の映像を観ました。
そこでは先輩達が、過酷な環境にも関わらずとても生き生きとしていて、
私はカッコいいという印象を受けました。
そして、各チームのプレゼンでは、それぞれコントをしたり、
その場にいる方に自分のチームのテーマを振ったりするなど
様々な発表をしていていました。
私達がチームの発表をする時にぜひ参考にしたいです。
また、4期生の小林諒也さんから、京都研修で事前に
自分達が決めたテーマに沿ったルートを調べた方が良いことや、
京都研修の際に持っていくと役に立つ物などを教えてもらいましたので、
そのアドバイスを参考に京都研修に備えます。
●今元局長の京都研修の意義のご説明
そして最後に、「京都研修になぜ行くのか?』という、
京都研修の意義についてお話をしていただきました。
私は今まで、京都研修になぜ行くのかがよく
分かっていませんでした。
しかし、今元局長のお話から、「京都研修は今までの学校の修学旅行とは違い、
自分の人間力を磨くための修学旅行」ということを教えて頂きました。
私達が京都研修に行った時には、ベン大の先輩方のように
京都で何かを掴みたいです。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
平成26年(2014)【6月27日(金)】 「限界突破」/高岡祥郎先生(元プロラリードライバー) 「人脈学」/井上吏司先生(井上電気株式会社 取締役社長)
2014/06/27
コメント (0)
----------------------------------------------------------------------
●1日の流れ
9:45 新聞アウトプット
3面「スマホで生活支援 火花」
9面「韓国ゼネコン 東南ア席巻」
10:30 「限界突破」/高岡祥郎先生(元プロラリードライバー)
11:55 昼休憩
13:00 人脈學/井上吏司先生(井上電気株式会社 取締役社長)
14:30 「手帳學」/横前淳子さん(ラジオパーソナリティ)
15:10 終礼•解散
・明日の持ち込み講義打ち合わせ
・井上社長へのお礼ハガキを書く
----------------------------------------------------------------------
●高岡祥郎先生の講義
高岡先生は、ラリードライバーとして世界の砂漠を駆けた伝説の人物にして、
井上社長のご友人。
F1の監督や電気自動車の開発などを手掛けた後、現在では自動車の世界からは
きっぱりと手を引き、新型電池の研究開発に携わっているという、
多芸で恐ろしく有能な方である。
高岡さんは「ガキ大将になれ!」という言葉を何度も口にされていた。
ガキ大将であるためには、勝負には常に全力で、危険も顧みず、
人の倍以上の経験を積んでいかなければならない。
数々の死線をくぐり抜けてきた高岡さんだからこそ言える言葉だと感じた。
商売に関して言えば、「買いたきゃ、売ってやるよ」というくらいの姿勢がよいという。
それは、他人と同じようなものを売るから値下げなどしなければならなくなるのであって、
真似出来ないものなら売り手優位だ。
その独自性を獲得するため、日々努力を重ねていきたい。
●本当に人を大切にする人と、お付き合いをする
井上社長からは、手紙を書くことが如何に大切かを教えて頂いた。
手紙を出し続けたからこそ、ご縁が繋がって、商売でより大きな仕事を手に入れたり、
小泉純一郎氏のような超大物と出会うことが出来たりするのである。
私もベン大に来てから何度か葉書を出したが、形式などいまいち分からないまま、
要領を得ないものを送ってしまっていた。
だが、葉書なら形式的挨拶など気にせず、相手の良いところ、共感した言葉などを
書いていけばよい、と知って気が楽になった。
課題として井上社長から与えられた、20人から返事を頂くことと同時に、
その相手にはさらに手紙も書くようにする。
人との繋がり、ご縁を大切にすることを行動に移したい。
●横前淳子先生によるお話
打ち合わせのためにいらっしゃった、手帳学の横前淳子さんにも少しお話を聞くことが出来た。
オリジナル手帳の進み具合や、最近のご縁のことについてお話されていた。
オリジナル手帳が実現することになったきっかけもまた、マメな連絡でご縁が繋がったからであった。
何かを為し遂げるためには、「人脈をつくる」能力が必要不可欠だと学んだ一日だった。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●1日の流れ
9:45 新聞アウトプット
3面「スマホで生活支援 火花」
9面「韓国ゼネコン 東南ア席巻」
10:30 「限界突破」/高岡祥郎先生(元プロラリードライバー)
11:55 昼休憩
13:00 人脈學/井上吏司先生(井上電気株式会社 取締役社長)
14:30 「手帳學」/横前淳子さん(ラジオパーソナリティ)
15:10 終礼•解散
・明日の持ち込み講義打ち合わせ
・井上社長へのお礼ハガキを書く
----------------------------------------------------------------------
●高岡祥郎先生の講義
高岡先生は、ラリードライバーとして世界の砂漠を駆けた伝説の人物にして、
井上社長のご友人。
F1の監督や電気自動車の開発などを手掛けた後、現在では自動車の世界からは
きっぱりと手を引き、新型電池の研究開発に携わっているという、
多芸で恐ろしく有能な方である。
高岡さんは「ガキ大将になれ!」という言葉を何度も口にされていた。
ガキ大将であるためには、勝負には常に全力で、危険も顧みず、
人の倍以上の経験を積んでいかなければならない。
数々の死線をくぐり抜けてきた高岡さんだからこそ言える言葉だと感じた。
商売に関して言えば、「買いたきゃ、売ってやるよ」というくらいの姿勢がよいという。
それは、他人と同じようなものを売るから値下げなどしなければならなくなるのであって、
真似出来ないものなら売り手優位だ。
その独自性を獲得するため、日々努力を重ねていきたい。
●本当に人を大切にする人と、お付き合いをする
井上社長からは、手紙を書くことが如何に大切かを教えて頂いた。
手紙を出し続けたからこそ、ご縁が繋がって、商売でより大きな仕事を手に入れたり、
小泉純一郎氏のような超大物と出会うことが出来たりするのである。
私もベン大に来てから何度か葉書を出したが、形式などいまいち分からないまま、
要領を得ないものを送ってしまっていた。
だが、葉書なら形式的挨拶など気にせず、相手の良いところ、共感した言葉などを
書いていけばよい、と知って気が楽になった。
課題として井上社長から与えられた、20人から返事を頂くことと同時に、
その相手にはさらに手紙も書くようにする。
人との繋がり、ご縁を大切にすることを行動に移したい。
●横前淳子先生によるお話
打ち合わせのためにいらっしゃった、手帳学の横前淳子さんにも少しお話を聞くことが出来た。
オリジナル手帳の進み具合や、最近のご縁のことについてお話されていた。
オリジナル手帳が実現することになったきっかけもまた、マメな連絡でご縁が繋がったからであった。
何かを為し遂げるためには、「人脈をつくる」能力が必要不可欠だと学んだ一日だった。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●世界に名を刻む
高岡先生は、ラリー業界の重鎮である。プロ時代の頃は、
多くの成績を残された人で、現役を知り添えた後、バッテリーの研究をされている。
最近は、そのバッテリーが完成されて、これから販売に取り掛かることを伺った。
・演出とストーリー
高岡先生は、ご自身で50台の製造を手掛けて販売をし、
広告などがないということで、全国、8か所でイベントを開催した。
その時のアンケートに、「この車を購入したいですか?」というのを書き、
実際に850台を販売に取り付けたのである。
これは、とてもすごい事である。人は追い込まれたときに、ものすごいエネルギーを
放出するのであると感じた。また、販売方法に関しても、その車のストーリーを考え、
演出することで、消費者に「買いたい」と思わせることが何よりも大切である。
私も、999億円を稼ぐにはストーリー性と演出が一番必要であると感じるので、
3年間で身に付け、世界に名を残す人物になる。
・プロになるには・・
プロというのはビジネスのプロである。同じことをしている業種や人がライバルである。
そして、必ず、2位ではなく1位を取らなければ売れないからである。
それでは、どのようにすれば、ライバルに勝てるのか。
それは、ライバルより研究を繰り返し、発想、誰もしていないことを考えることで、
自ずとライバルとは差が生まれる。だから、高岡先生はすごい人である。
だから、プロのビジネスマンになるよう、業界研究を怠らずに、
隅から隅まで下調べをして、実験を繰り返しするようにしていきます。
●井上吏司社長の「人脈學」
今回は、「人脈學」ということで井上電気の井上社長のお話を伺った。
話の内容は、はがきや手紙を送ることで、人脈の輪が広がることにつながるのである。
実際に、手紙やはがきは書く機会がほとんどなく、書き方さえ知らないという現状である。
よって、今回の講義はとても大切である。
また、あらかじめ与えることが大切であると教わった。
何を与えるのかというと、人脈を与えれば、いずれ人脈が与えられることに。
そして、人を大事にすることを教わった。私自身も
これにはすごく共感した。
さらに、今回の講義で課題が出された。それは、「1年間で20枚の返事がくるようにする」
というものである。井上社長によると、1%の確率で返事が来るらしいので、
最低200枚のはがきや手紙を送らなければ、目標は達成しないのである。そのため、
如何に返事がくるような文の構成を考えていくことが必要である。
そして、言葉遣いも考える必要がある。ですので、早急に取り掛かります。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
--------------------------------------------------------
高岡先生は、ラリー業界の重鎮である。プロ時代の頃は、
多くの成績を残された人で、現役を知り添えた後、バッテリーの研究をされている。
最近は、そのバッテリーが完成されて、これから販売に取り掛かることを伺った。
・演出とストーリー
高岡先生は、ご自身で50台の製造を手掛けて販売をし、
広告などがないということで、全国、8か所でイベントを開催した。
その時のアンケートに、「この車を購入したいですか?」というのを書き、
実際に850台を販売に取り付けたのである。
これは、とてもすごい事である。人は追い込まれたときに、ものすごいエネルギーを
放出するのであると感じた。また、販売方法に関しても、その車のストーリーを考え、
演出することで、消費者に「買いたい」と思わせることが何よりも大切である。
私も、999億円を稼ぐにはストーリー性と演出が一番必要であると感じるので、
3年間で身に付け、世界に名を残す人物になる。
・プロになるには・・
プロというのはビジネスのプロである。同じことをしている業種や人がライバルである。
そして、必ず、2位ではなく1位を取らなければ売れないからである。
それでは、どのようにすれば、ライバルに勝てるのか。
それは、ライバルより研究を繰り返し、発想、誰もしていないことを考えることで、
自ずとライバルとは差が生まれる。だから、高岡先生はすごい人である。
だから、プロのビジネスマンになるよう、業界研究を怠らずに、
隅から隅まで下調べをして、実験を繰り返しするようにしていきます。
●井上吏司社長の「人脈學」
今回は、「人脈學」ということで井上電気の井上社長のお話を伺った。
話の内容は、はがきや手紙を送ることで、人脈の輪が広がることにつながるのである。
実際に、手紙やはがきは書く機会がほとんどなく、書き方さえ知らないという現状である。
よって、今回の講義はとても大切である。
また、あらかじめ与えることが大切であると教わった。
何を与えるのかというと、人脈を与えれば、いずれ人脈が与えられることに。
そして、人を大事にすることを教わった。私自身も
これにはすごく共感した。
さらに、今回の講義で課題が出された。それは、「1年間で20枚の返事がくるようにする」
というものである。井上社長によると、1%の確率で返事が来るらしいので、
最低200枚のはがきや手紙を送らなければ、目標は達成しないのである。そのため、
如何に返事がくるような文の構成を考えていくことが必要である。
そして、言葉遣いも考える必要がある。ですので、早急に取り掛かります。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
--------------------------------------------------------
●物事を成功させるにはストーリーと演出
高岡祥郎先生は、元ラリーレースのドライバーやF1レーサーの監督などを
経験された方で、現在、車のリチウム電池の開発を行っている方です。
高岡さんは今までの経験や人脈を生かして、これまでなかった
新たなバッテリーをほぼ実用化出来る段階まで開発を進めており、
将来このバッテリーが自動車産業に大きな影響を及ぼすことに
なるかもしれないと感じました。
また、今回の高岡さんのお話で1番印象に残った点は、
ビジネスではどんなことでも強きでいき、
海外の人と取引する場合は相手の国がどんな文化なのか知ることが重要なことです。
そして、周りの人の同意を得るには、「ストーリーと演出がないと
どんな物事でも成功しない」と学ばせて頂きました。
●人脈學/井上吏司社長
井上社長は何よりも人脈を大切にされている方で、
井上電気が利益をあげているのも、人脈による部分があります。
色々な会社への繋がりが井上電気を支えていると言っても過言ではないと感じました。
また、井上社長が仰っられた「人を大事すると良いことがある」というお話を聞いて、
私も名刺交換した方々に手紙やハガキを送り、そして、それを継続することで
自分の人脈も広がるのではないかと感じました。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
高岡祥郎先生は、元ラリーレースのドライバーやF1レーサーの監督などを
経験された方で、現在、車のリチウム電池の開発を行っている方です。
高岡さんは今までの経験や人脈を生かして、これまでなかった
新たなバッテリーをほぼ実用化出来る段階まで開発を進めており、
将来このバッテリーが自動車産業に大きな影響を及ぼすことに
なるかもしれないと感じました。
また、今回の高岡さんのお話で1番印象に残った点は、
ビジネスではどんなことでも強きでいき、
海外の人と取引する場合は相手の国がどんな文化なのか知ることが重要なことです。
そして、周りの人の同意を得るには、「ストーリーと演出がないと
どんな物事でも成功しない」と学ばせて頂きました。
●人脈學/井上吏司社長
井上社長は何よりも人脈を大切にされている方で、
井上電気が利益をあげているのも、人脈による部分があります。
色々な会社への繋がりが井上電気を支えていると言っても過言ではないと感じました。
また、井上社長が仰っられた「人を大事すると良いことがある」というお話を聞いて、
私も名刺交換した方々に手紙やハガキを送り、そして、それを継続することで
自分の人脈も広がるのではないかと感じました。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
平成26年(2014)【6月26日(木)】 第3回飛び込み営業研修(実践) クラウドファンディングPJの話し合い
2014/06/26
コメント (0)
----------------------------------------------------------------------
●1日の流れ
9:00 朝礼・清掃
9:30 新聞アウトプット
「米、物言い、日本に照準」
⇒日本に物言いがどう影響を与えるか」
「ミドリムシ燃料始動」
⇒バイオ燃料が増えるとどうなるか」
10:30 飛び込み営業(in五反田)
12:15 昼休憩
13:00 クラウドファンディング話し合い
・各自の企画を詰める
----------------------------------------------------------------------
●次の一手の質問力
【飛び込み営業 第3回目】
最初にRPをして互いの営業姿勢を評価し合った。
私の場合、まずまず明るい姿勢を示せているようなので及第点といったところか。
柳沢くんに対して企業側のRPをやった際に、意地悪になりすぎたと反省。
今回の飛び込み営業では、初めての五反田まわりで、マンションも多く
オフィスビルを探すのに手間取ってしまった。
戦果は、訪問21件、チラシ渡し20件で、ポケットティッシュがなく
チラシのみの営業であるにもかかわらず、今までで最高の数字だった。
事前にアドバイスを受けた「他の学生とも競争していまして…」という泣きが
想像以上に効果的だった。というより、これで粘った相手は全員受け取っていただけた。
案外、同情を引けるものらしい。
本題のコピー機に興味を持って下さった方が、今回は1人いらっしゃった。
そこはスタジオなのでコピー機は置かないとのことだったが、
メンテナンスの事や中古であることなどいくつか質問を受けた。
帰ってきてから、「お詳しいようですが、前に何か関係の仕事をされていたり
したんですか?」などの質問を繋げていたら、さらに掘り下げることが出来ただろう、
とアドバイスを頂いた。
まだまだ、対面すると頭が真っ白になりがちなので、慣れてきたら次の一手、
というか質問を出せるようレベルアップしていきたい。
●とにかく動くこと
【CFプロジェクトの詰め作業】
以前発表したきり進展できていなかった、クラウドファンディングのプロジェクトを
進める作業に入った。
「なぜ自分がやるのか?」とか、「世の中にどのような影響を与えるか?」といった点では、
あまり以前から考えを発展させることは出来なかった。
とにかく最初の一歩を踏み出し、動き出さないと頭も働かないのでは?ということで、
今週中にヘヴィメタルバンド、他のイベント主催者といった方面にコンタクトを取り始めることにした。
その出会いの中から、協力して下さる人を見つけていったり、新たな発想を生み出す
手がかりを見つけていったりできるだろう。
動く。それが今の課題である。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●1日の流れ
9:00 朝礼・清掃
9:30 新聞アウトプット
「米、物言い、日本に照準」
⇒日本に物言いがどう影響を与えるか」
「ミドリムシ燃料始動」
⇒バイオ燃料が増えるとどうなるか」
10:30 飛び込み営業(in五反田)
12:15 昼休憩
13:00 クラウドファンディング話し合い
・各自の企画を詰める
----------------------------------------------------------------------
●次の一手の質問力
【飛び込み営業 第3回目】
最初にRPをして互いの営業姿勢を評価し合った。
私の場合、まずまず明るい姿勢を示せているようなので及第点といったところか。
柳沢くんに対して企業側のRPをやった際に、意地悪になりすぎたと反省。
今回の飛び込み営業では、初めての五反田まわりで、マンションも多く
オフィスビルを探すのに手間取ってしまった。
戦果は、訪問21件、チラシ渡し20件で、ポケットティッシュがなく
チラシのみの営業であるにもかかわらず、今までで最高の数字だった。
事前にアドバイスを受けた「他の学生とも競争していまして…」という泣きが
想像以上に効果的だった。というより、これで粘った相手は全員受け取っていただけた。
案外、同情を引けるものらしい。
本題のコピー機に興味を持って下さった方が、今回は1人いらっしゃった。
そこはスタジオなのでコピー機は置かないとのことだったが、
メンテナンスの事や中古であることなどいくつか質問を受けた。
帰ってきてから、「お詳しいようですが、前に何か関係の仕事をされていたり
したんですか?」などの質問を繋げていたら、さらに掘り下げることが出来ただろう、
とアドバイスを頂いた。
まだまだ、対面すると頭が真っ白になりがちなので、慣れてきたら次の一手、
というか質問を出せるようレベルアップしていきたい。
●とにかく動くこと
【CFプロジェクトの詰め作業】
以前発表したきり進展できていなかった、クラウドファンディングのプロジェクトを
進める作業に入った。
「なぜ自分がやるのか?」とか、「世の中にどのような影響を与えるか?」といった点では、
あまり以前から考えを発展させることは出来なかった。
とにかく最初の一歩を踏み出し、動き出さないと頭も働かないのでは?ということで、
今週中にヘヴィメタルバンド、他のイベント主催者といった方面にコンタクトを取り始めることにした。
その出会いの中から、協力して下さる人を見つけていったり、新たな発想を生み出す
手がかりを見つけていったりできるだろう。
動く。それが今の課題である。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●飛び込み営業(第3弾)
今回の飛び込み営業は五反田で行いました。西新宿とは違い、
飲食店が多くて、とても住みやすいところだと感じた。
また、飛び込み営業で感じたことは大きく分けて2つ。
それは、1つ目は、相手に応援される方法、2つ目は相手と長く話す方法を
考えることです。
・「相手に応援される方法」
学生という身分を最大限に利用することです。
私には特技もなければ相手に誇れるものが何もありません。ですから、唯一、
社会人に許されるであろうことは、学生という身分であると思います。
そして、「他の学生と競争しています」というフレーズは、非常に効果的であると思いました。
もっと応援されるような言葉を考えて、営業をしていきます。
・「相手と長く話す方法」
相手から何かしらの情報を得るということに繋がっていきます。
では、どのようにすれば長く話せるのか…。
1つは、日本ベンチャー大學の話題を提供することや、
自分の素姓を話すことで、相手の警戒心が解くことだと思います。
そして、2つ目は質問力です。
これは、非常に重要であると私は考えています。良い質問をすればするほど
相手の情報を聴くことができるからです。
普段から、質問力を身に付けられる練習をしておかなければいけないです。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
--------------------------------------------------------
●3回目の営業學
3カ所でプリンタについてのご説明が出来ました。
今回で3回目ということで、もう緊張することはなく
スムーズに営業に入ることが出来ました。その理由としては、
前回の営業學とは営業のやり方を変え、
「大學で営業という体験をさせてもらっている」と伝えた事です。
また「挨拶周りとしてチラシを配っている」と言うと、
話を聞く方の態度も変わって、プリンタのご説明を聞いて貰えました。
しかし、プリンタの中身までは、中々興味を持ってもらうことは
出来ませんでした。
そのため、次回の営業學では、営業先の方にどのようにして
興味を持ってもらうか、また、まだ目標枚数を1回も達成出来てない
ので、次回の営業學ではぜひ達成したいと感じました。
●クラウドファンディングプロジェクトの話し合い
クラウドファンディングの自分のプロジェクトを詰めましたが、
前回の事業発表会から、私のプロジェクトがあまり進んでいないと感じました。
そのため、今回の時間を使って、もう1度自分のプロジェクトに対する
想いを文章に書くことで再確認しました。
また、プロジェクトの中身に関しても、声優さんを男女1人ずつ
出演してもらうことや、高額なリターンはイベントのチケットを
予定しているため、イベントの参加者から当日のチケット代を徴収するなどの
変更を取り入れて、イベントの内容として入れることにしました。
そして、当日は花火を行なうため、イベントは夏休みの最後の日である
8月31日を目標にプロジェクトを進めていきます。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
今回の飛び込み営業は五反田で行いました。西新宿とは違い、
飲食店が多くて、とても住みやすいところだと感じた。
また、飛び込み営業で感じたことは大きく分けて2つ。
それは、1つ目は、相手に応援される方法、2つ目は相手と長く話す方法を
考えることです。
・「相手に応援される方法」
学生という身分を最大限に利用することです。
私には特技もなければ相手に誇れるものが何もありません。ですから、唯一、
社会人に許されるであろうことは、学生という身分であると思います。
そして、「他の学生と競争しています」というフレーズは、非常に効果的であると思いました。
もっと応援されるような言葉を考えて、営業をしていきます。
・「相手と長く話す方法」
相手から何かしらの情報を得るということに繋がっていきます。
では、どのようにすれば長く話せるのか…。
1つは、日本ベンチャー大學の話題を提供することや、
自分の素姓を話すことで、相手の警戒心が解くことだと思います。
そして、2つ目は質問力です。
これは、非常に重要であると私は考えています。良い質問をすればするほど
相手の情報を聴くことができるからです。
普段から、質問力を身に付けられる練習をしておかなければいけないです。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
--------------------------------------------------------
●3回目の営業學
3カ所でプリンタについてのご説明が出来ました。
今回で3回目ということで、もう緊張することはなく
スムーズに営業に入ることが出来ました。その理由としては、
前回の営業學とは営業のやり方を変え、
「大學で営業という体験をさせてもらっている」と伝えた事です。
また「挨拶周りとしてチラシを配っている」と言うと、
話を聞く方の態度も変わって、プリンタのご説明を聞いて貰えました。
しかし、プリンタの中身までは、中々興味を持ってもらうことは
出来ませんでした。
そのため、次回の営業學では、営業先の方にどのようにして
興味を持ってもらうか、また、まだ目標枚数を1回も達成出来てない
ので、次回の営業學ではぜひ達成したいと感じました。
●クラウドファンディングプロジェクトの話し合い
クラウドファンディングの自分のプロジェクトを詰めましたが、
前回の事業発表会から、私のプロジェクトがあまり進んでいないと感じました。
そのため、今回の時間を使って、もう1度自分のプロジェクトに対する
想いを文章に書くことで再確認しました。
また、プロジェクトの中身に関しても、声優さんを男女1人ずつ
出演してもらうことや、高額なリターンはイベントのチケットを
予定しているため、イベントの参加者から当日のチケット代を徴収するなどの
変更を取り入れて、イベントの内容として入れることにしました。
そして、当日は花火を行なうため、イベントは夏休みの最後の日である
8月31日を目標にプロジェクトを進めていきます。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------

 RSS 2.0
RSS 2.0












