東京校の講義レポート
令和2年(2020)【10月27日(火) 】吉田松陰先生ゆかりの地めぐり
2020/10/27
コメント (0)
1. 先日の出来事
・吉田松陰先生ゆかりの地めぐり
2. 気付き
「時代は変わっても、時間と場所は変わらない」
先日、わたしは吉田松陰先生ゆかりの地をめぐった。自分では行かないであろう場所に行き、詳しくひとつひとつ説明していただけたことが大きな学びとなり、知識となった。6時間にもわたり吉田松陰ゆかりの地をめぐったが、あれから1日が経ち一番心に残っていることは何かと聞かれたら、吉田松陰先生を通していろんな人と出会ってお話をしたことであると答える。
このように参加者の世代はそれぞれだったが、吉田松陰のゆかりの地をめぐるという同じものを見て・感じて・共有したことが、今元さんが最初に仰られてた「時代は変わっても、時間と場所は変わらない」という言葉にもしかしたら当てはまるのでないかと思った。
それぞれ生まれてきた、そして育ってきた時代は違っても、今私たちが生きてる時間と場所は変わらない。
始め、学生ひとりな上に女ひとりという非常に心細くて不安だったが、私の全く知らない世界に足を踏み入れてる大人の方々との会話は刺激があり貴重であり振り返ってみればすごく幸せな時間であった。参加してすごくよかった。もしこのような機会がまたあれば参加したいと思うし、他の学生の方にもとりあえず足を運んでみることを是非オススメする。
3. 実行したいこと
参加者の方たちは、受け身ではなく能動的に動いていたことがとても印象的だった。私ももっともっと「質問」をたくさんすればよかったと思った。だからこれからはもっと能動的に動き、「質問」をたくさんできるようにしたい。
清泉女子大学文学部
M.K
・吉田松陰先生ゆかりの地めぐり
2. 気付き
「時代は変わっても、時間と場所は変わらない」
先日、わたしは吉田松陰先生ゆかりの地をめぐった。自分では行かないであろう場所に行き、詳しくひとつひとつ説明していただけたことが大きな学びとなり、知識となった。6時間にもわたり吉田松陰ゆかりの地をめぐったが、あれから1日が経ち一番心に残っていることは何かと聞かれたら、吉田松陰先生を通していろんな人と出会ってお話をしたことであると答える。
このように参加者の世代はそれぞれだったが、吉田松陰のゆかりの地をめぐるという同じものを見て・感じて・共有したことが、今元さんが最初に仰られてた「時代は変わっても、時間と場所は変わらない」という言葉にもしかしたら当てはまるのでないかと思った。
それぞれ生まれてきた、そして育ってきた時代は違っても、今私たちが生きてる時間と場所は変わらない。
始め、学生ひとりな上に女ひとりという非常に心細くて不安だったが、私の全く知らない世界に足を踏み入れてる大人の方々との会話は刺激があり貴重であり振り返ってみればすごく幸せな時間であった。参加してすごくよかった。もしこのような機会がまたあれば参加したいと思うし、他の学生の方にもとりあえず足を運んでみることを是非オススメする。
3. 実行したいこと
参加者の方たちは、受け身ではなく能動的に動いていたことがとても印象的だった。私ももっともっと「質問」をたくさんすればよかったと思った。だからこれからはもっと能動的に動き、「質問」をたくさんできるようにしたい。
清泉女子大学文学部
M.K
令和2年(2020)【10月22日(木) 】秋の出版編集トレーニング3日目 4期生5組
2020/10/22
コメント (0)
------------------------------------------------------
令和2年(2020)【10月22日(木)】
秋の出版編集トレーニング3日目
4期生5組
--------------------------------------------------------
《掌の上から本質へ》
本日は新聞に書かれていることを忠実に読み取るように意識して臨んだのですが、
これからは、よりその記事が世間のどのような変化を表しているかを読み取れるようにします。
誰が得で、誰が損をしていて、それは誰が操作しているのか、という言葉が印象的でした。
あらゆる記事の中の殆どが人為的に発生した出来事について書いていることを改めて認識しました。
《人と文章は一致しているか?》
人事の方は文章を読んでその人柄を掴むという前提をもっと念頭に置く必要があるとわかりました。
また、自分の文章力、語彙力が不足していて、伝えたいことを書き切れていないことも痛感したので、まずは沢山書いてみることからはじめます。
・文字量を書いてから引き算をするという形でESを書く練習をします。また、結論をはっきり一言で表すようにします。
M.T@都留文科大学
--------------------------------------------------------
《自分の位置を知り、そこからどう動くか》
「『なぜ』そうなるのか、物事の本質を捉える」「斜め上から考えて俯瞰する」という話を聞き、
自分は今までいかに狭い視野で生きてきたか、ということに気付かされた。「社会はどういう仕組みで動いているのか」を、
先週と今日とではじめてちゃんと理解した。
また、無理をしてプロの領域に踏み込むのではなく、自分の専門分野の知識を生かして話をつなげた方がより確実であり、
企業が知りたい自分の適性やその人らしさを見せることができるということも知った。
また、自分の文章にはまだまだ改善の余地があることもひしひしと感じた。
今までもなんとなく感じていたことではあるが、自分の文章は「基礎」段階で止まっていることを改めて実感し、
その先へ行けるようこれからブラッシュアップしていく必要があると強く感じた。
・新聞を継続して読む。
・「なぜそうなるのか」という視点を持ち、ニュースでもそれ以外のことでも、情報を受け取るだけでなく物事を俯瞰して考える癖を普段からつける。
・1番言いたいことの結論をコンパクトに、(できればインパクトも意識して)最初に伝えてから話す、ということを普段の会話の中でも実行する
・春秋を定期的に読んで文章の書き方を学びとるようにする。
・本を今よりたくさん読むなどして語彙力を増やす。
A.U@武庫川女子大学
令和2年(2020)【10月22日(木)】
秋の出版編集トレーニング3日目
4期生5組
--------------------------------------------------------
《掌の上から本質へ》
本日は新聞に書かれていることを忠実に読み取るように意識して臨んだのですが、
これからは、よりその記事が世間のどのような変化を表しているかを読み取れるようにします。
誰が得で、誰が損をしていて、それは誰が操作しているのか、という言葉が印象的でした。
あらゆる記事の中の殆どが人為的に発生した出来事について書いていることを改めて認識しました。
《人と文章は一致しているか?》
人事の方は文章を読んでその人柄を掴むという前提をもっと念頭に置く必要があるとわかりました。
また、自分の文章力、語彙力が不足していて、伝えたいことを書き切れていないことも痛感したので、まずは沢山書いてみることからはじめます。
・文字量を書いてから引き算をするという形でESを書く練習をします。また、結論をはっきり一言で表すようにします。
M.T@都留文科大学
--------------------------------------------------------
《自分の位置を知り、そこからどう動くか》
「『なぜ』そうなるのか、物事の本質を捉える」「斜め上から考えて俯瞰する」という話を聞き、
自分は今までいかに狭い視野で生きてきたか、ということに気付かされた。「社会はどういう仕組みで動いているのか」を、
先週と今日とではじめてちゃんと理解した。
また、無理をしてプロの領域に踏み込むのではなく、自分の専門分野の知識を生かして話をつなげた方がより確実であり、
企業が知りたい自分の適性やその人らしさを見せることができるということも知った。
また、自分の文章にはまだまだ改善の余地があることもひしひしと感じた。
今までもなんとなく感じていたことではあるが、自分の文章は「基礎」段階で止まっていることを改めて実感し、
その先へ行けるようこれからブラッシュアップしていく必要があると強く感じた。
・新聞を継続して読む。
・「なぜそうなるのか」という視点を持ち、ニュースでもそれ以外のことでも、情報を受け取るだけでなく物事を俯瞰して考える癖を普段からつける。
・1番言いたいことの結論をコンパクトに、(できればインパクトも意識して)最初に伝えてから話す、ということを普段の会話の中でも実行する
・春秋を定期的に読んで文章の書き方を学びとるようにする。
・本を今よりたくさん読むなどして語彙力を増やす。
A.U@武庫川女子大学
新聞アウトプットは本質を考えていくことも必要であるということとESを書くときは400字と言われたら、395以上〜400以内で書く。
・次回、アウトプットもESも今回の気付きを活かして書く。
T.I@近畿大学
--------------------------------------------------------
《本質を読み取る》
今回も新聞アウトプットで貴重なお話を聞くことができました。
どうしてだろうということを深く考え、誰が得して誰が損するなど新聞から連想して考えることが大切だと分かりました。
ESでは気になるニュースなどを聞かれる際に意外性や関連がないようなニュースを取り上げて関連性を取り上げることも学びました。
・次回、新聞アウトプットではどうしてだろうという深掘りをしっかりします。
K.I@相模女子大学
--------------------------------------------------------
《物事の本質を見極めよ》
なぜこのテーマが1面にあるのか、なぜこのテーマが大きく書かれているのか。それを考えることが何よりも大切なことだと今回気づいた。
今回1面のはじめに来ていた記事は「2050年までに二酸化炭素の実質ゼロ」についてだった。
ここで考えるべきは「実質ゼロ」が計画通りいくのかではなく、なぜこの記事がはじめにきたかのかだった。
すると見えてきたのは、この発表により今後日本がどう動いていくかであり、またこれを知ることで企業の動きがわかった。
だから1面にこの記事があるのだ。これが今回学んだ「物事の本質を見極めよ」である。
・新聞を読んだ後、なぜ一面にこの記事がきているのかを考える。
M.K@清泉女子大学
・次回、アウトプットもESも今回の気付きを活かして書く。
T.I@近畿大学
--------------------------------------------------------
《本質を読み取る》
今回も新聞アウトプットで貴重なお話を聞くことができました。
どうしてだろうということを深く考え、誰が得して誰が損するなど新聞から連想して考えることが大切だと分かりました。
ESでは気になるニュースなどを聞かれる際に意外性や関連がないようなニュースを取り上げて関連性を取り上げることも学びました。
・次回、新聞アウトプットではどうしてだろうという深掘りをしっかりします。
K.I@相模女子大学
--------------------------------------------------------
《物事の本質を見極めよ》
なぜこのテーマが1面にあるのか、なぜこのテーマが大きく書かれているのか。それを考えることが何よりも大切なことだと今回気づいた。
今回1面のはじめに来ていた記事は「2050年までに二酸化炭素の実質ゼロ」についてだった。
ここで考えるべきは「実質ゼロ」が計画通りいくのかではなく、なぜこの記事がはじめにきたかのかだった。
すると見えてきたのは、この発表により今後日本がどう動いていくかであり、またこれを知ることで企業の動きがわかった。
だから1面にこの記事があるのだ。これが今回学んだ「物事の本質を見極めよ」である。
・新聞を読んだ後、なぜ一面にこの記事がきているのかを考える。
M.K@清泉女子大学
令和2年(2020)【10月15日(木) 】秋の出版編集トレーニング2日目 4期生5組
2020/10/15
コメント (0)
------------------------------------------------------
令和2年(2020)【10月15日(木)】
秋の出版編集トレーニング2日目
4期生5組
--------------------------------------------------------
《解像度の上げ方》
これまで新聞に対して「読んだ方がいいもの」という漠然とした認識を持っていましたが、
どのように読むべきか、どこを読むべきかという話を聞いたことによって、
自分の中で新聞に対するイメージの解像度が上がったように感じます。新聞に限らず、
「やった方がいいこと」の解像度を上げることが、新しく物事を始めるために必要だと感じました。
・今日から毎日、新聞を読むことを通してインプット・アウトプットの習慣をつけます。
明日に先延ばしすることなく、「今日のうちに」の意識を持ってあたります。
R.M@武蔵野大学
--------------------------------------------------------
《知らないことを話すって難しい》
今日は当たり前のことを改めて知った。
新聞のアウトプットでわかったのは自分が元から知っていた事柄の新聞を読むのは、理解するのは、意見するのはそう難しくなかった。
しかし、この議論について述べましょうと言われたとき、自分が大して興味がないもの、知識がないものだとまず2分半で理解することすら難しかった。
そこから意見を述べるってなったとき、どうしても前の人が述べていたことについて考えたことになってしまい、
イマイチ新聞を読んでの意見がうまくいえなかった。
また知識が不十分なためより自分で話しててうまく人に説明できないというのがすごく悔しいと感じた。しっかり相手に分かりやすく伝える力をつけたい。
・文章力をつけたいという思いが強いから、仰っていた「春秋」を写し書きしようと思う。そして新聞記事の気になる事柄を家族と議論したい。
M.K@清泉女子大学
--------------------------------------------------------
新聞アウトプットでお話しいただいた意見を言うのではなく、
気づいたことや初めて知ったことを出すということを心がけていたつもりでしたが、まだできていないことに気づきました。
・日経新聞の購読(親に相談)
・ワールドビジネスサテライトを見る
・敬語の上達
T.I@近畿大学
令和2年(2020)【10月15日(木)】
秋の出版編集トレーニング2日目
4期生5組
--------------------------------------------------------
《解像度の上げ方》
これまで新聞に対して「読んだ方がいいもの」という漠然とした認識を持っていましたが、
どのように読むべきか、どこを読むべきかという話を聞いたことによって、
自分の中で新聞に対するイメージの解像度が上がったように感じます。新聞に限らず、
「やった方がいいこと」の解像度を上げることが、新しく物事を始めるために必要だと感じました。
・今日から毎日、新聞を読むことを通してインプット・アウトプットの習慣をつけます。
明日に先延ばしすることなく、「今日のうちに」の意識を持ってあたります。
R.M@武蔵野大学
--------------------------------------------------------
《知らないことを話すって難しい》
今日は当たり前のことを改めて知った。
新聞のアウトプットでわかったのは自分が元から知っていた事柄の新聞を読むのは、理解するのは、意見するのはそう難しくなかった。
しかし、この議論について述べましょうと言われたとき、自分が大して興味がないもの、知識がないものだとまず2分半で理解することすら難しかった。
そこから意見を述べるってなったとき、どうしても前の人が述べていたことについて考えたことになってしまい、
イマイチ新聞を読んでの意見がうまくいえなかった。
また知識が不十分なためより自分で話しててうまく人に説明できないというのがすごく悔しいと感じた。しっかり相手に分かりやすく伝える力をつけたい。
・文章力をつけたいという思いが強いから、仰っていた「春秋」を写し書きしようと思う。そして新聞記事の気になる事柄を家族と議論したい。
M.K@清泉女子大学
--------------------------------------------------------
新聞アウトプットでお話しいただいた意見を言うのではなく、
気づいたことや初めて知ったことを出すということを心がけていたつもりでしたが、まだできていないことに気づきました。
・日経新聞の購読(親に相談)
・ワールドビジネスサテライトを見る
・敬語の上達
T.I@近畿大学
《毎日新聞を読むこと、ニュースを見ること》
「経済」とは経世済民(世のため、人のために動くこと)の略であり、
また社会人になるということはその経済活動に参画することである、ということを知った。
そして、世のため人のために新しいものを生み出すには「今」をちゃんと知る必要があることを学び、新聞を読む意義を理解することができた。
・日経新聞の一面を必ず読む。
(特に時間がない時はタイトルだけでも読む。時間に余裕があれば二、三面の総合、さらに余裕があれば政治・経済・国際を中心に読み進める。
日経新聞を読む代わりにワールドビジネスサテライトを見るのも可。勿論、ワールドビジネスサテライトと日経新聞の両方をチェックすると尚良し。)
・文章力を上げたいので、春秋を読む。
・ダ・ヴィンチニュースのサイトを1日1回は開き、ざっと見て、気になった記事があったら読んでみる。
A.U@武庫川女子大学
--------------------------------------------------------
《経済》
私は今まで新聞を読むことがなく、ニュースも見ないで過ごしてきたけれど、今日の講座を受けてどれだけ今を知ることが大事かを知ることができました。
新しいものを作る際には経済を知ることで今起きていることや過去にあったことをを把握し、社会の流れを理解することが必要だと学びました。
・毎日新聞を読むこと
・ニュースを見ること
K.I@相模女子大学
「経済」とは経世済民(世のため、人のために動くこと)の略であり、
また社会人になるということはその経済活動に参画することである、ということを知った。
そして、世のため人のために新しいものを生み出すには「今」をちゃんと知る必要があることを学び、新聞を読む意義を理解することができた。
・日経新聞の一面を必ず読む。
(特に時間がない時はタイトルだけでも読む。時間に余裕があれば二、三面の総合、さらに余裕があれば政治・経済・国際を中心に読み進める。
日経新聞を読む代わりにワールドビジネスサテライトを見るのも可。勿論、ワールドビジネスサテライトと日経新聞の両方をチェックすると尚良し。)
・文章力を上げたいので、春秋を読む。
・ダ・ヴィンチニュースのサイトを1日1回は開き、ざっと見て、気になった記事があったら読んでみる。
A.U@武庫川女子大学
--------------------------------------------------------
《経済》
私は今まで新聞を読むことがなく、ニュースも見ないで過ごしてきたけれど、今日の講座を受けてどれだけ今を知ることが大事かを知ることができました。
新しいものを作る際には経済を知ることで今起きていることや過去にあったことをを把握し、社会の流れを理解することが必要だと学びました。
・毎日新聞を読むこと
・ニュースを見ること
K.I@相模女子大学
《新聞を読む》
私は新聞を読むことが苦手だった。最初から最後まで読み切ることを「新聞を読む」ということだと思っていたからだ。
しかし、今日新聞の読み方を聞き、1面から9面までの大局を掴むという読み方を学んだ。
こうすることで漠然と新聞を読み進めるより効率よく現在のトピックを知れるのだ。
これを聞いて新聞の扱い方がわかった気がして、これなら新聞を読む習慣がつきそうだと思った。
・教えてもらった通りに新聞を読む
・ダ・ヴィンチを買ってみる
・WBSを見る
N.O@愛知大学
--------------------------------------------------------
《「知らなかった」こそが大事》
初めての新聞アウトプットで、本日は記事を読んで思いつくままに発言してしまったのですが、
そもそも経済について知識があまりにも足りないことに気づかされました。
「経済」の言葉の意味もお話の中ででてきましたが、理解していなかったことを知ること、
人の気づきをインプットすることが第一歩として大切であるとわかりました。
《「知る」ことが自己実現に繋がる》
今までは何となく文章を書く仕事がしたいと思っていたり、具体的に自分が将来何を実現したいのかがわからなくて悩んでいたりしたのですが、
まずは過去の、今の日本を知ることから始まるというお言葉が胸に刺さりました。
それをしないまま新しい何かを作り出したり、成し遂げたりすることはできないというのが本当にその通りだなと感じました。
・日本の政治・経済・国際について、毎日知識を得るようにします。
また、知らないことをごまかさずに積極的に質問していくようにします。
M.T@都留文科大学
私は新聞を読むことが苦手だった。最初から最後まで読み切ることを「新聞を読む」ということだと思っていたからだ。
しかし、今日新聞の読み方を聞き、1面から9面までの大局を掴むという読み方を学んだ。
こうすることで漠然と新聞を読み進めるより効率よく現在のトピックを知れるのだ。
これを聞いて新聞の扱い方がわかった気がして、これなら新聞を読む習慣がつきそうだと思った。
・教えてもらった通りに新聞を読む
・ダ・ヴィンチを買ってみる
・WBSを見る
N.O@愛知大学
--------------------------------------------------------
《「知らなかった」こそが大事》
初めての新聞アウトプットで、本日は記事を読んで思いつくままに発言してしまったのですが、
そもそも経済について知識があまりにも足りないことに気づかされました。
「経済」の言葉の意味もお話の中ででてきましたが、理解していなかったことを知ること、
人の気づきをインプットすることが第一歩として大切であるとわかりました。
《「知る」ことが自己実現に繋がる》
今までは何となく文章を書く仕事がしたいと思っていたり、具体的に自分が将来何を実現したいのかがわからなくて悩んでいたりしたのですが、
まずは過去の、今の日本を知ることから始まるというお言葉が胸に刺さりました。
それをしないまま新しい何かを作り出したり、成し遂げたりすることはできないというのが本当にその通りだなと感じました。
・日本の政治・経済・国際について、毎日知識を得るようにします。
また、知らないことをごまかさずに積極的に質問していくようにします。
M.T@都留文科大学
令和2年(2020)【10月13日(火) 】秋の出版編集トレーニング2日目 4期生4組
2020/10/13
コメント (0)
------------------------------------------------------
令和2年(2020)【10月13日(火)】
秋の出版編集トレーニング2日目
4期生4組
--------------------------------------------------------
《新聞の重要性》
私は今まで、新聞を読む習慣がありませんでした。
しかし、今回のお話を聞いて、新聞で現在経済や、昨日の出来事を知ることによって、未来の予測ができると聞いて、新聞の重要性を理解しました。
そして、未来を知るには、やはり現状をしっかり把握しておく必要があることを改めて理解しました。
《続けること》
新聞は、一度読むだけだなく、毎日続けて読むことに意味があるのだと思いました。これは、新聞だけでなく、色々なことに言えると思います。
毎日少しずつでも、新聞の1面かそれ以上を読むことを続けて、半年後には日本の経済について詳しく知っていたいです。
・日経新聞の1~3面をできるだけ毎日読む。忙しくても1面は読む
・夜11時のニュースを見る
・流通新聞を読む
・出版業界を描いた映画やドラマに触れる
・話を聞いている間、どんなことを質問すべきか考える。何事にも疑問点を持って接する。
M.K@関西大学
--------------------------------------------------------
《社会に出てからの当たり前》
本日の講義を経て、新聞、主に日経新聞を読むことへのモチベーションが上がりました。
主に、日経新聞がどのように構成されていて、どういった優先順位で読み進めていくべきかということ、
日経新聞を読むことがどう役に立っていくのかということについて学びました。
日経新聞について、私は毎週土曜日に開催してくださっている新聞アウトプットの時間をきっかけに、しっかりと読み始めたばかりです。
活字の羅列を読むのは得意な方だと思っているのですが、わからない語を調べたり、どういうことだったかとわからなくなって
もう一度読み直すなどの作業があることで、まだまだ読み進めるのに時間がかかります。
しかし、こうした過程を積むことにも意味があるのだと思いました。特に、本日上がった「経済」という単語を一つ取ったとしても、
いざ説明してくださいと言われた際には、なんとなくの言葉しか出ず、本当の意味というものを知らずに使用していたということに気づかされました。
知識があるかないかは、用語を出したときの反応でわかるとおっしゃっていた通り、自分に自信をつけるためにも知識を習得することは重要であり、
大きな武器になると改めて感じました。また、わからない単語を調べて内容をある程度把握するだけではなく、そこから自分はどういう社会にしたいのか、
そして将来的にどういった社会になりそうかというところまで考えるようにしていきたいと思いました。
日経新聞の一面は、社会に出た際には知っていて当たり前、むしろ知らなければ恥ずかしいという内容であることも踏まえ、
今から日経新聞に目を通すことを習慣化していきたいと思います。徐々にでも、成長を自分で感じるためにも、
まず継続して行うということに重点を置いて日経新聞、そして現代の社会に向き合っていければと思いました。
・日経新聞を購読する
・どんなに忙しいという時にでも、一面だけ読むでもいいので、継続して読む
・わからない単語はわからないままにせず、知識を増やしていく
・記事の内容から、未来のことを予測するような視点も持てるよう意識する
R.S@明治学院大学
令和2年(2020)【10月13日(火)】
秋の出版編集トレーニング2日目
4期生4組
--------------------------------------------------------
《新聞の重要性》
私は今まで、新聞を読む習慣がありませんでした。
しかし、今回のお話を聞いて、新聞で現在経済や、昨日の出来事を知ることによって、未来の予測ができると聞いて、新聞の重要性を理解しました。
そして、未来を知るには、やはり現状をしっかり把握しておく必要があることを改めて理解しました。
《続けること》
新聞は、一度読むだけだなく、毎日続けて読むことに意味があるのだと思いました。これは、新聞だけでなく、色々なことに言えると思います。
毎日少しずつでも、新聞の1面かそれ以上を読むことを続けて、半年後には日本の経済について詳しく知っていたいです。
・日経新聞の1~3面をできるだけ毎日読む。忙しくても1面は読む
・夜11時のニュースを見る
・流通新聞を読む
・出版業界を描いた映画やドラマに触れる
・話を聞いている間、どんなことを質問すべきか考える。何事にも疑問点を持って接する。
M.K@関西大学
--------------------------------------------------------
《社会に出てからの当たり前》
本日の講義を経て、新聞、主に日経新聞を読むことへのモチベーションが上がりました。
主に、日経新聞がどのように構成されていて、どういった優先順位で読み進めていくべきかということ、
日経新聞を読むことがどう役に立っていくのかということについて学びました。
日経新聞について、私は毎週土曜日に開催してくださっている新聞アウトプットの時間をきっかけに、しっかりと読み始めたばかりです。
活字の羅列を読むのは得意な方だと思っているのですが、わからない語を調べたり、どういうことだったかとわからなくなって
もう一度読み直すなどの作業があることで、まだまだ読み進めるのに時間がかかります。
しかし、こうした過程を積むことにも意味があるのだと思いました。特に、本日上がった「経済」という単語を一つ取ったとしても、
いざ説明してくださいと言われた際には、なんとなくの言葉しか出ず、本当の意味というものを知らずに使用していたということに気づかされました。
知識があるかないかは、用語を出したときの反応でわかるとおっしゃっていた通り、自分に自信をつけるためにも知識を習得することは重要であり、
大きな武器になると改めて感じました。また、わからない単語を調べて内容をある程度把握するだけではなく、そこから自分はどういう社会にしたいのか、
そして将来的にどういった社会になりそうかというところまで考えるようにしていきたいと思いました。
日経新聞の一面は、社会に出た際には知っていて当たり前、むしろ知らなければ恥ずかしいという内容であることも踏まえ、
今から日経新聞に目を通すことを習慣化していきたいと思います。徐々にでも、成長を自分で感じるためにも、
まず継続して行うということに重点を置いて日経新聞、そして現代の社会に向き合っていければと思いました。
・日経新聞を購読する
・どんなに忙しいという時にでも、一面だけ読むでもいいので、継続して読む
・わからない単語はわからないままにせず、知識を増やしていく
・記事の内容から、未来のことを予測するような視点も持てるよう意識する
R.S@明治学院大学
 《洞察力を鍛えろ》
《洞察力を鍛えろ》今起こっていることが分からなければ新しいものは作れない、という言葉にハッとしました。確かに世の中の現状を知らなければ、
人々に楽しんでもらえるコンテンツは生み出せないと気付きました。
また、その洞察力を鍛えるために新聞を読むことは、社会人になるにあたって大事であることも気付かされました。
《自分のペースでコツコツと》
最初は毎日新聞買って読んでアウトプット、できるかな…と心配でした。
しかし、自分が続けられるやり方でやればいいとアドバイスしていただいて、自分のペースでやっていいんだ、と安心しました。
できるかなと思い留まる前に、自分ができる範囲でまずやってみることが大きな一歩になることに気付きました。
・新聞を読む(自分のペースで)
・読んで学んだことを、人と共有する
・疑問点を持ちながら話を聞き、質問を積極的に投げかける
N.J@都留文科大学
--------------------------------------------------------
《源流》
個人面談を数週間前に終え、日経新聞を読み始めたもののやはり内容が難しく、読んでは概要をノートにまとめる毎日。
自分の考えを書き出すなど到底できず、何度か諦めようと思いました。
しかし今回の講義を終えて、何に着目して読もうとしてたのか改めて考えると、ただひたすら文を追うことしか頭になかったのだとようやく学習しました。
今後も毎日読む上で、今回教えていただいた着眼点など、よく噛み締めて読み進めていこうと思います。
ノートに内容をまとめる際に、ただ真新しいことだけ選出するのではなく、前の日に関わりのある事象と比較し、
次はどんなことが起こりそうかなど、分からなくともまずは自分の頭で何かしら考えます。
S.S@国士舘大学
《洞察力を鍛えろ》
今起こっていることが分からなければ新しいものは作れない、という言葉にハッとしました。確かに世の中の現状を知らなければ、
人々に楽しんでもらえるコンテンツは生み出せないと気付きました。
また、その洞察力を鍛えるために新聞を読むことは、社会人になるにあたって大事であることも気付かされました。
《自分のペースでコツコツと》
最初は毎日新聞買って読んでアウトプット、できるかな…と心配でした。
しかし、自分が続けられるやり方でやればいいとアドバイスしていただいて、自分のペースでやっていいんだ、と安心しました。
できるかなと思い留まる前に、自分ができる範囲でまずやってみることが大きな一歩になることに気付きました。
・新聞を読む(自分のペースで)
・読んで学んだことを、人と共有する
・疑問点を持ちながら話を聞き、質問を積極的に投げかける
N.J@都留文科大学
--------------------------------------------------------
《源流》
個人面談を数週間前に終え、日経新聞を読み始めたもののやはり内容が難しく、読んでは概要をノートにまとめる毎日。
自分の考えを書き出すなど到底できず、何度か諦めようと思いました。
しかし今回の講義を終えて、何に着目して読もうとしてたのか改めて考えると、ただひたすら文を追うことしか頭になかったのだとようやく学習しました。
今後も毎日読む上で、今回教えていただいた着眼点など、よく噛み締めて読み進めていこうと思います。
ノートに内容をまとめる際に、ただ真新しいことだけ選出するのではなく、前の日に関わりのある事象と比較し、
次はどんなことが起こりそうかなど、分からなくともまずは自分の頭で何かしら考えます。
S.S@国士舘大学
今起こっていることが分からなければ新しいものは作れない、という言葉にハッとしました。確かに世の中の現状を知らなければ、
人々に楽しんでもらえるコンテンツは生み出せないと気付きました。
また、その洞察力を鍛えるために新聞を読むことは、社会人になるにあたって大事であることも気付かされました。
《自分のペースでコツコツと》
最初は毎日新聞買って読んでアウトプット、できるかな…と心配でした。
しかし、自分が続けられるやり方でやればいいとアドバイスしていただいて、自分のペースでやっていいんだ、と安心しました。
できるかなと思い留まる前に、自分ができる範囲でまずやってみることが大きな一歩になることに気付きました。
・新聞を読む(自分のペースで)
・読んで学んだことを、人と共有する
・疑問点を持ちながら話を聞き、質問を積極的に投げかける
N.J@都留文科大学
--------------------------------------------------------
《源流》
個人面談を数週間前に終え、日経新聞を読み始めたもののやはり内容が難しく、読んでは概要をノートにまとめる毎日。
自分の考えを書き出すなど到底できず、何度か諦めようと思いました。
しかし今回の講義を終えて、何に着目して読もうとしてたのか改めて考えると、ただひたすら文を追うことしか頭になかったのだとようやく学習しました。
今後も毎日読む上で、今回教えていただいた着眼点など、よく噛み締めて読み進めていこうと思います。
ノートに内容をまとめる際に、ただ真新しいことだけ選出するのではなく、前の日に関わりのある事象と比較し、
次はどんなことが起こりそうかなど、分からなくともまずは自分の頭で何かしら考えます。
S.S@国士舘大学
《もったいない》
今回、新聞アウトプットの意義についての話で、新聞には昨日起こった最新情報が書いてあり、
経済や政治などのトピックスが詰まっている宝庫であるとわかりました。今までの事を知ることで未来の予測ができると言われ、
今までぼんやりと新聞を見るだけだったのはとてももったいないことであると気づきました。
就活のためだけでなく、社会人になってからも、新聞を読んで情報を仕入れることは大切であると気づきました。
《舞台としての出版社》
出版社の雰囲気を知ることができるドラマや映画、漫画を教えていただきました。
いくつかは見たことがあったのですが、私が知っているよりもずっと多くの作品に出版社が登場していました。
ドラマや漫画など、満遍なくどのコンテンツでも出版社が舞台のものがあるということに気づきました。
さらに、働く側と経営している側というふたつの視点があるという言葉を聞いて、
ただ見るだけではなく視点を考えて見ることが大切であると気づきました。
・わからない言葉を学ぶつもりで新聞を読む
・少しでも疑問に思ったことは質問する
・ニュースを見ること、新聞を読むことを継続する
Y.H@関西学院大学
--------------------------------------------------------
《新聞の情報》
新聞を読む習慣が私にはなかったため、初めての新聞アウトプットでした。
また、新聞は今の情報を詳しく教えてくれる教科書であると言うことを教えていただき確かにと思いました。
新聞は今だけでなく未来も理解することができるものであるため読む習慣をつけていきたいと思った。
《疑問は学びながら考える》
最後に、質問をする機会があったのですが自分はいつも質問ありますか?という場面において質問を出せません。
自分は学んでいるときに教えてもらっている事だけを飲み込むだけであったため自分ではあまり考えていないのかもしれないと思いました。
・学んでいる時に、自分で考える癖をつける。
・新聞を読むことを習慣づける。
・わからないことは調べる癖をつける。
C.W@東洋大学
--------------------------------------------------------
《空虚になっていました》
新聞アウトプットにおいて、ある人が記事内容と田舎の日本の暮らしとの間にある関連性について話していた。
このように、社会の出来事と実践的な物事との結びつきを意識する考えが自分には欠けていると気づいた。
特に私は抽象的な言葉や概念を多く用いてしまい、議論が机上の空論のような空虚さを纏ってしまう。
彼女のように現実世界との具体的なリンクを意識していかなければ、議論が説得性に欠けてしまうと思わされた。
《新聞はストーリーテラー》
新聞が思考の流れを生みだすように構成されていることを知った。
まずは経済を行う際の基盤である政治、それから経済活動、そして外的要因としての国際問題へと読み手の視点を誘導しているとは見事だ。
社会を一つのストーリーとしてみると、それまで分断されて難しく感じていた事象も理解しやすくなるだろう。
今後は新聞に隠されたそうした社会の流れを意識して読んでいきたい。
・抽象的な言葉を避ける事
・分からない言葉の意味をきちんと調べる事
・質問や意見を積極的に言う事
R.T@同志社大学
今回、新聞アウトプットの意義についての話で、新聞には昨日起こった最新情報が書いてあり、
経済や政治などのトピックスが詰まっている宝庫であるとわかりました。今までの事を知ることで未来の予測ができると言われ、
今までぼんやりと新聞を見るだけだったのはとてももったいないことであると気づきました。
就活のためだけでなく、社会人になってからも、新聞を読んで情報を仕入れることは大切であると気づきました。
《舞台としての出版社》
出版社の雰囲気を知ることができるドラマや映画、漫画を教えていただきました。
いくつかは見たことがあったのですが、私が知っているよりもずっと多くの作品に出版社が登場していました。
ドラマや漫画など、満遍なくどのコンテンツでも出版社が舞台のものがあるということに気づきました。
さらに、働く側と経営している側というふたつの視点があるという言葉を聞いて、
ただ見るだけではなく視点を考えて見ることが大切であると気づきました。
・わからない言葉を学ぶつもりで新聞を読む
・少しでも疑問に思ったことは質問する
・ニュースを見ること、新聞を読むことを継続する
Y.H@関西学院大学
--------------------------------------------------------
《新聞の情報》
新聞を読む習慣が私にはなかったため、初めての新聞アウトプットでした。
また、新聞は今の情報を詳しく教えてくれる教科書であると言うことを教えていただき確かにと思いました。
新聞は今だけでなく未来も理解することができるものであるため読む習慣をつけていきたいと思った。
《疑問は学びながら考える》
最後に、質問をする機会があったのですが自分はいつも質問ありますか?という場面において質問を出せません。
自分は学んでいるときに教えてもらっている事だけを飲み込むだけであったため自分ではあまり考えていないのかもしれないと思いました。
・学んでいる時に、自分で考える癖をつける。
・新聞を読むことを習慣づける。
・わからないことは調べる癖をつける。
C.W@東洋大学
--------------------------------------------------------
《空虚になっていました》
新聞アウトプットにおいて、ある人が記事内容と田舎の日本の暮らしとの間にある関連性について話していた。
このように、社会の出来事と実践的な物事との結びつきを意識する考えが自分には欠けていると気づいた。
特に私は抽象的な言葉や概念を多く用いてしまい、議論が机上の空論のような空虚さを纏ってしまう。
彼女のように現実世界との具体的なリンクを意識していかなければ、議論が説得性に欠けてしまうと思わされた。
《新聞はストーリーテラー》
新聞が思考の流れを生みだすように構成されていることを知った。
まずは経済を行う際の基盤である政治、それから経済活動、そして外的要因としての国際問題へと読み手の視点を誘導しているとは見事だ。
社会を一つのストーリーとしてみると、それまで分断されて難しく感じていた事象も理解しやすくなるだろう。
今後は新聞に隠されたそうした社会の流れを意識して読んでいきたい。
・抽象的な言葉を避ける事
・分からない言葉の意味をきちんと調べる事
・質問や意見を積極的に言う事
R.T@同志社大学
令和2年(2020)【10月8日(木) 】秋の出版編集トレーニング1日目 4期生5組
2020/10/08
コメント (0)
------------------------------------------------------
令和2年(2020)【10月8日(木)】
秋の出版編集トレーニング1日目
4期生5組
--------------------------------------------------------
《解釈と取捨選択》
「他己紹介の感想」の時間でも触れたが、インパクトのある、そして中身のある他己紹介(発表)をするには、
聞いたことをただそのまま伝えるのではなく、聞いた材料をもとに自分なりに解釈して自分の言葉で本人の特徴を言い表す、
ということが必要であることに気付いた。
また、聞いたこと全てを紹介するのではなく、その人の特徴がより表れていると思う部分をピックアップすることの重要さも実感した。
話題を絞って話すことで、一つ一つの話題が濃いものになり、全体としても意義のある内容になることを理解することができた。
また、今日は全体的に時間オーバーで話してしまったが、先ほど述べたポイントを意識することで、それを改善することもできるのではないか思う。
上記の気付きを意識して、発表の場はもちろん、できれば普段の会話の中でも、工夫のある話し方を明日から少しずつでも実践します。
A.U@武庫川女子大学
--------------------------------------------------------
《鏡》
他己紹介をするのは、聞いたことをまとめる力を鍛えるものだと思っていたが、他人から自分がどう見えるかを知ることもできるのだということに気づいた。
また、自分は自分自身が◯◯な人間だと思っていても、それは鏡に映っている自分であり、左右反対の像である。
したがって正面から見てもらえる機会があってよかった。
とにもかくにも、敬語を練習すること。理想としては、最後に木曜メンバーから敬語が上手くなったと言われるくらいにしたい。
T.I@近畿大学
令和2年(2020)【10月8日(木)】
秋の出版編集トレーニング1日目
4期生5組
--------------------------------------------------------
《解釈と取捨選択》
「他己紹介の感想」の時間でも触れたが、インパクトのある、そして中身のある他己紹介(発表)をするには、
聞いたことをただそのまま伝えるのではなく、聞いた材料をもとに自分なりに解釈して自分の言葉で本人の特徴を言い表す、
ということが必要であることに気付いた。
また、聞いたこと全てを紹介するのではなく、その人の特徴がより表れていると思う部分をピックアップすることの重要さも実感した。
話題を絞って話すことで、一つ一つの話題が濃いものになり、全体としても意義のある内容になることを理解することができた。
また、今日は全体的に時間オーバーで話してしまったが、先ほど述べたポイントを意識することで、それを改善することもできるのではないか思う。
上記の気付きを意識して、発表の場はもちろん、できれば普段の会話の中でも、工夫のある話し方を明日から少しずつでも実践します。
A.U@武庫川女子大学
--------------------------------------------------------
《鏡》
他己紹介をするのは、聞いたことをまとめる力を鍛えるものだと思っていたが、他人から自分がどう見えるかを知ることもできるのだということに気づいた。
また、自分は自分自身が◯◯な人間だと思っていても、それは鏡に映っている自分であり、左右反対の像である。
したがって正面から見てもらえる機会があってよかった。
とにもかくにも、敬語を練習すること。理想としては、最後に木曜メンバーから敬語が上手くなったと言われるくらいにしたい。
T.I@近畿大学
《インパクトが重要》
伝える相手にイメージが湧きやすくするためにもインパクトがあるキャッチコピーや内容を話すことが大切だということが分かりました。
また、先に結論を言うと言うのは文章を書くときには意識していたことですが、話すときには意識していなかったので心掛けたいと思います。
他の人の他己紹介を聞いているととても要約が上手で自分の感じた印象も混ぜて話されていたので、私自身も簡潔に要約してこれからは話せるようにしたいです。
また、緊張せずにリラックスして素の自分を出せるように場慣れしていきたいです。
K.I@相模女子大学
--------------------------------------------------------
《説明と選択》
書籍紹介と他己紹介を通じて、自分が脳内で考えていることを忠実に説明するのは難しいと気づいた。
自分の考えている内容が全員にしかも時間内に伝わるようにするには、自分の脳内にある必要な情報と不必要な情報を取捨選択することが大切であると考える。
・人の話したことはメモをする
・思考をアウトプットする癖をつける
N.O@愛知大学
--------------------------------------------------------
《伝えるって難しい》
他己紹介をしてみて、自分の伝える力の乏しさに気づいた。
内容を簡潔にまとめて制限時間内に発表する、ということはとても難しかった。
自分が得た情報から取捨選択し、相手に分かりやすく伝えるにはまだまだ練習が必要であると学んだ。
また、質問も単に聞くだけではなく、相手から聞き出したい情報は何かを考えながらする必要があることを学んだ。
《インパクトある発表を》
キャッチコピー力が足りないことに気づいた。相手の関心を引きつけるには、インパクトが大事であると学んだ。
続きが気になるような、どういうこと?と思わせるキャッチコピーを考えれるようになれば、より話が面白くなることを学んだ。
・結論は最初に述べる
・制限時間内に伝わるようにまとめる
・インプットしたものはアウトプットする癖をつける
・色々なことに疑問を持つ
N.J@都留文科大学
伝える相手にイメージが湧きやすくするためにもインパクトがあるキャッチコピーや内容を話すことが大切だということが分かりました。
また、先に結論を言うと言うのは文章を書くときには意識していたことですが、話すときには意識していなかったので心掛けたいと思います。
他の人の他己紹介を聞いているととても要約が上手で自分の感じた印象も混ぜて話されていたので、私自身も簡潔に要約してこれからは話せるようにしたいです。
また、緊張せずにリラックスして素の自分を出せるように場慣れしていきたいです。
K.I@相模女子大学
--------------------------------------------------------
《説明と選択》
書籍紹介と他己紹介を通じて、自分が脳内で考えていることを忠実に説明するのは難しいと気づいた。
自分の考えている内容が全員にしかも時間内に伝わるようにするには、自分の脳内にある必要な情報と不必要な情報を取捨選択することが大切であると考える。
・人の話したことはメモをする
・思考をアウトプットする癖をつける
N.O@愛知大学
--------------------------------------------------------
《伝えるって難しい》
他己紹介をしてみて、自分の伝える力の乏しさに気づいた。
内容を簡潔にまとめて制限時間内に発表する、ということはとても難しかった。
自分が得た情報から取捨選択し、相手に分かりやすく伝えるにはまだまだ練習が必要であると学んだ。
また、質問も単に聞くだけではなく、相手から聞き出したい情報は何かを考えながらする必要があることを学んだ。
《インパクトある発表を》
キャッチコピー力が足りないことに気づいた。相手の関心を引きつけるには、インパクトが大事であると学んだ。
続きが気になるような、どういうこと?と思わせるキャッチコピーを考えれるようになれば、より話が面白くなることを学んだ。
・結論は最初に述べる
・制限時間内に伝わるようにまとめる
・インプットしたものはアウトプットする癖をつける
・色々なことに疑問を持つ
N.J@都留文科大学
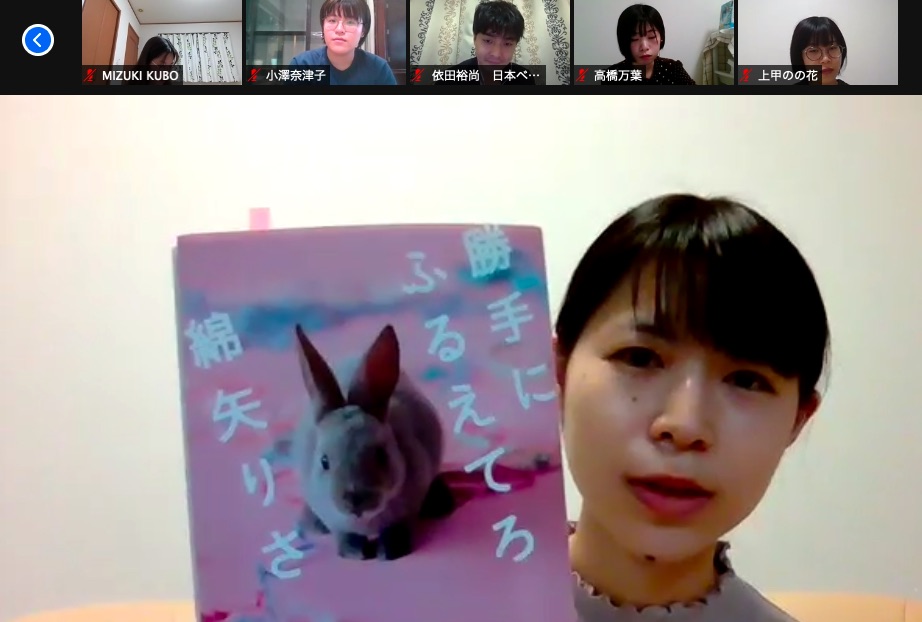 《発想力は、強い》
《発想力は、強い》本の紹介でさまざまな本が紹介されていましたが、とくに板持君の教科書を持ってくるという発想に驚かされました。
アピール文を考える際にも、この他人がすぐには思いつかない独自の発想が大切だと感じました。
また、上甲さんの紹介のときに、世界で5番目に読まれているという情報に引き付けられたので、
どのような順番で伝えるかという発想力も肝心であることがわかりました。
自分の話し方のクセ、弱いところを周りの方に聞いて、まず知るところから始めます。
また、他の方の話し方をよく観察して、良いところを盗んで真似していきます。
M.T@都留文科大学
--------------------------------------------------------
《自分は堂々とした人だった!?》
私は自分の話をするのが大好きだ。
しかし、と同時に話を聞くのも大好きだ。だからずかずかと質問するし、自分も答える。
それを自分自身積極性はあるかもしれないが、すこしばかり図々しいことだと思っていた。
しかし彼女は私を紹介する際、私を堂々とした人だったと語った。正直にとても嬉しかった。
自身堂々とする意識は全くせずただその場を楽しんで話をしていただけなのに、そんな風に感じていたとはびっくりした。
それが大きな発見であり、楽しいと思った。ではそんな他己紹介を聞いた他の方の目にはどのように私が写ったのか次に気になるところだ。
思いをしっかり人へ伝える方法を一から学びたい。そのためにまずは上手い人の話をしっかり聞いてなぜ上手いのかそのわけを考えようと思った。
M.K@清泉女子大学
- < 前
- Page 1 / 2













 RSS 2.0
RSS 2.0












