東京校の講義レポート
平成25年(2013)【12月17日(火)】 日本の経営、教育のあり方/ 高瀬拓士先生(日本コンピュータ開発 相談役最高顧問)
2013/12/17
コメント (0)
●自らにできることを
高瀬先生はご自身のお考えを惜しみなく主張される。
しかし、それは強要ではない。
私たちに先生ご自身の提示してくださる。
私利私欲のためではなく、公のために動く。
4度目の講義となった今回、受けさせていただく度に先生の偉大さを実感する。
この日は「経営」というテーマで、先生は、単に儲けるためではなく、問題認識を持ち、それを何とかしたいから経営をしているのだ、と言われる。
会社も社会の一員で、儲かるためだけ社会の仕組みを一方的に利用するというのはおかしい、とおっしゃっていた。
日本では株式会社という仕組みが株主だけのものとなってしまったのが良くないというお話もあった。
企業は社会の公器、株主や経営者だけでなく様々な人のもので、それが自分のものだと思うから、多くの人を不幸にしてしまう。
そのような利己的な考えをなくすことで、関わる人々の幸せへの欲求が満たされるのではないか、と言われる。
また、先生は「国を変えるには教育しかない」ともおっしゃっていて、企業は最高の社会人教育機関で、経営者は教育者でもあるというお話もあった。
教育とは社会人教育以外にも家庭と学校の教育があり、現代の学校の仕組みも変えるべきだと、と。
特に日本の大学の仕組みが生徒に怠け癖をつけるので、否が応でも勉強する高等専門学校や欧米の大学のようにすべきだともおっしゃっていた。
日本は素晴らしい国。
しかし、それを日本人が知らないから、世界の人々も知らない。
他の先進国には類を見ない多神教国家で、人間とそれ以外のものを同じレベルに見て、感謝することができる。
それが素晴らしいという。
日本と他の国とは文化が違うので、例えばアメリカと同じことをしても意味がない。
今の日本人は「考える」という文化がなくなってしまって、それは欧米の真似の文化が定着してしまったからだという。
明治維新以来の近代化は、和魂洋才と表現されるように、日本の文化を大切にしながら、その上に欧米の文化・技術を積極的に取り入れて来たという歴史があるが、今は無魂米才。
考える文化を取り戻す必要がある。
多くの現代の日本の若者は世の中のことに無関心で、過去がそのままこれからも続いていくと思っている。
将来を担っていくのは特に若い人々だ。
私たちが日本を、地球を、人生を考え、社会に対しても責任感を持たなければならない。
私もこれからの社会を生きる上で、自分にできることをする。
世の中のために何ができるだろうかを考えながら、これからも目標に向かって邁進していく。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
高瀬先生はご自身のお考えを惜しみなく主張される。
しかし、それは強要ではない。
私たちに先生ご自身の提示してくださる。
私利私欲のためではなく、公のために動く。
4度目の講義となった今回、受けさせていただく度に先生の偉大さを実感する。
この日は「経営」というテーマで、先生は、単に儲けるためではなく、問題認識を持ち、それを何とかしたいから経営をしているのだ、と言われる。
会社も社会の一員で、儲かるためだけ社会の仕組みを一方的に利用するというのはおかしい、とおっしゃっていた。
日本では株式会社という仕組みが株主だけのものとなってしまったのが良くないというお話もあった。
企業は社会の公器、株主や経営者だけでなく様々な人のもので、それが自分のものだと思うから、多くの人を不幸にしてしまう。
そのような利己的な考えをなくすことで、関わる人々の幸せへの欲求が満たされるのではないか、と言われる。
また、先生は「国を変えるには教育しかない」ともおっしゃっていて、企業は最高の社会人教育機関で、経営者は教育者でもあるというお話もあった。
教育とは社会人教育以外にも家庭と学校の教育があり、現代の学校の仕組みも変えるべきだと、と。
特に日本の大学の仕組みが生徒に怠け癖をつけるので、否が応でも勉強する高等専門学校や欧米の大学のようにすべきだともおっしゃっていた。
日本は素晴らしい国。
しかし、それを日本人が知らないから、世界の人々も知らない。
他の先進国には類を見ない多神教国家で、人間とそれ以外のものを同じレベルに見て、感謝することができる。
それが素晴らしいという。
日本と他の国とは文化が違うので、例えばアメリカと同じことをしても意味がない。
今の日本人は「考える」という文化がなくなってしまって、それは欧米の真似の文化が定着してしまったからだという。
明治維新以来の近代化は、和魂洋才と表現されるように、日本の文化を大切にしながら、その上に欧米の文化・技術を積極的に取り入れて来たという歴史があるが、今は無魂米才。
考える文化を取り戻す必要がある。
多くの現代の日本の若者は世の中のことに無関心で、過去がそのままこれからも続いていくと思っている。
将来を担っていくのは特に若い人々だ。
私たちが日本を、地球を、人生を考え、社会に対しても責任感を持たなければならない。
私もこれからの社会を生きる上で、自分にできることをする。
世の中のために何ができるだろうかを考えながら、これからも目標に向かって邁進していく。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
●考える力、習慣
経営問題が主題の講義の中で、日本の大学教育のあり方についても講義して頂いた。
大学を卒業した学士が、自ら考える力や習慣を持たない、と言われる。
就活においても大学側では、「こうすればうまくいく、内定が取れる」などと、就職ガイダンスで色々と与え過ぎて、大学生も言われた通り就活を行う。
出版社も本を売るためハウツー本ばかりを出していった結果は、自分で考える力や習慣を持たずに社会に出る、という日本になっている というお話だった。
色々な情報を安易に鵜呑みにしたりせず、また学生も考える習慣を無くし答えを安易に求めずに、自分で考え結論に辿り着く必要があると感じた。
●企業は誰のものか (誤解あるいは表現力のまずさを感じ、だいぶ修正を加えました。)
企業の役割についても、お話をして頂いた。
会社は、経営者によってそのあり方が大きく変わる。国家、学校、地方自治体… など、どれを取っても同じことだ。
日本の企業は、アメリカ式経営の導入で会社は株主のものだという考えが当たり前になり、経営者が株主の発言に大きく影響されるようになった。文化的背景の異なる日本では、会社は社会の公器であり、株主のものという考えだけではいけないのではないかという事だった。
誰であれ、企業や組織を自分のものと誤解してはいけない。
そう陥ってしまわぬよう気をつけなければならないと感じた。
また高瀬先生より、書籍『日本で一番大切にしたい会社』に掲載された障害者雇用率が高いことによって表彰された会社についてのお話もして頂く。
単に雇用率が高いというだけで、職場環境や処遇面での実態評価が見落とされているのではないかという疑問がある との話があった。
数字だけを見て、すべてを理解してはいけない。
高瀬先生がいくつかの作業現場を訪ねて見たら、作業環境の悪い中で長時間にわたって立って作業をしているという会社もあった。
自分だけが利益を上げようと自分を大きくみせたり、会社を、社員を自分の思い通りに動かしてしまうと、いつか行き詰まってしまうと感じる。
高瀬先生が提案するのは、地球も会社同様、一つの集団であるという考え方だ。
自分達が自分達のためだけを考え過ぎているならそれを改め、会社が誰のものでもないという見方で誠実に活動するべきなのだと感じた。
From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)
---------------------------------------------------------------------------
経営問題が主題の講義の中で、日本の大学教育のあり方についても講義して頂いた。
大学を卒業した学士が、自ら考える力や習慣を持たない、と言われる。
就活においても大学側では、「こうすればうまくいく、内定が取れる」などと、就職ガイダンスで色々と与え過ぎて、大学生も言われた通り就活を行う。
出版社も本を売るためハウツー本ばかりを出していった結果は、自分で考える力や習慣を持たずに社会に出る、という日本になっている というお話だった。
色々な情報を安易に鵜呑みにしたりせず、また学生も考える習慣を無くし答えを安易に求めずに、自分で考え結論に辿り着く必要があると感じた。
●企業は誰のものか (誤解あるいは表現力のまずさを感じ、だいぶ修正を加えました。)
企業の役割についても、お話をして頂いた。
会社は、経営者によってそのあり方が大きく変わる。国家、学校、地方自治体… など、どれを取っても同じことだ。
日本の企業は、アメリカ式経営の導入で会社は株主のものだという考えが当たり前になり、経営者が株主の発言に大きく影響されるようになった。文化的背景の異なる日本では、会社は社会の公器であり、株主のものという考えだけではいけないのではないかという事だった。
誰であれ、企業や組織を自分のものと誤解してはいけない。
そう陥ってしまわぬよう気をつけなければならないと感じた。
また高瀬先生より、書籍『日本で一番大切にしたい会社』に掲載された障害者雇用率が高いことによって表彰された会社についてのお話もして頂く。
単に雇用率が高いというだけで、職場環境や処遇面での実態評価が見落とされているのではないかという疑問がある との話があった。
数字だけを見て、すべてを理解してはいけない。
高瀬先生がいくつかの作業現場を訪ねて見たら、作業環境の悪い中で長時間にわたって立って作業をしているという会社もあった。
自分だけが利益を上げようと自分を大きくみせたり、会社を、社員を自分の思い通りに動かしてしまうと、いつか行き詰まってしまうと感じる。
高瀬先生が提案するのは、地球も会社同様、一つの集団であるという考え方だ。
自分達が自分達のためだけを考え過ぎているならそれを改め、会社が誰のものでもないという見方で誠実に活動するべきなのだと感じた。
From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)
---------------------------------------------------------------------------
●高瀬先生の講義
高瀬先生は「あるべき姿」という言葉を多く使われた。
企業のあるべき姿、親のあるべき姿、そして大学生のあるべき姿。
それぞれ最高の教育機関であったり、子にお金ではなく愛情を一杯かけ、
苦労させるべきであったり、空いた時間でとにかく勉強すべきであったりと
当たり前のことのはずだ。
しかし、このような当たり前のことであってもハッとさせられた。
これは当たり前のことが皆出来ていないためであろう。
今の自分のあるべき姿を考えることはどんな場面でも役に立つ。
長期的にみて自分のあるべき姿はもちろん、場面場面でも自分が今
どういう行動をとるべきかも考えるようにする。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
●『若者は、青臭くていい。青臭いのが若者の特徴なんだから』
「若者は理想を持って生きて欲しい!」というメッセージを頂きました。
不純な気持ちではなく、自分の純粋な気持ちに従って生きて欲しいと、
高瀬先生は仰られました。
青臭くてもいい。ずる賢く生きるよりも、理想を高く掲げて生きていきたい。
青臭いのは若者の特徴であると教えて頂きました。
若者が安定を求めたり、中途半端なところで妥協したりしていたら、
誰が新しい時代を切り開くのか。
私達若者は、感謝・謙虚という日本の素晴らしい文化を大切に、
理想を掲げて生きていくべきだと気づかせて頂きました!
From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)
---------------------------------------------------
高瀬先生は「あるべき姿」という言葉を多く使われた。
企業のあるべき姿、親のあるべき姿、そして大学生のあるべき姿。
それぞれ最高の教育機関であったり、子にお金ではなく愛情を一杯かけ、
苦労させるべきであったり、空いた時間でとにかく勉強すべきであったりと
当たり前のことのはずだ。
しかし、このような当たり前のことであってもハッとさせられた。
これは当たり前のことが皆出来ていないためであろう。
今の自分のあるべき姿を考えることはどんな場面でも役に立つ。
長期的にみて自分のあるべき姿はもちろん、場面場面でも自分が今
どういう行動をとるべきかも考えるようにする。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
●『若者は、青臭くていい。青臭いのが若者の特徴なんだから』
「若者は理想を持って生きて欲しい!」というメッセージを頂きました。
不純な気持ちではなく、自分の純粋な気持ちに従って生きて欲しいと、
高瀬先生は仰られました。
青臭くてもいい。ずる賢く生きるよりも、理想を高く掲げて生きていきたい。
青臭いのは若者の特徴であると教えて頂きました。
若者が安定を求めたり、中途半端なところで妥協したりしていたら、
誰が新しい時代を切り開くのか。
私達若者は、感謝・謙虚という日本の素晴らしい文化を大切に、
理想を掲げて生きていくべきだと気づかせて頂きました!
From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)
---------------------------------------------------
平成25年(2013)【12月15日(日)】 濱口晴彦先生(文学博士、早稲田大学名誉教授)、芋販売開始
2013/12/15
コメント (0)
 --------------------------------
--------------------------------●1日の流れ
9:00 朝礼
9:15 松陰神社参拝
9:30 掃除、焼き芋開始
10:05 新聞アウトプット
・7面 SC開業 60件超に回復
・3面 国債発行総額 最高へ
11:00 昼食休憩
12:15 濱口先生を松陰神社案内
13:30 濱口晴彦先生の講義
「人生のあいまいさ-その向こうにあるもの」
・あいまいさへの視野
・自我の彷徨、あいまいさの中へ
・人生のあいまいさからの離脱
・あいまいさの向こうにある3つの壁
・あいまいさのフロンティア
・人間の視野
・生まれてから死ぬまでの経路
・幸福に必要な9つの条件
・人生の方程式
15:00 質疑応答
16:00 終礼、解散
--------------------------------
●心のあり方
心のあり方が人、人生を決める。
杉晋作は「おもしろき こともなき世を おもしろく すみなすものは 心なりけり」
という歌で、心のあり方の重要性を歌っている。
また日本の近代化の中で、夏目漱石の教え子であった藤村操は個人主義に適応できず
自殺してしまったという。
作家として活躍した夏目漱石や石川啄木とは違って、心のあり方で命を落としてしまった。
石川啄木が十五歳の心を歌った素晴らしい歌を残している。
「不来方の お城の草に 寝ころびて 空に吸われし 十五の心」
人生の方程式も教えていただいた。
いかにお金、もの、人間関係の値が高くても、それに意欲をかけるのだから、
意欲がゼロなら結果もゼロである。
意欲には志も当てはまる。
心のあり方を考え、人生というものをさらに深く考えなければならないと、改めて教えていただいた。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
難しいお話であったが、自分の人生を生きるためのヒントを与えていただいた。
結果を得るための方程式
f=(a+b+c)x
結果=(お金+物+人間関係)×意欲
どんなに物質的に豊かでも、意欲が0では、結果も自ずと0になる。
意欲が大きければ大きいほど、それに伴って結果も大きなものになる。
つまり、何をするにも意欲があってこそ、ということだ。
また、大人として成熟していくにつれて、それまでの価値観が崩れ、
新たな価値観を再構築していくという話からは、
いわゆる型にはまった通りの価値観を持っている内は、受動的な生き方をしており、
価値観の変容が起きた後は、自分の人生を自分で取捨選択していくといった、
主体的な生き方になっていることに気づく。
価値観に支配されるか、自分で価値観を選択し、従わせるかで、生き方に大きな差が出るだろう。
私は後者の生き方をしていく。
From:和田将寛@東京校5期生ダッシュ生(神奈川出身・富士常葉大学1年)
-------------------------------------------------------------------
 ●「人生のあいまいさ- その向こうにあるもの」
●「人生のあいまいさ- その向こうにあるもの」自立する事により、
今まで庇護されて自分がなくなり、
新たな自分へと代わって行く。
新しい事、新しい自分に代わろうとする時、
必ず何らかの喪失があり、
喪失を恐れず行動して行く事で、
違った道が開けると、私は感じた。
常に勇気を持って果敢に行動して行きます。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
●『人生に意味を見いだす』
17年という短い歳月で命を絶った藤村操さんのお話が深く残りました。
藤村さんの自殺の原因は、人生に意味を見いだせなかった為だと言われています。
親の敷いたレールに乗っていれば良かった時期から、自分でレールを敷く時期への
移行が、藤村さんはうまくいきませんでした。
自分のレールに、生きる意味や大きな価値を付加する事が出来なかった…
藤村さんの生きた時代は、20世紀と21世紀をまたぐ時代でした。
21世紀は、自分の人生にどう意味を持たせるかを考えるようになった時代です。
藤村さんの事件は、近代的自殺のはじまりだと言われています。
自分がどこに向かって何をすべきかが明確にあれば人は生きられます。
ゴールが明確であればあるほど情熱的に生きられます。
藤村さんが抱えておられた悩み苦しみは、今の若者も抱えている悩みです。
試行錯誤しながら自分の役割・ゴールを探していく。
From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)
---------------------------------------------------
 ●『人生のあいまいさに向き合う』
●『人生のあいまいさに向き合う』人生のイニシエーション(=通過儀礼)という難しい内容だった。
藤村操という方の、生きる意味に悩み死を覚悟したら
気分がスッとしたいう辞世の句を教えて頂き、
私も親の経済的支援があった時の、
将来自分が何をしたいのか分からない時期を思い出した。
自分は何を目指して生きているのか、
将来何になりたいのかを思い悩む過程が
大人になるまでの段階ではある。
しかし社会に出ると、社会の中で自分を認めてくれる人が
出てくるので、その悩みは解消されていくものだと思う。
大人になる段階、今後の人生の中で
今自分の経験・知識だけで思い悩む事が
実は大した事ではないかもしれない。
人生のあいまいさに突き当たったときも、
プラスに変えてポジティブに生きて行こうと感じた。
From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)
---------------------------------------------------------------------------
平成25年(2013)【12月14日(土)】 歴史現地学/赤穂義士の足跡を辿る
2013/12/14
コメント (0)
 --------------------------------
--------------------------------●1日の流れ
7:30 本所松坂町公園(旧吉良邸)集合、朝礼
8:00 本所松坂町公園見学
8:10 赤穂義士の凱旋の道筋ツアースタート
8:30 赤穂義士、討ち入りの裏門到着
9:00 休息の地到着
10:00 松尾芭蕉の碑へ
11:00 築地到着…昼食(45分)
11:45 築地出発
12:30 勝海舟、西郷隆盛、江戸城無血開城締結の地へ
13:00 赤穂義士、切腹の地へ
14:00 泉岳寺到着、参拝
15:30 一度解散、西新宿教室へ
17:00 山近義幸理事長による「人間力道場」開始
・グループワーク「~の法則」
・五輪ピック発表
・テーマ:トークの法則
・質疑応答
20:00 終了、解散
--------------------------------
●歴史というもの
今日12月14日は、赤穂義士が討ち入りを果たした日。
吉良上野介の屋敷から泉岳寺に至るまでの、
赤穂義士の凱旋で歩いた道を実際に辿ってみた。
この日集合の朝7:30から、吉良邸には多くの人が集まっていたし、行く先々でも
ツアー団体の何組かに出くわした。
執着地点の泉岳寺では赤穂義士の祭りが行われ、溢れかえるほどの人たちが
義士の墓参りの列を作り、討ち入りがこれほどまで現代にも影響を及ぼすのかと驚いた。
吉良上野介が忠臣蔵舞台の敵役になった反面、実は吉良は優しい名君で、
キレた浅野内匠頭に非があったという説もある。
吉良邸跡にはそんな名君が祀られていた。
歴史は勝者を中心に語られ、彼らが正しかったと認識される。
吉田松陰先生も赤穂義士の影響を受けたという。
真実はわからないが、歴史というものの多面性を学んだ。
この日は義士の通った道を実際に歩くことで、
12月14日の早朝に起きた場面を
リアルに感じることができた。
●法則の復習
山近理事長の人間力道場に議事録係として参加させていただいた。
この日のテーマはトークの法則。
「~の法則」の話は以前の実践営業塾でも教わったが、
生かすと決めながらもそれを実践しきれていないということがわかった。
しかしふたたび聞くと、より記憶に残る。
今度こそ、一つでも多く身につける。
脱・砲丸投げの法則、できているだろうか…。
この日は野鴨の法則がとても印象に残った。
二回目で、前回と違う思いを持つことがあるようだ。
人間、厳しいことを忘れると何にもできなくなってしまう。
どんな環境になってもそのことを忘れないようにする。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●歩いて感じる
●歩いて感じる本日は赤穂浪士討ち入りの日。
義士たちが討ち入りの際に辿った道を 皆で歩くという、ベンチャー大學恒例のイベント。
私は本日で三度目の参加である。
今年は、昨年いけなかった義士たちのお墓参りも行うことが出来た。
ただ電車で泉岳寺へ行ってお墓参りするのではなく、
実際に義士たちが歩いた道を歩いてからお墓参りすることが
このイベントの醍醐味である。
実際に歩くことによって普段気付かないものに気付けたり、
義士たちがどういった想いで歩いていたかを感じることが出来る。
私が最も好きな立ち寄り箇所は、大石良雄外16人忠烈の跡。
この場所は仇討ち後、細川家にお預けとなった大石内蔵助ほか
16名の義士が切腹をした場所。
門には鍵がかかっており、中を覗くことしかできない(中には何もない)。
にも関わらず、昨年にも増して見学者がみられた。
これほどの年月が経ち、今もなお多くの人々の賞賛を呼んでいるのは
本当にすごいことである。
今年も歩けて本当によかった。
改めて、歴史を感じるということは、歴史を机上で学ぶよりも何倍もの価値が
あるということがわかった。
From:南出浩@東京校4期生・実行生(大阪府出身・桃山学院大学卒)
---------------------------------------------------
 ●『赤穂浪士討ち入りの日』
●『赤穂浪士討ち入りの日』道の途中には、看板が立てられており、赤穂浪士が体を休めた場所や、
休もうと思ったが断られた場所の詳細が記されていました。
赤穂浪士は討ち入り後、目立たないように、わざと遠回りをします。
歩行距離は10数キロにもなります。それを、47人もの人数での移動です。
大変な移動だと想像致しました。
From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)
---------------------------------------------------
平成25年(2013)【12月12日(木)】 人脈学/井上吏司先生(井上電気株式会社 取締役社長) ゲスト:伊谷江美子社長、横前淳子先生
2013/12/12
コメント (0)
 --------------------------------
--------------------------------●1日の流れ
9:00 朝礼、掃除
9:45 新聞アウトプット
10:30 株式会社クオレコーポレーション
伊谷江美子社長の講義(身だしなみ、第一印象についてのマナー)
12:00 質疑応答
12:15 昼休
13:15 横前淳子先生の講義(手帳学課題発表)
13:50 人脈学/井上電気株式会社
井上吏司社長の講義(上海研修アウトプット)
14:35掃除
15:00終礼、解散
--------------------------------
●伊谷江美子社長の講義
講義を受けて一番思った事は、
自分の話は思った以上に伝わってはおらず
相手の話を100%理解するのは難しいという事です。
相手に伝えているではなく、伝わる話し方が、
まるで出来ていない事に、改めて気付きました。
●手の位置、目線、あごの位置
計算に入れ、相手に聞きやすいスピードとトーンで話す。
これらの事を適切に行なえるように、
動画等で確認しながら、
今まで以上にスピーチの訓練をし、
相手に伝える話し方を身につけます。
●笑顔
マナーとして相手に不快なイメージを与えない為に
必要な物は、笑顔だと教わった。
特に、自分は表情が乏しいとよく言われているので、
先生の笑顔は好感と安心をあたえると聴き
もっと、自然な表情を作る練習を
しなければ、と感じた。
常ににこやかな表情をすることは、
他者との円滑なコミュニケーションを
行なう上で、必ず役に立つとも感じる。
自分の表情が周りに与える影響を考えて、
行動、発言をするようにして行きます。
●人脈学/井上吏司社長
上海研修のアウトプットをさせて頂いたが、
今日1日の講義を受けて、
井上社長のお話を少しお聞きし
人脈学の本質を垣間見たような気がしました。
まずは、手紙やお礼メール等でつながりを作り、
中が深まってきたら、
その人を別の場所に連れて行き、人に紹介する。
他人の夢や目標を応援し、
その事をまず支援する。
自分は経営者になるという夢に向かって進んでいるが、
その夢の為に、井上社長はいろんな人を紹介してくださる。
今は、恩を受けるばかりだが、
いずれ返して行きたいと思っています。
この誰かの為に何かをし、
相手を喜ばせるこの事の積み重ねが、
人脈を作る事なのだと感じました。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●スキルアップ、リーダーへ
●スキルアップ、リーダーへ井上社長の紹介で来てくださった伊谷社長は、
ご自身の人生の経験からスキルアップのための実践的なことまで、
濃密な講義をしてくださった。
海外生活での経験、英国人のボーイフレンドに会うために
キャビンアテンダントになったこと、
まだ女性が社会で活躍することが難しいときに経営者になって、
志のために社会の新しい領域を開拓してきたこと。
それらの経験があってこその実践論なのだろう。
鳥の眼・魚の眼・虫の眼という見方を身につけること、
あごの角度によって相手に与える印象がまるで違うこと、
多くの人の前では視点をジグザグに動かすと良いということ、
重要な言葉の前や後に「間」をおくということ、など。
この日新しく身についたことや、今までの講師の方のお話との組み合わせで
深まった知識もあり、充実した学びの時間となった。
ベンチャー大學のプレゼンの場などを活かし、一つでも多く実際の場で使えるようにする。
スキルの上でもリーダーになるためにというお話があったが、
途中で教えていただいたリーダー論が特に印象に残った。
「リーダーが時代に乗れなくなったとき、組織は衰退する」という。
織田信長、徳川家など、様々な歴史上のリーダーの研究から出た結論ののようだ。
ベンチャー大學の中條学長のお言葉も教えてくださった。
「会社の器は、決して個人の器より大きくならない」
●人脈学とは
この日は横前淳子先生も、井上社長との繋がりで来てくださった。
先生の手帳術を説明してくださり、ライフリング作成への期待が大きくなった。
長野から来てくださって、本当に有難い。
井上社長には上海研修の最終日に工場見学をさせていただき、
今まで食べたことがない豪華な中華料理までご馳走になった。
今回、講義の場で少しでもお礼ができたら嬉しいと思ったが、ご多忙の中
わざわざ足を運んでいただいて、感謝・繋がりの人脈学を教えていただいて
またまた感謝の念に絶えない。
今元さんもおっしゃっていたが、アナログでの感謝、お礼に尽きるのだろう。
私はまだまだ感謝力が足りないと思う。
お礼も充分に実践できていないことがある。
お礼ハガキ、メールから忘れずに送り、力を身につけて、ご縁や人脈を広げる。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●『話の聴き方』
●『話の聴き方』伊谷江美子先生のお話を伺いました。
「話の聴き方」についてお話を伺ったのですが、普段出来てないことが
たくさん見つかり勉強になりました。
基本的なところでは、腕組みをして聴かない・手を後ろに組まずに前に組むなどです。
これを守るだけで、相手が受ける印象が変わります。
また、話を聴く時の気持ちに関しては、先入観を持たずに「心を0にして聴く」。
特にクレームの時などはその状態で聴かないと、ついつい反論してしまう事になります。
意識しないと出来ないことばかりなので、日々トレーニングして聴く技術を身につけます。
●『手帳学』
横前淳子先生は、手帳を使って夢を叶えてこられました。
先生の手帳には、理想のプライベートや欲しいものなどの写真が貼ってあります。
写真にすることで強いイメージとなり、望むものが手に入りやすくなります。
頭の中で強いイメージをすると、シンロニシティという作用が起こり、
イメージしたものが、なぜか突然目の前に現れたりするそうです
(例えば、話したいなと思っていた相手から電話が突然かかってくるなど)!
卑屈になったり腐ったりせず、素直に夢を描いていく事が、
夢を叶える秘訣だなと感じさせて頂きました。
From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)
---------------------------------------------------
平成25年(2013)【12月10日(火)】 上海研修 最終日
2013/12/10
コメント (0)
 ●12月10日
●12月10日・帰国
名残惜しかった。
上海という場所に魅力を感じたし、海外に出ることの中毒性を思い出した研修になった。
海外の現場で学べた経験は数知れない。
思えば、ベンチャー大學の研修という機会だからこそ味わうことができたことばかりだった。
支えてくださった事務局の方々、大阪校の皆様、大西社長をはじめとした
リビアスの皆様、井上電気の斎藤さん、日興の皆様、上海講義をしてくださった木村先生…。
こうして考えてみると、信じられないほどの多くの方の支えで勉強できていることに驚く。
心より感謝致します。
上海での経験も活かし、今後のベンチャー大學での学び、自分の人生をさらに充実したものにしていく。
From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)
---------------------------------------------------------
●まとめ
上海に行って見て、一番感じたことは、
ニュースで見ることだけではダメだということです。
反日やスト活動が盛んだとニュースでは言っていたが、
個人と国家間では違うらしく、
反日的な対応は特にされなかった。
また、ストも中国全体ではあるが、
そこまで多くはないとも教えていただいた。
得た知識で、仮定し検証する事で
さらに進んだ仮定を出す事が出来るようになる。
こうした事の繰り返しが、
自身の成長を促すと感じた。
もっと大胆な行動、体験をして、
人間力を高めて、日本を支える
立派な経営者になります。
From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●全体を通して
●全体を通して大西社長がお話の中で、日本が成熟した大人で、中国は勢いがあって青年のようだと
言われていたが、その通りだなと感じた。
道路の上に野菜を広げて売っていたり、日本の銀座のような綺麗で栄えている
通りから一歩入ると、まるでスラム街のようになっていたりなど
見方によってはめちゃくちゃに思えるかもしれないが、それだけ成長の余地を残しているともいえる。
現状でも日本のGDPを超えた中国だが、人口の多さと勢い、成長の余地を考えた時、
これからも伸びていくだろうなと感じた。
グローバル化していく今からの時代、中国は経済的に大きな地位を得るだろう。
そんな中国に私たちがこれから社会へでて戦っていかなければならない。
その危機感を抱けた点でも今回実際に上海へいって良かったと感じた。
From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)
---------------------------------------------------------
●5日目
・日本に向けて
最終日、ついに上海とお別れになるのだが
来た時に感じた上海の臭いなどが
全く気にならなくなっていることに気づく。
初日は少し気分が悪くなったのに
こんなに早く慣れていることに驚いた。
帰りの電車においても
来た時に乗った時のようにそわそわせず
落ち着いて載ることができたが、
それもこの研修において
現地の人に道を案内してもらったり
値引き交渉を行ったりして
観光では味わうことのできなかった経験をできたからだと感じる。
帰りの浦東空港でも、日本に到着してからの成田でも
手続きで焦ることもなく行動できたのも
最初に比べれば大きな成長である。
今まで海外を経験がなかった人だからこそ
成長も大きかった今回の上海研修なのではないかと感じた。
今回の経験で広がった視野は今後のベン大での生活や
社会人になってから活きると感じた。
From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)
----------------------------------------------------
●全体の感想
飛行機で3,4時間であり、その気になれば日帰りで行くことも可能な距離であるにも
関わらず、スケールの大きさが明らかに異なっていた。
ビルの大きさ、道路の広さ、空気、発展度合いも全く違う。
日本が成熟しきっていること、中国がまだまだ発展していく可能性があることを
肌で感じることができた。特に異なるのは人が持っているエネルギーだ。
露天商など商売人のとにかく売ろうとする姿勢は日本では見られない。
シンガポールにチャイナタウンができていること、アフリカ大陸にも
チャイニーズレストランがあることも納得できる。中国のビジネスマンも
この姿勢を持っていると考えると非常に危機感を覚える。
今はまだ中国メーカーは技術力が高くないため、安い商品をたくさん売る手法を
とっているが、技術力が高まれば日系企業は多くのお客様を失うだろう。
格差を通して日本が改めて恵まれていることが分かった。しかし、
恵まれていることに少々慣れてしまったのが今の日本の現代人だと思う。
理屈で思ってもなかなか実感として得られない。今回の上海研修で
実感として感じることができた。本当に貴重な経験をさせていただいた。
こういった経験をさせていただけたのもベンチャー大學の支援企業さまのおかげである。
改めて感謝申し上げます。
From: 春山恭平@東京校5期生ダッシュ生(東京都出身・杏林大学4年)
------------------------------------------------------------------




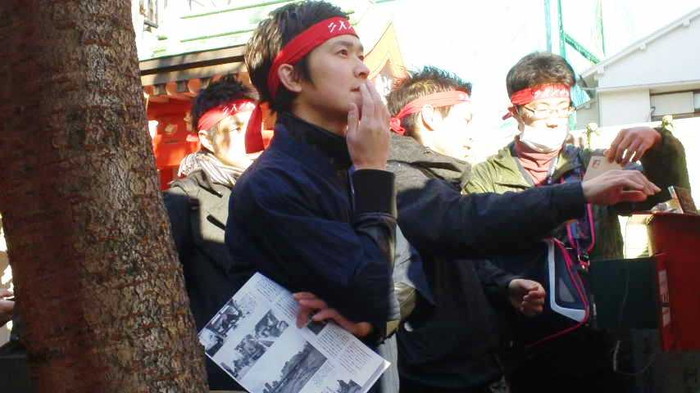




 RSS 2.0
RSS 2.0












