東京校の講義レポート
平成27年(2015)【2月13日(金)】 DJ学/横前忠幸先生(株式会社いと忠 代表取締役)&手帳術/横前淳子先生(ラジオパーソナリティ)
2015/02/13
コメント (0)
 -------------------------------------------------
-------------------------------------------------●1日の流れ
9:00 DJ学『こだわりミュージック』講義(第2回)
/横前忠幸先生(株式会社いと忠 代表取締役)
「AKBのしくみ」
「AKB48のブームはいつ終わるのか?」
9:50 体験DJ① 須藤雄介「北欧より愛をこめて」
10:15 体験DJ② 鈴木駿介「冬と夏のコントラスト」
10:40 体験DJ③ 嘉形俊輔「精神安定剤」
11:05 体験DJ④ 柳沢一磨 「YANAGI'sアニソン祭り」
11:30 「牧村隆輝のイナセなこだわりミュージック」
・『君が代』トリビア
11:50 講義終了・感想文記入
12:00 昼食
13:00 手帳術/横前淳子先生(ラジオパーソナリティ)
エクセレンスマップ作り
14:30 各自のエクセレンスマップの発表
15:00 講義終了・記念撮影
-------------------------------------------------
●DJ学「こだわりミュージック」講義(第2回)
・ブームとジャンル
はじめの横前社長の質問の中で「AKB48のブームはいつ終わるのか?」
という質問があった。
しかし、すでに「AKB48」は最早一過性の流れである「ブーム」ではなく、
すでにそこにあることが当たり前の「ジャンル」へと変化している。
「ジャンル」とは例えば芸能面なら宝塚やジャニーズ、一般的に言えば
野球やサッカーなどがそれに当てはまる。
要するに「ジャンル」とは表に出てようが出ていまいが気にしない存在。
あることが当たり前ものを指すのである。そんな「ジャンル」に
「AKB48」を変えた仕組みを作ったのが秋元康さんである。
秋元康さんはブームをブームとして終わらせないために「会いに行けるアイドル」
というコンセプトの元、「AKB48」を本家として、全国各地に様々なグループを作り、
そして、その中で競わせることでレベルの向上に努めたのである。
その一環として選抜総選挙やドラフト制、研究生の制度がある。
こうした仕組みが整っていたから「AKB48」は「ブーム」から「ジャンル」と
変化することが出来たのである。
・人に自分の好きな音楽の良さ伝えるには
今回はそれぞれが持ち時間15分でDJを体験させて頂いた。
当初、DJというのはただ自分が好きな音楽を
ただ流しているだけでいいのかと勘違いしていたが、実はそうではない。
他の人に自分の曲に好印象を持ってもらうためにはいくつか
ポイントがある。1つ目がテーマを絞ることである。
テーマにあってない曲をかけたりすると人は退屈に感じてしまう。
そのために曲のジャンルや作曲者を絞ったりすると良い。
2つ目が狭い意味で関連性を持たせ、最後に自分の一押しの曲をかけたりする
ことで聞いている人に更に好印象を与える。
このようなことがしっかりと出来ていれば魅力的なDJをすることが
出来るのである。
●手帳術「エクセレンスマップ作り」
・夢や目標を実現するために
今回、エクセレンスマップという夢実現のために6つの項目を基に
夢実現のための自分のマップ作りをした。最初は半信半疑で作業をしていたが
不思議と作業していく内に、楽しみながらマップ作りそのものを
楽しんでいたことに驚いた。私のエクセレンスマップは多くの写真や
イラストを活用して作ったため、自分の性格がよく表現されていて、
より具体的で分かりやすいマップを作ることが出来た。
また、不思議と段々作っていく内に自分の夢や目標が達成出来るという
自信がつく効果がこのエクセレンスマップにはあると感じた。
今後、このエクセレンスマップを周りの人達にも紹介していきたい。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
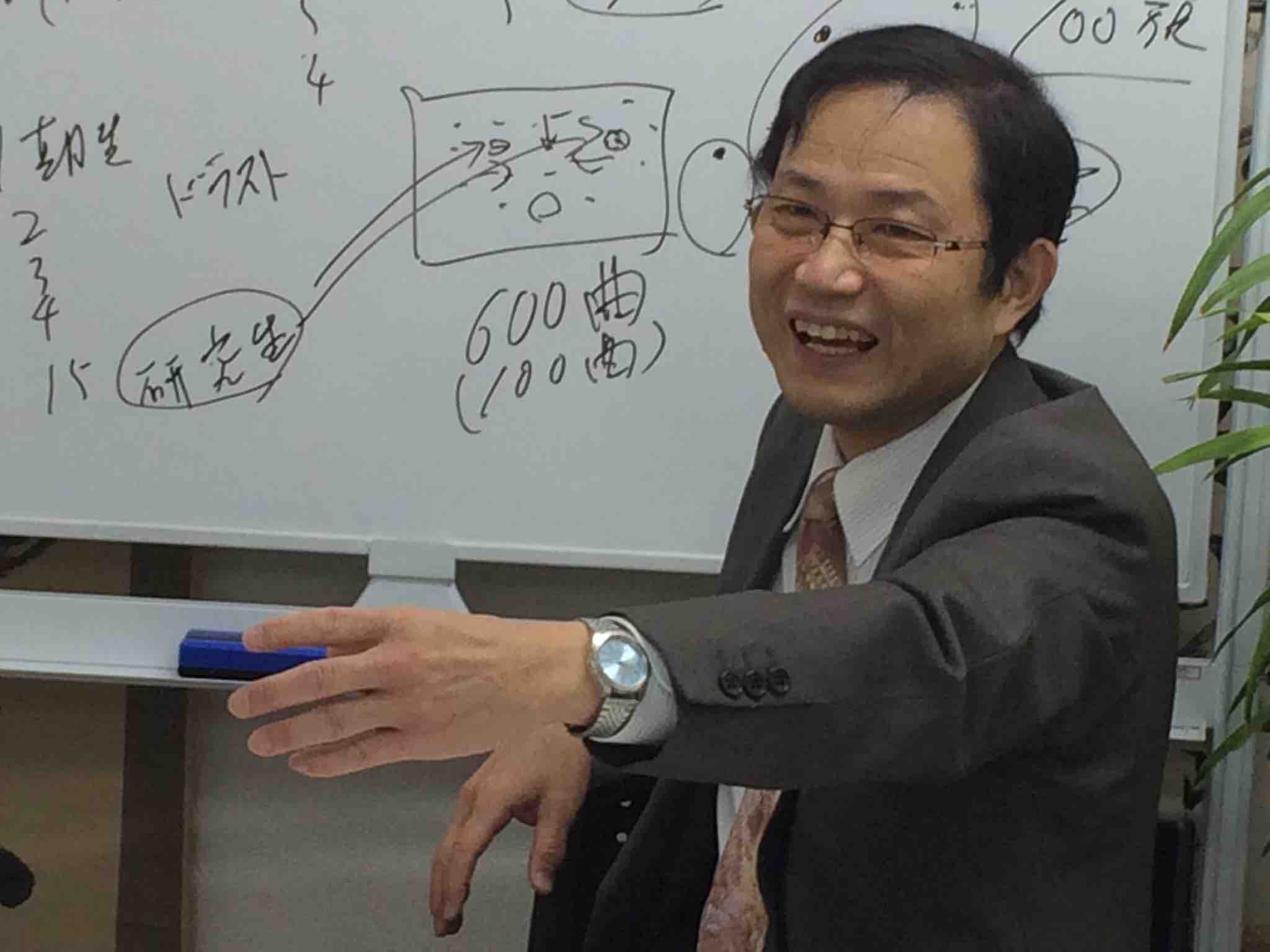 ●セオリー重視
●セオリー重視それは、横前社長流の4つのポイントにするとまとまる、というものである。
1、つかみ(安心または驚き)
2、基本
3、バリエーション
4、〆 である。
これら4つを意識すると聴いている側は、一つの番組を聴いて
“分かったような感覚"になるであるや"勉強になる"といった印象を
抱きやすいことを学ばせていただいた。
しかし、今回の結果は私にとって不甲斐ないものであった。
私は「精神安定剤」というテーマで安易に自分の好きな曲を
皆さんにも伝えたいのみでしかなかった。もっと、客観的視点が必要であったと感じた。
そして、今回の「DJ学」を通して改めて音楽の素晴らしさと6期生の好きな曲が
わかって少し以前より仲良くできたと私は思った。
また、もっと"為になる"音楽の知識を身につけていきます。
●手帳術
・整理整頓
今回はエクセレントマップを作製するものであった。
実際に、「精神・心」「健康」「仕事・人間関係」「知識・教養」
「家庭・プライベート」、「お金・もの」の6種類をそれぞれ自分なりに
写真やイラストで穴埋めを行った。
自分の理想が「こんなものであったらな」と考えながらの作業が
私にとって楽しかったのである。
そして、このエクセレントマップの特徴は、自身がわくわくするような
夢満載の手帳を常に持ち歩くこととなる。そのため、手帳を開くたびに
自分の理想のイメージを1年間持ち続けることができる。
こうした意味でも、このエクセレントマップを完成させたのは本当に良い
機会であると感じた。また、他の6期生の夢満載のものをみるとこれも
またちょっと深い部分が知れたという優越感のような感覚に覚えて楽しかった。
この1年間は「24時間手帳」とともに人生を歩んで目標に一歩でも近づく努力を
して参ります。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
---------------------------------------------------------
 ●横前忠幸社長のDJ学・第2回
●横前忠幸社長のDJ学・第2回今回は、最初にAKB48の仕組みについて詳しく教えて頂いた。
「AKBブームはいつ終わるか?」
しかし、この質問には根本的な間違いがある。それは、AKBはすでにブームではなく、
ジャンルと化しているという点だ。
ブームとは一過性の波にすぎないとすれば、AKBはそうではなく、
ファンの定着とメンバーの育成について高度なシステムを構築している。
チームを分けて競争させること(入れ替えも)、研修生という二軍制度などは
野球やサッカーに類似している。
なにより、野球やサッカーというものが当たり前の存在となっていて、
ブームとはなりえないのと、AKBは同じである。
AKBはほかにも、下積みが仕組化されアイドルの分厚い層が存在すること、
「推しメン」の仕組みによってファンが熱心になることなど
秋元康氏の仕掛けた戦略には目を見張るものがある。
そして、今回の横前社長のレクチャーによって、AKBのトップアイドルたちが必死に這い上がり、
競争を勝ち抜いてきたつわものたちであるということを理解した。
これは今までの先入観を覆される、非常に意義のあるお話を聞くことが出来た。
そして、今回は私たちがDJとなって曲の紹介を体験した。
ヘヴィメタルを皆に聴いて頂くとても貴重な機会となった。
ただ、テーマ設定を「北欧メタル」としたが、思った以上にフィンランドに
偏ってしまい、テーマに一貫性がなかった。
聴いている人が納得できるようなテーマ設定が出来ると、より興味を持って
聴いてもらうことが出来る。
反対に、個人的な趣味だけで選んでしまうと、疑問符ばかりが浮かんで
聴くことに集中できないのだ。
横前社長のおっしゃったとおり、時には自分の好みでない曲でも意義を考えて
入れる必要がある。
最後に「君が代特集」をお手本として聴かせて頂いたが、やはり「聴かせる展開」を
作っていらっしゃった。
掴みから定番、バリエーションを入れて最後に締める、という大きな流れは、
音楽に限らずスピーチなどでも使える。
自分の好きなもの、大切なものを人に紹介する技術を、これからもっと磨いていきたい。
●横前淳子先生の手帳学・第3回
今回は、エクセレンスマップという、1年後の自分を思い描いたシートを作成した。
色々な画像を張り付けながら、6つの分野についてそれぞれこうなりたいという
イメージを具体化した。
やってみて分かるのは、自分の関心の度合いによって分野ごとに充実さが違うと
いうことだ。
例えば、健康に関する分野ではあまり自分がどうなりたいのかわかっていないことに
気付いた。
淳子先生によれば、偏りなく全体をバランスよくステップアップさせていくことが、
幸せになるために必要である。
自分の頭の中身と行動にバランスがとれているか、確認するためにもとても有用な
マップ作りをすることが出来た。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
平成27年(2015)【2月4日(水)】 経営問題を考える/高瀬拓士先生(日本コンピュータ開発 最高顧問)
2015/02/04
コメント (0)
 ●イスラム国と人質殺害
●イスラム国と人質殺害シリアで日本人がイスラム国に捕まって、とてつもなく大きな問題を、日本政府だけでなく関係各国にももたらした。色々な角度から、深く考えさせられました。
●企業は何のためにあるのか?
人が生きて行く中で、企業の中で過ごす時間が占める割合はとても大きい。
だから企業は、社会人教育機関としての役割も持っている。
企業がどう考え、どのように仕事をするかによって、そこで働く人々にも
大きな影響を与えるからだ。
一方で、これからの中小企業は、特に大企業にぶら下がっている中小企業は、
企業規模が小さいにもかかわらず、大企業同様に世界経済、日本経済に振り
回される、
中小企業も研究開発部門を持ち、大企業の下請け的ではない、独自の存在
意義を持った、地元、地域に根差した中小企業として、独立してやっていく道が
ある。
研究開発部門を持つお金・人財がないなら、地域の学校、大学や高専、専門
学校に協力してもらえばいい。
ITを活かして、地域の社会・経済にも貢献しつつ、グローバル市場を見据えて
活動することが中小にはできるのである。
就職では、どんな企業を選んで入るのか、基準を持っていることが重要だ。
就職は、受験料、払込金まで納入し、入学したら授業料まで払う大学とは違う。
自分の好きなことをさせてくれるなどということはない。
結婚と一緒と思えばいい。相手が自分を幸せにしてくれるなどと期待すべきで
はない。相手も企業も、自分のために生まれ育っているわけではない。
「あの人(企業)を幸せにするためなら、どんなことでもする」と思える相手を
見つけ、選ぶべきだ。
つまり結婚相手、就職先を選ぶときには、その人の人柄や「企業柄」こそが
大事だ。
●子どもたちに歴史を伝える
高瀬先生は、小さい頃からキュリー夫人伝や「レ・ミゼラブル」のような伝記もの、
古典ものの名作などを読むことによって、自然に社会や人生を学んできた。
子どもたちに講義をして、松陰先生のことを伝える際にも、その価値を決めつけ
て、一方的に教え込むというより、「どんな人がいたか」「どんな社会だったか」と
いうことを、物語のように伝え、判断は任せるのが良い。
それを受けて、子どもたちが自分は何を勉強したいと思うか、自分で考える課題
を見つける材料になる。
押しつけではない、子どもたちの本当の学びを助けることが出来ると分かって、
とてもやる気がわいてきた。
・久住高原開墾、ワイナリー計画
最近始まったばかりのプロジェクトについても、教えて下さった。
「大分の久住高原で、荒れ地を開墾して農地にし、ブドウ畑を育て、ワイナリーも起こし、
若者たちには農業体験をしてもらうばを作る」という内容である。地元の市長の協力も
取り付け、県知事立会いの下で調印式を終えたところだという。
会長に就任したのは群馬県出身の人で、群馬でやっていた事業をそのまま九州でも
始めることになったが、その社長に抜擢された、知人である熊本の人の要請で高瀬先
生も顧問としてかかわることになっているという。
群馬出身者の私としては俄然興味をそそられた。
この事業からも、高瀬先生が日本の若者、農業、地域社会といったことについて
強い関心を持たれていることがよく分かった。
大分は遠い土地であるが、交通費を用意出来たらすぐにでも見学させて頂きたいと感じた。
●高瀬先生の講義は4回目にして最終回。
「自分の頭で考える」ことの大切さを何度も教わった。
答えは誰かに与えてもらうものではなくて、自分で困難に直面しながら探し求めなければならない。
人生や社会に関心を持ち、色々な経験から知っていくことで、自分のやりたいことを決めることが
出来るのである。
高瀬先生のように、世界を見渡して視野を広げることも、自らの足元を見るために重要である。
自分の頭で考えることを、高瀬先生の講義を思い出して、忘れることが無いように努めよう。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●2つの事件の共通点と日本の経営問題
高瀬先生が最初に私達に対して「イスラム国日本人拘束事件」について
それぞれどう思っているか?について問われた。
この事件に対しての意見は人それぞれだが、1つ言えることは
事件のメディアの報道の仕方が極端であるということを
高瀬先生はご指摘された。
また、この事件と「秋葉原無差別殺傷事件」は関係ないように見えて
実は共通点が2つある。
1つ目が社会に対する不満と2つ目が他人に迷惑をかけているということである。そして、これが日本の経営問題とどう関わっていくかと言えば「こういった根源の問題に対して、どういう風に行動するか?」という点においてはどちらも同じことがあると言える。
●企業のあるべき姿と就職するということ
企業は最高最強の社会人教育機関である。だから国民の民度にも影響を与えている。
企業が人々の日常生活に与える影響は大きい。
今の大学ではただ知識ばかりを学んでいて、自分の意見を持つことも、自分の頭で考えることもせず、社会や人生にも興味を持たず、社会に出ても学士らしい役には立たない。
そんな学生が社会に出ても耐えられず、会社を早期退職することになるのは当然である。
企業側としては、そのような学生たちを、一日も早く利益を稼いでくれる企業戦士に改造するため社内教育を行っている。
これから就職する学生は、まずは自分の中でしっかりと自分の就職観、企業を選ぶ基準を持つこと。そして、就職は結婚と同じであり、相手(会社側)に幸せを求めるのではなく、
自分が相手(会社側)を幸せにしたいと思う意識を持つことが重要である。
要するに相手の外見ではなく、人柄(会社柄)で選ぶことである。
高瀬先生が仰った『当社の常識は世の中(一般企業)の非常識』というような、信念を持った
企業に私も就職したい。
●自分が今できること
最後に高瀬先生からどんな質問でもお答え下さるということで私は「モチベーションが下がった時にどうしていますか?」という質問をさせて頂いた。
その質問に対する高瀬先生の回答は「自分が今出来るベストを尽くせ!」
「今何をするかに全力を出せ!」というお言葉を頂きました。
とにかくないものねだりではなく、今有るものを活かして、やるべき時に、やるべきことを、 精一杯やること。そして周りの人と比べず、今自分がやるべきことに集中することが自分のモチベーションを上げることに繋がるのである。
今回で高瀬先生の講義は最後だったが、これまでの講義で自分の意見を持つことの大切さと、物事をいろんな角度から見ることの重要性を学ばせて頂いた。
そして、高瀬先生も仰っていたように、これからの日本は私達若者が作っていくのである。
その自覚を持ちつつ、これからの自分の人生に今回学ばせて頂いたことを活かしていきたい。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
高瀬先生が最初に私達に対して「イスラム国日本人拘束事件」について
それぞれどう思っているか?について問われた。
この事件に対しての意見は人それぞれだが、1つ言えることは
事件のメディアの報道の仕方が極端であるということを
高瀬先生はご指摘された。
また、この事件と「秋葉原無差別殺傷事件」は関係ないように見えて
実は共通点が2つある。
1つ目が社会に対する不満と2つ目が他人に迷惑をかけているということである。そして、これが日本の経営問題とどう関わっていくかと言えば「こういった根源の問題に対して、どういう風に行動するか?」という点においてはどちらも同じことがあると言える。
●企業のあるべき姿と就職するということ
企業は最高最強の社会人教育機関である。だから国民の民度にも影響を与えている。
企業が人々の日常生活に与える影響は大きい。
今の大学ではただ知識ばかりを学んでいて、自分の意見を持つことも、自分の頭で考えることもせず、社会や人生にも興味を持たず、社会に出ても学士らしい役には立たない。
そんな学生が社会に出ても耐えられず、会社を早期退職することになるのは当然である。
企業側としては、そのような学生たちを、一日も早く利益を稼いでくれる企業戦士に改造するため社内教育を行っている。
これから就職する学生は、まずは自分の中でしっかりと自分の就職観、企業を選ぶ基準を持つこと。そして、就職は結婚と同じであり、相手(会社側)に幸せを求めるのではなく、
自分が相手(会社側)を幸せにしたいと思う意識を持つことが重要である。
要するに相手の外見ではなく、人柄(会社柄)で選ぶことである。
高瀬先生が仰った『当社の常識は世の中(一般企業)の非常識』というような、信念を持った
企業に私も就職したい。
●自分が今できること
最後に高瀬先生からどんな質問でもお答え下さるということで私は「モチベーションが下がった時にどうしていますか?」という質問をさせて頂いた。
その質問に対する高瀬先生の回答は「自分が今出来るベストを尽くせ!」
「今何をするかに全力を出せ!」というお言葉を頂きました。
とにかくないものねだりではなく、今有るものを活かして、やるべき時に、やるべきことを、 精一杯やること。そして周りの人と比べず、今自分がやるべきことに集中することが自分のモチベーションを上げることに繋がるのである。
今回で高瀬先生の講義は最後だったが、これまでの講義で自分の意見を持つことの大切さと、物事をいろんな角度から見ることの重要性を学ばせて頂いた。
そして、高瀬先生も仰っていたように、これからの日本は私達若者が作っていくのである。
その自覚を持ちつつ、これからの自分の人生に今回学ばせて頂いたことを活かしていきたい。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-------------------------------------------------------
 ●企業のあるべき姿
●企業のあるべき姿高瀬先生は、自分が就職した企業で仕事をしている内に、知らず知らずの内に多くの教育を受けた。
その経験から、企業は最高、最強の社会人教育機関だと思っている。
しかし、現代の多くの企業は社内教育を通じて、自社の利益の為の企業戦士として育てていると言える。
それではいけないと高瀬先生は仰る。本来、企業として大切なことは、社員を人間的に成長させるような教育を施すことにある。それは社員が自分の人生、自分おすむ社会に関心を持ち、どのよう
にするのかを考えさせることにつながるからだ。
そうして、今自分に何が足りないのか、どうしたらもっと成長ができるのだろうかが自ずとわかってくる。
日本人は、そのような国民になって欲しいと思っている。まさに、高瀬先生は日本国について考えてい
る、数少ない日本人であると思った。
また、こんなことも仰られていた。企業を選ぶうえで大切なことは、己の幸せを追求するのではなく、
相手を幸せにしたいな思える企業に就職すると良いとアドバイスを頂いた。
私は、このアドバイスを元にこれから就職活動をしてゆきます。
●全力とは
その時間にやるべきことに、一生懸命に取り組むことである。例えば、講義を受けている間は、その講師の話であったり、その講師についてだけを一心不乱に考えることであると高瀬先生は仰っていた。
それを聴いて私はハッと気が付いた。今まで全力を出しきったと思いこんでいたのだということに…。
そう思うと、もっともっと全力を出し切らないといけないと学ばせて頂いた。
これからの生活から全力疾走で突き進んでいく。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
---------------------------------------------------------
●気付き
まず議題として上がったのが、邦人がイスラム人に人質として捕らわれ殺害された事件についてだった。
「イスラム国」に参加しようという日本人がいたが、高瀬先生は、「人間はもともと不満を探す生き物」だと
仰っていた。最近判決が出た秋葉原事件についても、この豊かな国に住んでいながら社会に不満を持ち、
他人を犠牲にしてその鬱憤を晴らした結果だとも仰っていた。
私も他人の優れた点を羨む傾向があり、なぜあの人にできて私には出来ないのかと常々思ってしまう。
私も日々不満は溜めず、感情はうまくコントロールする事が大事だと感じた。
そして次に就職について。
就職というのは先生曰く、結婚と同じであると話されていた。
また先生は就活する上で、自分は何がしたいのか常に軸を持っておくべきだとも仰られていた。
今の一般的な大学生は、将来が保証されているという理由から大企業を志望することが多い傾向にある。
しかし大企業は成果主義であるため、リストラも多いという話だ。
そして、大企業に何のために就職するのかということも語られていた。
確かに私も就活していた時、名の知れた企業は安心しているからという理由で志願していた。
しかしだからといって、その企業に入って何がしたいのかということは何も考えていなかった。
私は就職してから、ただ自分の利益だけを決して求めたくない。
人々一人一人が喜ぶような仕事ぶりをする。
そしてその組織に属して自分がやりたいことを喜んでやりたい。
From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)
----------------------------------------------------------
まず議題として上がったのが、邦人がイスラム人に人質として捕らわれ殺害された事件についてだった。
「イスラム国」に参加しようという日本人がいたが、高瀬先生は、「人間はもともと不満を探す生き物」だと
仰っていた。最近判決が出た秋葉原事件についても、この豊かな国に住んでいながら社会に不満を持ち、
他人を犠牲にしてその鬱憤を晴らした結果だとも仰っていた。
私も他人の優れた点を羨む傾向があり、なぜあの人にできて私には出来ないのかと常々思ってしまう。
私も日々不満は溜めず、感情はうまくコントロールする事が大事だと感じた。
そして次に就職について。
就職というのは先生曰く、結婚と同じであると話されていた。
また先生は就活する上で、自分は何がしたいのか常に軸を持っておくべきだとも仰られていた。
今の一般的な大学生は、将来が保証されているという理由から大企業を志望することが多い傾向にある。
しかし大企業は成果主義であるため、リストラも多いという話だ。
そして、大企業に何のために就職するのかということも語られていた。
確かに私も就活していた時、名の知れた企業は安心しているからという理由で志願していた。
しかしだからといって、その企業に入って何がしたいのかということは何も考えていなかった。
私は就職してから、ただ自分の利益だけを決して求めたくない。
人々一人一人が喜ぶような仕事ぶりをする。
そしてその組織に属して自分がやりたいことを喜んでやりたい。
From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)
----------------------------------------------------------
平成27年(2015)【1月27日(火)】 リアル経営学(農業編)/中野芳男先生(ロハス農園 代表)
2015/01/27
コメント (0)
平成27年(2015)【1月24日(土)】 第4回 クラウドファンディング発表会
2015/01/24
コメント (0)
平成27年(2015)【1月17日(土)】 1部:中條高徳学長 DVD特別講義 2部:人間力道場 第9回/山近義幸理事長代行(ザメディアジョングループ代表)
2015/01/17
コメント (0)
-------------------------------------------------
●1日の流れ
10:45 新聞アウトプット
3面「スイス 安全通貨の乱」
11:15 TODOリスト作成
12:00 休憩
12:30 CF発表会の練習
15:00 中條学長DVD特別講義
・吉田松陰先生について
・日本人として
18:00 山近社長の人間力道場
・後輩を育てる
--------------------------------------------------------------
●日本人の誇り/中條学長のDVD特別講義
昨年末にお亡くなりになられ、
中條学長による特別講義を受けることが出来る機会は、失われてしまった。
これまでにわずか3度しか、直接お会いできることはなかったが、
その一つ一つが、かけがえのないものとして記憶されている。
今回は過去に収録された中條学長の講義を、DVDで受講できることになった。
中條学長のお話を聞いて、先生がかねがね、日本の若者が日本を
愛することが出来なくなってしまった、ということを嘆いていらっしゃったのを思い出した。
何よりも、私たち若者にもっと自分の生まれ育った国のことを知り、愛するように
なってほしい、という想いが強かったのだと思う。
だからこそ、体調を悪くされ、外出が難しくなってきてからも、
日本ベンチャー大學のために動いて下さったのだ。
「歴史を学びなさい」と繰り返し言われたのは、私たちが日本人として
誇りを持って生きるために必要不可欠だからである。
もう一つ、入学式の時に中條学長から、「君は人生の回り道をしたけれども、
良い選択だったね。私も回り道をしたのだよ」という言葉を掛けて頂いたのを覚えている。
先生もまた、陸軍士官学校の学生であったその時に終戦を迎え、人生の目的を
見失いながら、その後旧制高校へと進学、数年遅れの学業を修めていかれた。
この日本ベンチャー大學で1年間学んでいくことが、必ず意味のあるものになると
中條学長が保証して下さったのである。
中條学長が私たちに教え、また期待して下さったものの大きさは、これからも忘れてはならない。
●山近社長の人間力道場・第9回
今回のテーマは、後輩を育てるということである。
後輩を育てることは、後輩にどんな姿を見せるか、どうやってコミュニケーションを
とるか、ということと密接にかかわる。
成功体験よりも失敗体験を多く話すこと。そのためには、まずたくさんの失敗を
重ねていることが必要だ。
20代はもっとも失敗しやすいが、反対に失敗しても痛手の少ない年代と言える。
また、質問力はここでも生きてくる。自分から喋っても自慢話になりやすい。
それよりも、「何か壁に当たっていないか?」と問いかけるほうが、
こちらの言葉が相手の心に響く。
講義を受けて感じたのは、もっとも重要なのは日々の積み重ねである、ということだ。
質問力も、失敗経験の豊富さも、毎日意識して質問し、失敗するようにしないと、
惰性では身につかないものである。
山近社長の日々の活動を思い返すと、大量の質問を繰り返している。
また、人生においては想像もつかないような失敗を(得意分野という飲みの席でも)
繰り返してきたという。
今の山近社長の地位はそうやって築き上げられたのだ、ということがこれで分かる。
それをこうして直接伝えて頂けたからには、私も質問と失敗の積み重ねを意識して取り組んでいく。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●1日の流れ
10:45 新聞アウトプット
3面「スイス 安全通貨の乱」
11:15 TODOリスト作成
12:00 休憩
12:30 CF発表会の練習
15:00 中條学長DVD特別講義
・吉田松陰先生について
・日本人として
18:00 山近社長の人間力道場
・後輩を育てる
--------------------------------------------------------------
●日本人の誇り/中條学長のDVD特別講義
昨年末にお亡くなりになられ、
中條学長による特別講義を受けることが出来る機会は、失われてしまった。
これまでにわずか3度しか、直接お会いできることはなかったが、
その一つ一つが、かけがえのないものとして記憶されている。
今回は過去に収録された中條学長の講義を、DVDで受講できることになった。
中條学長のお話を聞いて、先生がかねがね、日本の若者が日本を
愛することが出来なくなってしまった、ということを嘆いていらっしゃったのを思い出した。
何よりも、私たち若者にもっと自分の生まれ育った国のことを知り、愛するように
なってほしい、という想いが強かったのだと思う。
だからこそ、体調を悪くされ、外出が難しくなってきてからも、
日本ベンチャー大學のために動いて下さったのだ。
「歴史を学びなさい」と繰り返し言われたのは、私たちが日本人として
誇りを持って生きるために必要不可欠だからである。
もう一つ、入学式の時に中條学長から、「君は人生の回り道をしたけれども、
良い選択だったね。私も回り道をしたのだよ」という言葉を掛けて頂いたのを覚えている。
先生もまた、陸軍士官学校の学生であったその時に終戦を迎え、人生の目的を
見失いながら、その後旧制高校へと進学、数年遅れの学業を修めていかれた。
この日本ベンチャー大學で1年間学んでいくことが、必ず意味のあるものになると
中條学長が保証して下さったのである。
中條学長が私たちに教え、また期待して下さったものの大きさは、これからも忘れてはならない。
●山近社長の人間力道場・第9回
今回のテーマは、後輩を育てるということである。
後輩を育てることは、後輩にどんな姿を見せるか、どうやってコミュニケーションを
とるか、ということと密接にかかわる。
成功体験よりも失敗体験を多く話すこと。そのためには、まずたくさんの失敗を
重ねていることが必要だ。
20代はもっとも失敗しやすいが、反対に失敗しても痛手の少ない年代と言える。
また、質問力はここでも生きてくる。自分から喋っても自慢話になりやすい。
それよりも、「何か壁に当たっていないか?」と問いかけるほうが、
こちらの言葉が相手の心に響く。
講義を受けて感じたのは、もっとも重要なのは日々の積み重ねである、ということだ。
質問力も、失敗経験の豊富さも、毎日意識して質問し、失敗するようにしないと、
惰性では身につかないものである。
山近社長の日々の活動を思い返すと、大量の質問を繰り返している。
また、人生においては想像もつかないような失敗を(得意分野という飲みの席でも)
繰り返してきたという。
今の山近社長の地位はそうやって築き上げられたのだ、ということがこれで分かる。
それをこうして直接伝えて頂けたからには、私も質問と失敗の積み重ねを意識して取り組んでいく。
From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)
--------------------------------------------------------
●中條学長のDVD講義
松陰先生や日本人の歴史観について話されていた。
その中で特に印象に残ったのが『歴史を学ばない民族は滅びる』という言葉である。
歴史を学ばない人は物事を偏って見るようになり正しい判断が出来なくなる。
歴史だけでなくあらゆるものに触れることが重要である。
また、もう1つ印象に残ったのが『日本は恥の文化』という言葉である。
今の日本人の多くが日本人の誇りを忘れ、日本の良い習慣を蔑ろにしている人が多い。
そういった文化や良い習慣を受け継いでいき、後の世代に伝えていくことが
私達若い世代の役目である。
●人間力道場
・人を育てることが成長に繋がる
関心を持ってない人には人はついて来ない。人を育てるにはまずは関心を持つことである。
その人に関心を持てない場合はその人のやっていることに関心を持つと良い。
後輩を育てるためにはいくつかの方法がある。
1つ目が、自分の成功談より失敗談を話すことである。成功談は後輩にはただの
自慢話にしか聞こえないからである。あえて自分の弱味を見せることで
自分も1人の人間であるということを示すのである。
2つ目が、後輩のしたいことを聞くことである。
相手に話しをさせて肯定し共感することで人は安心感を持つためである。
3つ目が、お酒を飲みに行くことである。お酒は良い意味で人の腹の中を
見せ合うことが出来る唯一の方法であり、より深く付き合うことが出来るからである。
いずれ社会に出れば私も後輩を持つことになる。
その時に後輩を育てることで後輩も成長出来るが教える私も成長出来るのである。
自分も将来出来るであろう未来の後輩のためにも、社会に出るまでに
学生で出来ることを今の内に身につけていきたい。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-----------------------------------------------------
●中條学長のDVD特別講義
・日本人の自覚。
松陰先生のお話から日本人としてのあり方についてであった。
中條学長が思う松陰先生の凄いところは、個を大切にしていることである。
そして、今の学生と決定的に違うところは「感度の高さ」であると仰られていた。
確かに、松陰先生のような日本国を常に考えて行動している人は少ないと感じた。
また、中條学長が白板にある言葉を書いた。それは「時務学」である。
私はこの言葉はどんな意味なのか、わからなかったため
インターネットで調べた。時務学とは、知識技能を学ぶことらしい。
そして、それは人間学と合わせて学ぶことが必要であるという。
そう思うと、中條学長が仰られていた、「日本が情けない国になっている」
ということも辻褄が合う。
つまり、現代の日本人(特に私たちの世代)は人間学を学んでこなかったのだ。
ですから、私がベン大にいる間は人間学を学ぶことに必死に取組んでいきます。
特に、戦争のこと、先人達の考えを中心に学んでいきます。
●人間力道場 ~第9回目~
・"事"に関心をもつ
これは山近社長が大美賀先輩に送った言葉である。
一般的に人には嫌いな人と好きな人がいる。それが原因で仕事に影響することもある。
私もアルバイトではあるが、経験したことがある。
その解決策が見つからなかったので、私はその人の凄いところを懸命に探す努力をした。
けれども、それは続かなかった。
しかし、今回の人間力道場でその答えを見つけた。それは、人に関心を持つのではなく
その人がやっていること(仕事など)に関心をもっていけばよいということである。
確かに、関心を人から事に移動すれば感情なんて関係ない。
その人がしていることにだけ評価すればいいんだと感じた。
会社に勤めた時、もし、嫌いな人が出現しても“事"に関心をもつようにする。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
---------------------------------------------------------
松陰先生や日本人の歴史観について話されていた。
その中で特に印象に残ったのが『歴史を学ばない民族は滅びる』という言葉である。
歴史を学ばない人は物事を偏って見るようになり正しい判断が出来なくなる。
歴史だけでなくあらゆるものに触れることが重要である。
また、もう1つ印象に残ったのが『日本は恥の文化』という言葉である。
今の日本人の多くが日本人の誇りを忘れ、日本の良い習慣を蔑ろにしている人が多い。
そういった文化や良い習慣を受け継いでいき、後の世代に伝えていくことが
私達若い世代の役目である。
●人間力道場
・人を育てることが成長に繋がる
関心を持ってない人には人はついて来ない。人を育てるにはまずは関心を持つことである。
その人に関心を持てない場合はその人のやっていることに関心を持つと良い。
後輩を育てるためにはいくつかの方法がある。
1つ目が、自分の成功談より失敗談を話すことである。成功談は後輩にはただの
自慢話にしか聞こえないからである。あえて自分の弱味を見せることで
自分も1人の人間であるということを示すのである。
2つ目が、後輩のしたいことを聞くことである。
相手に話しをさせて肯定し共感することで人は安心感を持つためである。
3つ目が、お酒を飲みに行くことである。お酒は良い意味で人の腹の中を
見せ合うことが出来る唯一の方法であり、より深く付き合うことが出来るからである。
いずれ社会に出れば私も後輩を持つことになる。
その時に後輩を育てることで後輩も成長出来るが教える私も成長出来るのである。
自分も将来出来るであろう未来の後輩のためにも、社会に出るまでに
学生で出来ることを今の内に身につけていきたい。
From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)
-----------------------------------------------------
●中條学長のDVD特別講義
・日本人の自覚。
松陰先生のお話から日本人としてのあり方についてであった。
中條学長が思う松陰先生の凄いところは、個を大切にしていることである。
そして、今の学生と決定的に違うところは「感度の高さ」であると仰られていた。
確かに、松陰先生のような日本国を常に考えて行動している人は少ないと感じた。
また、中條学長が白板にある言葉を書いた。それは「時務学」である。
私はこの言葉はどんな意味なのか、わからなかったため
インターネットで調べた。時務学とは、知識技能を学ぶことらしい。
そして、それは人間学と合わせて学ぶことが必要であるという。
そう思うと、中條学長が仰られていた、「日本が情けない国になっている」
ということも辻褄が合う。
つまり、現代の日本人(特に私たちの世代)は人間学を学んでこなかったのだ。
ですから、私がベン大にいる間は人間学を学ぶことに必死に取組んでいきます。
特に、戦争のこと、先人達の考えを中心に学んでいきます。
●人間力道場 ~第9回目~
・"事"に関心をもつ
これは山近社長が大美賀先輩に送った言葉である。
一般的に人には嫌いな人と好きな人がいる。それが原因で仕事に影響することもある。
私もアルバイトではあるが、経験したことがある。
その解決策が見つからなかったので、私はその人の凄いところを懸命に探す努力をした。
けれども、それは続かなかった。
しかし、今回の人間力道場でその答えを見つけた。それは、人に関心を持つのではなく
その人がやっていること(仕事など)に関心をもっていけばよいということである。
確かに、関心を人から事に移動すれば感情なんて関係ない。
その人がしていることにだけ評価すればいいんだと感じた。
会社に勤めた時、もし、嫌いな人が出現しても“事"に関心をもつようにする。
From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)
---------------------------------------------------------




























 RSS 2.0
RSS 2.0












