東京校の講義レポート
平成23年(2011)【11月30日(水)】 呉真由美先生(速読コンサルタント) 『速読学』
2011/11/30
コメント (0)
■能力は上から引っ張るイメージで。
能力は何でも出来るレベルを底辺とすると、
高いレベルになると出来ることが少なくなる。
ピラミッド図のようなイメージだが、頂点はほんの些細なことしかできない。
その些細なことでも出来るリミッドを超えていく、
つまり頂点の高さが上がるとピラミッドの底辺も比例して大きくなる。
要は完璧にできる、を繰り返しても能力アップにはならず、
大まかでも限界のレベルを上げることが強化するのに適した方法なのだ。
プロはできるまでやるから、できるようになるのだ。
ひたすら信じてやり続けて能力が開花していく。
■科学よりも感覚の方が進んでいる。
科学で証明されていないことは結構ある。
技術が進んだ現代ならほとんどが証明されていると思っているが
解明できてないことは無数にあるものだ。
東洋医学、波動、スピリチュアルなど驚くことはあるが、無いとは誰も証明できていない。
ただ盲目的に信じるのではなく、その世界を自分も感じることが重要なのだ。
自分のものにする、知恵に変えていく。
私たちは証明できること、目に見えることに安心するが、
興味を持って素直にやってみると段々と成長の糧になっていくものだ。
From:佐々木信(弘前大学卒、北海道出身)@JVU3期生
-------------------------------------------------------------
速読を行うと、必ず「気づき」「感動」「前回との比較」について考える機会をいただきます。
速読をして気づいた事は何か、感動した事は何か。
速読はただ技術を身に付けるだけではありません。
重要なのは速読をどう生かしていくかです。
本を読むときに生かすのはもちろんの事、それ以外でも
どう活用できるのかを考えるのが非常に重要です。
これは速読に限った事ではなく、他の講義で教わった事でもそうです。
必要なのは、理解して実行して応用する事だと感じました。
速読をする時、必ずといって良いほど、「前回」を意識します。
前回はこのスピードで読めた、じゃあもっとはやくして読んでみよう。
この意識は非常に重要ですが、今回、私の意識のレベルが甘かったと認識させられました。
前回、かなり必死に読んで、本1冊を5分で終えました。
今回、3分半以内と言われ、あせって読んだ所、3分半で読み終えました。
かなり必死で限界と思った5分を3分の2にまで縮める結果が
次の講義であっという間に出ました。
自分が感じる限界というもののいい加減さを感じました。
本当にそこが限界なのか、それを確かめるためには
「前回より早く」という意識を常にもって繰り返し、
本当に出来なくなるまで試す事が重要だと感じました。
From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@JVU3期生
-------------------------------------------------------------
1.楽しいことは勝手に、嫌いなことは意識して
楽しいことは意識しないでも勝手にやるので、勝手に上達する。
しかし嫌いなことは、わざわざやろうとはしないので、いつまでも嫌いもしくは苦手なまま。
当たり前のことに聞えるかもしれないが、
言われるまで意識をしたことがなかったので、初めて気づきました。
私は得意だから好き、苦手だから嫌いだと思っていたが、それは逆。
好きだから何もしないでも得意になった。そして嫌いだから苦手になった。
こういった関係をしっかりと見つめなおしてみると、
嫌いじゃなくなれば、苦手ではなくなる、と思えるようになる。
2.人はみんな天才
天才といえば、勉強が出来る人によく使ったりするが、
よく考えれば、頭が良いことの形容詞ではない。
ある特定のスポーツだったり、ゲームだったり、色々な天才がいてもいいのだ。
人には必ずそういった天才の部分が1つはあると私は思う。
天才の条件は誰でも持っている。
後は気づいて伸ばしていくだけで、特定の天才にはなれる。
そういったものを見つけることが、
自分の夢ややりたいことにも繋がってくると私は感じました。
こういった意識改革や、動機付けはとても成長につなげることができる。
しっかりと意識して行動します。
From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@JVU3期生
能力は何でも出来るレベルを底辺とすると、
高いレベルになると出来ることが少なくなる。
ピラミッド図のようなイメージだが、頂点はほんの些細なことしかできない。
その些細なことでも出来るリミッドを超えていく、
つまり頂点の高さが上がるとピラミッドの底辺も比例して大きくなる。
要は完璧にできる、を繰り返しても能力アップにはならず、
大まかでも限界のレベルを上げることが強化するのに適した方法なのだ。
プロはできるまでやるから、できるようになるのだ。
ひたすら信じてやり続けて能力が開花していく。
■科学よりも感覚の方が進んでいる。
科学で証明されていないことは結構ある。
技術が進んだ現代ならほとんどが証明されていると思っているが
解明できてないことは無数にあるものだ。
東洋医学、波動、スピリチュアルなど驚くことはあるが、無いとは誰も証明できていない。
ただ盲目的に信じるのではなく、その世界を自分も感じることが重要なのだ。
自分のものにする、知恵に変えていく。
私たちは証明できること、目に見えることに安心するが、
興味を持って素直にやってみると段々と成長の糧になっていくものだ。
From:佐々木信(弘前大学卒、北海道出身)@JVU3期生
-------------------------------------------------------------
速読を行うと、必ず「気づき」「感動」「前回との比較」について考える機会をいただきます。
速読をして気づいた事は何か、感動した事は何か。
速読はただ技術を身に付けるだけではありません。
重要なのは速読をどう生かしていくかです。
本を読むときに生かすのはもちろんの事、それ以外でも
どう活用できるのかを考えるのが非常に重要です。
これは速読に限った事ではなく、他の講義で教わった事でもそうです。
必要なのは、理解して実行して応用する事だと感じました。
速読をする時、必ずといって良いほど、「前回」を意識します。
前回はこのスピードで読めた、じゃあもっとはやくして読んでみよう。
この意識は非常に重要ですが、今回、私の意識のレベルが甘かったと認識させられました。
前回、かなり必死に読んで、本1冊を5分で終えました。
今回、3分半以内と言われ、あせって読んだ所、3分半で読み終えました。
かなり必死で限界と思った5分を3分の2にまで縮める結果が
次の講義であっという間に出ました。
自分が感じる限界というもののいい加減さを感じました。
本当にそこが限界なのか、それを確かめるためには
「前回より早く」という意識を常にもって繰り返し、
本当に出来なくなるまで試す事が重要だと感じました。
From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@JVU3期生
-------------------------------------------------------------
1.楽しいことは勝手に、嫌いなことは意識して
楽しいことは意識しないでも勝手にやるので、勝手に上達する。
しかし嫌いなことは、わざわざやろうとはしないので、いつまでも嫌いもしくは苦手なまま。
当たり前のことに聞えるかもしれないが、
言われるまで意識をしたことがなかったので、初めて気づきました。
私は得意だから好き、苦手だから嫌いだと思っていたが、それは逆。
好きだから何もしないでも得意になった。そして嫌いだから苦手になった。
こういった関係をしっかりと見つめなおしてみると、
嫌いじゃなくなれば、苦手ではなくなる、と思えるようになる。
2.人はみんな天才
天才といえば、勉強が出来る人によく使ったりするが、
よく考えれば、頭が良いことの形容詞ではない。
ある特定のスポーツだったり、ゲームだったり、色々な天才がいてもいいのだ。
人には必ずそういった天才の部分が1つはあると私は思う。
天才の条件は誰でも持っている。
後は気づいて伸ばしていくだけで、特定の天才にはなれる。
そういったものを見つけることが、
自分の夢ややりたいことにも繋がってくると私は感じました。
こういった意識改革や、動機付けはとても成長につなげることができる。
しっかりと意識して行動します。
From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@JVU3期生
平成23年(2011)【11月28日(月)】 尾崎真澄先生(オザキエンタープライズ株式会社 代表取締役副社長) 『幸福学』
2011/11/28 21:17:02
コメント (0)
 1.言葉で引き寄せる
1.言葉で引き寄せる 本日は、自分の気持ちを良い方向へ持っていけるようにする方法を
沢山教えていただけました。
その中でも、言葉の大切さに私は着目しました。
「俺は軽い、俺は軽い」と思えば人は本当に軽くなる、
またはそう脳が錯覚するのか、本当に軽くなる。
逆も同じで重く感じる。
この自分の方法は、自分を高めることにもとても有効で、
たとえば、できないことやりたくないことでも「俺はできる!」と思えば、
失敗することなんてないのだ。
言葉に言った事は、必ず引き寄せることができる。
前にならった引き寄せの法則の気持ちverだと感じました。
ハッピー体操も毎日やらせていただいているが、
あれもこういった種類の自分の気分の上げ方だと思います。
朝に自分を高めて、一日良い気持ちで生活できるならば、
とても価値のあることだと改めて感じました。
ベンチャー大學では、新しいことやスピーチなど、苦手だったり、緊張したり、
できないと思ってしまうことも多々ある。
しかし、こういった言葉を発して自分を変えていくことができれば、
それは無敵だと感じました。
実際、私は体調がよくないときでも、
「平気だ!」と言って出かけるようなタイプなので、とても私向きだと感じました。
今後は、ことあるごとに使っていき、自分に落とし込んでいきます。
From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@JVU3期生
 ■心と身体は密接に関わっている。
■心と身体は密接に関わっている。笑いたい気分でなくても顔を作って笑っていると
脳が錯覚して楽しい気分になってくる話はよく聞く。
身体を調整する事で脳にまで影響を与えることができる。
今回の講義で心から身体に影響を与える事が出来ると学びすごく驚いた。
心からでも身体からでも双方向に作用し合うということは
自分マネジメントに役立つからだ。
イメージトレーニングで身体がやわらかくなる例から
自分の身体を知ることも大事だが、調子が良い状態に変えることができる。
気分がへこんでいる時は身体から元気を伝える。
疲れがたまっている時はイメージで元気を想像する。
ハイパフォーマンスを常に出せるように
最高の状態を発揮するために両方からプラスにしていく。
■五感を澄ますと新たに気づく事がある。
林檎を頂きたべたのですが、大学時代たくさん林檎を食べていましたが、
神経を澄ますと味の違い、食べる触感、喉を通る感触をよく感じる事ができました。
日頃から神経を尖らしてばかりいると疲れる。
けどもリラックスして五感が開いていればちょっとした違いに気づく事ができるようになる。
感性が豊かな人は些細な違いに敏感に反応できる。
もっと五感を通して色々経験し、ささやかな意味にでも気づいていく。
From:佐々木信(弘前大学卒、北海道出身)@日本ベンチャー大學3期生
 ■ストローク
■ストローク→今回はいつもの1分間ストロークの2倍の時間、
2分間のストロークを行なった。
いつもより長いストロークだったが、2分間ストロークをすることができた。
聴き手の安斎くんの聴き方が良かったからだ。
ストロークをすることによって、
・自分の良いところをパートナーから教えてもらえる
・自分が相手の良いところを見つける習慣ができる
という2つのメリットがある。
今回、安斎くんにストロークをしてもらってポジティブな氣持ちになった。
朝のスタートとしては最幸なスタートだ。
また、ベンチャー大學でも朝礼でこのストロークを取り入れてみては?と思った。
毎回違うテーマでストロークをすることによって、相手を褒める力も向上すると思う。
これがより相手とのコミュニケーション能力を向上させると思います。
また、お互いの成長をストロークにより実感できる良い機会だと思う。
"幸福はつかみとるもの"
講義中に尾崎先生が仰った言葉。
幸福は舞い込んでくるものではなく、つかみとるもの。
幸福をつかみとるためには、徳を積むことが大切だと思った。
また、普段からポジティブな姿勢、
言葉で幸福を引き寄せたり、受け入れる準備もすることが大切である。
宇宙銀行やザ・シークレットなど。
日頃から小さなことでいいから
幸福をつかみとるための行動を積み重ねていく。
From:小田和浩(富山大学卒、山口県出身)@日本ベンチャー大學3期生
 『体調と心の状態は、紙一重』
『体調と心の状態は、紙一重』私が風邪をひいていたからか、元気がないとすぐに指摘をいただいた。
そこで教えていただいたのは、ワクワクを想像することだ。
自分が元気になったときの姿を想像するだけのことだが、
予想以上に効果が高い。
風邪だったので、その日の気分はかなり落ち込んでいたが、
ワクワクすることで、体が軽くなる。
辛いときこそ、楽しいことを考えることの大切さを学ばせていただいた。
From:安齋義仁(いわき明星大学卒、福島県出身)@日本ベンチャー大學3期生
平成23年(2011)【11月25日(金)】 鳥越昇一郎先生(マーケティングウイング 代表) 『事業創造』
2011/11/25
コメント (0)
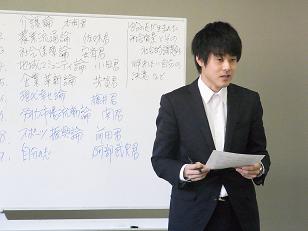
今回初めての取り組みと言う事で小論文を書きました。
テーマは各自、鳥越先生に与えられたもので、
自分の志に関わる分野についてです。
私のテーマは「農業流通論」を与えられ、
書くために今一度勉強しなおしました。
実際に書いてみると、農業の現状とその問題点が明確になり、
社会情勢が自分の事業とどう関わるかを発見しました。
自分がしたい事は何か、そのテーマは重く難しいかもしれません。
しかし、この分野で問題になっている事は何か、
そう問われると客観的に分析でき書きやすいです。
問題点から事業を考えると目的意識が明確になり、
事業を決定しやすく、焦点が定まってくる。
また差別化を図る要因にもなる。
より現状を分析することで自分の事業へと反映されていきます。
■志は厳しい決意
夢は「快い想像」、志は「厳しい決意」である。
夢と志の違いは隔たりが大きい。
自分を振り返ると、今考えているのは正直夢に近いです。
達成したら嬉しいな、ワクワクする事業だな、と考えるのが楽しく、
形になるのが楽しくもあります。
しかし、現実に起業するとなると、相当の苦労があります。
挫折や失敗などあり、順調に進むことはかなり稀です。
もし辛い時にでも続けていこうと思えるのは、
その事業が心から好きであるからではないでしょうか。
根本的な動機とそれを実現したい気持ちが志になります。
まだ夢の段階ですが、自分の考える事をトコトン好きになる、
憧れていつかは達成したいと思えるくらい好きになる。
いずれは志になるよう力を溜めていきます。
From:佐々木信(弘前大学卒、北海道出身)@日本ベンチャー大學3期生

鳥越先生が、最後の時間に仰っていた言葉です。
ある事について、その人なりの考えを持っていること。
簡単に言うと、そういう意味です。
これがないと、他人より一歩でも前へは行けないだろうと、
その他大勢に埋もれてしまう、と感じました。
たとえ、異色な光、色を放っていようと、他人より目立っていなければ相手にされない。
そして、他人に何と言われようと、曲げない何かを持っていなければいけない。
それは、素直どうこうとは違うと思います。
凛とした態度で語る。
一切ブレない、ここが大切です。
そのためには、中途半端な勉強ではいけません。
自分に厳しく、そして、1つのことに打ち込むこと。
難しいことですが、実践していきます。
From:芳賀淳(城西国際大学在籍、福島県出身)@日本ベンチャー大學3期生

意味を簡単に言うと、独特の意見や主張、ひときわ優れた見解をもっている、ということだ。
昔の私だったら、そんなものは持って無いし、持って無くても別にかまわないと考えただろう。
しかし、事業創造を続けていき、自分なりに立てたい構想や姿が見えてきている今、
何か人には無い自分なりの意見や考えが重要になってくると感じました。
これは日々の生活では、手に入れるのはとても難しいことだと思う。
しかし、この日本ベンチャー大學での講義、そして事業創造を続けることで、
自分なりに特化していける部分は絶対に出来ると私は考えました。
私だったら、介護施設・介護職については「一家言」を持てるようにならなくては、
起業したとしても、そこらの一般施設と同じになってしまう。
事業・企業を存続させること、そして介護職というモノのなかで、しっかり儲けること。
ES特化だけでなく、しっかりCSもしていくことが重要だと改めて感じ、考える時間になりました。
2.やりたいことの再確認
今回は「介護論」ということで、論文を作らせていただき、発表させていただけた。
問題点をあげていく中で、自分でどうにかできない問題と、
自分しか出来ない問題、それがよくわかってきました。
今回、私が大きく上げた問題点は介護職の給与の低さ、それによる人数の減少、
そして、根本である少子高齢化です。
この中で、自分でも取り組めること、それは職員の働きやすい現場モデルを作ること、
そして、介護職でキャリアアップのシステムをとり、給与を改善すること、だと感じました。
私だけでは取り組めない事として、
介護福祉士という資格以上の資格を作ることでの助成金やキャリアの上昇を狙うこと。
厚生労働省の今後の動きをもっとよくみていくことが、今の私には大切だと改めて感じました。
介護という職業が安定していた2000年最初のほうでは、
沢山の人がこの職を目指していたが、今では、資格をもっていても諦めてしまう人がいるほど、
給与の少ない仕事になってしまっていることは、今回調べてみないと、知ることができなかったと感じます。
今後も、課題に真剣に取り組み、少しずつ、しかし確実に、自分を成長させていきます。
From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@日本ベンチャー大學3期生
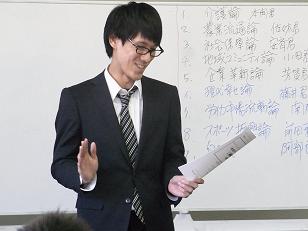

平成23年(2011)【11月23日(水)】 山近義幸(JVU日本ベンチャー大學理事長代行) 『歴史と人間力~安岡正篤先生に学ぶ』
2011/11/23
コメント (0)
【学び】 "農業で人をつくる"
安岡正篤先生が日本農士学校を通じて、人をつくろうと考えておられた事が分かった。
安岡先生によると、文化が成熟しすぎると国家が滅びると記されていた。
例えば、平安時代だったり江戸時代の旗本のような末路をたどるとされている。
しかし、昔の田舎武士のように質素倹約の生活で精神を磨けば
良い人材が育つと考えられた。
そのための農業である。
このことからも武士道のようなものを感じる。
日本男児たるもの美徳を身につける必要がある。
【氣づき】"師をもつ"
安岡正篤先生を学んで、"師をもつ"ことの大切さを改めて感じた。
金鶏学院を設立されたとき、吉田松陰先生が講義をされた松下村塾をモデルにしていた、
というお話はとても興味深かった。
安岡先生は、陽明学を軸に独学で自分の思想や考えを築いた。
そして、その考えや古典の教えをいろんな方々に教えた。
吉田松陰先生ではないが、先生の教えが弟子たちに伝えられて
その弟子たちが事を成すように感じた。
実際に安岡先生の元には多くの政治家が教えを請いに来たという。
何人か師をもち、教えを請うたり相談をすることがどれだけ大切なことかが分かる。
私も松陰先生という大偉人から志について学び、自分の志を高めていく。
From:小田和浩(富山大学卒、山口県出身)@JVU3期生
安岡正篤先生が日本農士学校を通じて、人をつくろうと考えておられた事が分かった。
安岡先生によると、文化が成熟しすぎると国家が滅びると記されていた。
例えば、平安時代だったり江戸時代の旗本のような末路をたどるとされている。
しかし、昔の田舎武士のように質素倹約の生活で精神を磨けば
良い人材が育つと考えられた。
そのための農業である。
このことからも武士道のようなものを感じる。
日本男児たるもの美徳を身につける必要がある。
【氣づき】"師をもつ"
安岡正篤先生を学んで、"師をもつ"ことの大切さを改めて感じた。
金鶏学院を設立されたとき、吉田松陰先生が講義をされた松下村塾をモデルにしていた、
というお話はとても興味深かった。
安岡先生は、陽明学を軸に独学で自分の思想や考えを築いた。
そして、その考えや古典の教えをいろんな方々に教えた。
吉田松陰先生ではないが、先生の教えが弟子たちに伝えられて
その弟子たちが事を成すように感じた。
実際に安岡先生の元には多くの政治家が教えを請いに来たという。
何人か師をもち、教えを請うたり相談をすることがどれだけ大切なことかが分かる。
私も松陰先生という大偉人から志について学び、自分の志を高めていく。
From:小田和浩(富山大学卒、山口県出身)@JVU3期生

本日は安岡正篤さんについて、学ぶことができました。
いつも歴史上の偉人の講義の日は色々調べてから、
何をしたかくらいは理解していくのですが、調べても何をやったのか、全くわからないような人でした。
やっていることが広すぎて、人脈にしても、時の総理大臣や社長など、
様々な人がお会いしていたという。
しかし、現地に行き、色々見てみると平成の名をつけた話だったり、
蒋介石に認められるような人だったり、日本は勿論、国外にまで名を響かせていたことを知りました。
今まで教科書で見たことも無かったような人だったが、
こんなにすごい事をやっていたり、残している人がいる。
それが、勿体無いと感じました。
歴史の偉人の方々から、人間としての魅力を学び、
それを少しずつでも、自分の生活に取り入れる、それが大切です。
私が感じた安岡先生から学ぶこと。
それは人に頼られる人になること。
師とまでは今の時代言われないかもしれないが、
自分の能力や性格を認めてくれる人を増やすこと。
そして、そんな期待にこたえられる自分になりたいと考えました。
2.話の流れを読み、自分の考えを持つ
次に自分に話が振られそうだな。こういってやろう!
そういった考えを常にすることが重要だと、改めて学ばせていただきました。
講師や企業の先生方は、いつも急な話を振られてもすぐに対応する。
これは、皆様がこういったことを日ごろから考えながら、
行動しているからなのだと、本日気づきました。
私も、半年以上ベン大で生活したことで、
日常的にやることについては、常に考えたり、咄嗟でも返せるようになったと自分でも感じます。
しかし、相手の質問というのは、どんな方向から飛んでくるのか、普通はわからない。
訊かれたいこと、訊かれるのがわかることには対応できても、
予想外の一撃に迷ったりすることは未だに多い。
最低でも、自分のことに関しては、どんなことを訊かれてもいいよう、
しっかりとイメージをして、答えを自分の中に持っておくことが、大切だと感じました。
From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@JVU3期生

安岡先生は幼少のころから学問に触れており、
四書を素読できるほど頭がよく、陽明学に通じていた。
また多くの物事への考え方をお持ちで、歴代首相に尊敬された影響を与えた人物である。
吉田茂や三島由紀夫は知っていたが、
その方々にものすごく影響を与えた先生の存在があまり世間で知られていないことに驚いた。
吉田松陰先生も高杉晋作、桂小五郎の方が認知されている。
歴史には流れがあり、すぐれた行動家には優れた先生がいると
改めて師匠を持つ事の大事さを感じました。
ベン大の仕組みは、日々、師が変わる事です。
講師をしてくれる方を尊敬して
何か学べるところはないかと、常に考える姿勢を今一度腰を入れて取り組みます。
■ベンチャー大學が各地に広がっている。
今回、山近社長の講義の半分が
ベンチャー大學の各分校を紹介するホームルームとなった。
日本各地に広がっていき、たくさんの人が教養を学ぶ機会が増えるのはすごく嬉しい事です。
また私の学生時代にもベンチャー大學があればな、と受けられる人たちがうらやましくもあります。
しかし今私はここの学生であり、中條先生曰く、「価値を作る側」ということです。
今は講義を受けさせて頂いている側ですが、
いずれはその講義の価値を伝える側、それも結果でです。
東京本校の生徒として名前に恥じないよう、残り4カ月より一層精進していきます。
From:佐々木信(弘前大学卒、北海道出身)@JVU3期生

講義の予定表で名前が出てきて初めて知りました。
しかし、調べてみると、各界の著名人や総理大臣が師と仰ぐほどの
とてつもないほどの大物だと知りました。
そんな方を何故知らなかったのか。
一つは私の勉強不足、もう一つは表舞台に目立って出てくる方ではなかったから、と感じました。
歴史の資料や教科書で出てくる内容は
あくまで表の部分を読み取ったに過ぎないのだと感じました。
私は、何故安岡先生がこんなにすごい方に育ったのか興味が出ました。
なので、記念館に行き、安岡先生の生涯の年表を見てきました。
安岡先生が小さい頃行っていた素読という言葉が私の中でひっかかりました。
そもそも「素読」を知らなかったので、調べると、そのすごさが分かりました。
最初は素の状態で読むのかと思ってました・・・。
素読とは、全てを暗記するまで読む事。
少年期に四書五経を近所のおじさんから教わり素読した
という事実に安岡先生のすごさが伺えます。
小さい頃からすでに儒教に親しんでおり、学校では剣道に勤しんでいた。
剣道では大会で成績も残され、
文武両道をすすんでいったすごい方なのだと感じました。
山近社長の講義では、
まず初めに日本ベンチャー大學の全国展開の状況を聞かせていただきました。
全国での日本ベンチャー大學の模範となる立場であると改めて感じ、
改めて気合を入れて精進しなければと感じました。
山内社長のお話では、リーダーになるために必要なものについて教わりました。
人間的魅力、マネジメント、専門的機能。
この3つを身に付け、こうあるためにどう具体的に行動すれば良いのか、
重要だなとお話を聞いて感じました。
このお話をされる前に、山内社長は何となく話を振られると分かっていたとおっしゃっていました。
いつも全体の状況、流れを見られており、
いつでも何かがあれば何かができるように備えていらっしゃるという事。
その姿勢はとても参考になり、見習わなければと感じました。
最後に山近社長から、5年後に本を出せる人間になれとお言葉をいただきました。
それは、自分なりの意見を持って、
人に指導できるようになるまで昇華しろという意味なのかなと私は感じました。
自分が理解したら終わりではなく、理解した後、どのようにして後世に伝えていくか。
伝え方まで上手く考えるのが、本当に理解したという事につながるのかなと感じました。
From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@JVU3期生



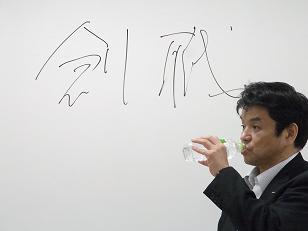





平成23年(2011)【11月22日(火)】 『ザメディアジョン感謝祭2011』
2011/11/22
コメント (0)

初めに感じたのは野田先生と中條先生は同じ意見を持っている人物ではないという事。
そして、それにもかかわらずとてもあつい信頼関係がある事です。
時にかなりディープな内容もあり、公開対談は非常に濃い内容でした。
「日本を変えるには」という件について。
意見が2人とも違うにも関わらず、とてもあつい思いのこもった、なるほどと納得する意見でした。
■野田先生の意見
日本を変えるなら自分自身の誇りを信じる人間が必要である。
何かを実現するには知恵と努力が必要だ。
■中條先生の意見
日本をスイスのような綺麗な国にするべきだ。
その日本が攻撃されれば、その国に世界中からブーイングがくるような国にしなければならない。
野田先生のおっしゃる人間とは周りに流されず、
自分の考えをきちんと持てる人間かなと、意見を聞いて感じました。
戦後、教育の改革により、考えが変わってしまった日本人。
しかし改革は7年、それ以降は元に戻っているのだから日本人のせいである。
今一度、しっかりと自分達を見つめなおす必要があると感じた。
中條先生のおっしゃった意見はとても新鮮で魅力的でした。
新鮮と感じたのは、物事を回避する目線で、中條先生は日本を変える事において、
戦争で侵略されないように「攻撃させたくなくさせる」という視点で語っていただきました。
戦争は人の心理から生まれるものであるのに、
自分は表面の事実だけしか見てなく、それは非常に盲点でした。
綺麗な、攻撃したくなくなるような日本、私も作っていきます。
野田先生は、教育が悪いからベンチャーが育たないとおっしゃいました。
個性を伸ばせ!ともおっしゃいました。
下に伝える、自分の体験を話すという事が非常に重要で、
それが良い人間のいる社会を維持していくために必要な事なのだと感じました。
これからの時代、創職系男子が日本を変えていく!という素晴らしいお言葉をいただきました。
私は、自分から日本を変えていくよう、知恵と努力と行動力をもって動きます。
From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@日本ベンチャー大學3期生

野田先生は次の時代を作っていくのは、仕事を自ら創ることだと仰いました。
もう日本は大企業と中小企業の差が固定したようであり、ましてやベンチャー企業は育ちにくい文化だ。
しかしアジアでは次々に栄えており、日本にとって代わろうとしている。
労働力は日本よりも安く、技術も上達しているからだ。
今までの日本と同じように就職活動をしても将来は同じように安定しているわけでもない。
人の手でやっていたことが機械に変わる可能性もある。
ではそんな時代に必要となることは何か。
人に甘えないで自分で考え行動していくことが安定した生活を築けるはず。
職に就くではなく、職を創る人間になる。
From:佐々木信(弘前大学卒、北海道出身)@日本ベンチャー大學3期生

→私はまだまだ歴史には疎いので、この言葉を聞いた時にすぐ意図が分かりませんでした。
しかしながら中条先生がおっしゃった昔の軍人は、侍と同じでした。
国の為に、愛する人のために闘いに行く、志高い人。
どこからどこまでを軍人というのか分かりませんが、
私は軍人は国を守るというイメージがありますから、悪とは思えません。
そういった時代背景も、自分は何も知らないのだと思い知らされました。
全てを知らずして意見はできませんが、国家が軍人を犠牲にして悪にしたのなら、
国家が責任を持って正すべきだと思います。
2.感動(涙)byベン大生@ベン大出し物
→最初の駆け足から始まり、マイクなしでのスピーチは、とてもベン大らしく、素敵でした。
急に雰囲気が変わられて最初はびっくりしましたが、
スピーチを聞いていると感動して泣きそうになってしまいました。
他の浴衣インターンの方たちもそう言っておりましたし、
感謝祭にお越し下さった皆さんも、ベン大に興味を持ったりしていました。
ベン大の就活コースとして参加させて頂いて、改めて光栄なことだなぁと思います。
ちなみに一番面白かったのは、小林さんがちゃんとナレーションなさっていたことです。
いつ茶々を入れないか…と心配でした。(驚愕でした)
From:高橋沙姫(東洋大学4年生)@日本ベンチャー大學就活コース

私としては、想像以上に上手く出来たのではないか、と感じています。
当日色々なトラブルに遭ったり、緊張して噛んでしまったり、
たくさんの事がありましたが、それも含めてとても楽しい経験をさせていただけました。
あんなに広い会場そして場で、皆様に口で伝えることができていなかった気持ちを
直接伝えることができて、本当にスッキリというか、気持ち良い気分です。
皆様、良かった、や実現できるようにがんばれ!という温かい言葉をかけてくださいました。
本当に、私達の周りには、勉強になる人達がいっぱいいることを、
本日改めて感じると共に、そこへの感謝をもっともっと伝えていく大切さを学ぶことが出来ました。
口で言うことができる機会はとても少ないが、このように貴重な場を頂くことができ、
そして思いを伝えることができた。
私としてはとても満足のいく結果でした。
スピーチとしては、まだまだなところもあるので、
この程度で満足せず、今後もしっかりと勉強していきます。
From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@日本ベンチャー大學3期生






- < 前
- Page 1 / 4


 RSS 2.0
RSS 2.0












