広島校ブログ
日本ベンチャー大學広島校の講義の様子をお伝えします。
平成24年(2012)【9月8日(土)】 大西恵子先生(大西恵子事務所 代表) 『コミュニケーション学』
2012/09/08
コメント (0)
 ①やったこと
①やったこと新聞アウトプット、朝礼、講義(「伝え方を磨く」大西恵子先生)、終礼
②気付き
私は人前で話をしたり、目上の人と話すことに苦手意識を感じていた。
拙い言葉遣いで、相手を不快にしてしまうことが、とても恐かった。
しかし、それは意識のベクトルが
自分の「恥ずかしい」「嫌われたくない」という気持ちに向いていたからだ。
何かを話すとき、私は相手の時間をいただいている。
相手の気持ちにベクトルが向いているのなら、
恥ずかしいことよりも、相手に理解してもらうことに集中するはずだ。
「敬語よりも伝える意思が重要」
この言葉が今回の授業でいちばん心に残った。
今後は間違えを極度に恐れずに、
どうすれば伝わるかを考えて簡潔な話し方を心がける。
誤った言葉遣いについては指摘していただいた際に謝罪し、直していく。
失敗を恐れてばかりでは、話し方の上達も遅い。
意識があれば技術はついてくるという教えを、私はこう解釈した。
また、大西先生が私たちの発表練習を聞いてくださっているときに
書かれていたメモの情報量の多さに驚いた。
大西先生は、普段から毎日の出来事や気づきをメモされている。
こういったことの積み重ねが、
大西先生の洗練されたコミュニケーションの源ではないかと思う。
外の世界にアンテナを張り、他人を思いやる気持ちを保つ。
そのために高校時代から読み続けている自己啓発本を毎月読み返すことにした。
③実行項目
来月の配属面談の要点を絞り、
自分の考えを伝える練習をする。
④感想
本日の講義では発表の実践練習があった。
皆が発表者に注目しながら笑顔で聞いていたため、
とても話しやすかったと全員が感じていた。
ベンチャー大学・広島校も学生が増え、とても雰囲気が良い。
この調子で学習速度も向上し、
さらに充実したクラスになっていくことへの期待が高まる。
私も同期に負けないように、様々な刺激を受けながら成長していこうと思う。
From:河本将治(広島大学4年)@JVU広島校1期生
 大西恵子先生に営業活動の秘訣や言葉の使い方を教わり、
大西恵子先生に営業活動の秘訣や言葉の使い方を教わり、これから社会人になって活かせる知識ばかりでした。
「話をするのに8割は準備がものをいう」という話を聞き、
私が現在、実践していることと重なるところがあると実感しました。
私自身、自分の趣味、旅行をしたときの思い出、
気になる記事などについてノートに貼ったり書いたりしていて、
「いつか話のネタになったり、役立つことがあるだろう」
という気持ちで取り組んでいます。
こういった取り組みが人と話をするときに活かされているので、
これからも継続していきます。
話をするときにもう少し構成を練って話した方がいいという指摘を
大西恵子先生から受けたので、これからは意識して話の筋立てをしていきます。
From:山本健勝(広島修道大学4年)@JVU広島校1期生
平成24年(2012)【9月1日(土)】 桑野隆司先生(株式会社ピアズ 代表取締役) 『リアル経営学』
2012/09/01
コメント (0)
 ~リアル経済学 “セルフイノベーション"~
~リアル経済学 “セルフイノベーション"~□全体の流れ(担当:学生リーダー)
8:50 集合
~10:00 新聞アウトプット/フリーペーパー話し合い
-------------------------------------------------------
10:30 会場準備
・株式会社ピアズの方々と名刺交換
・昼食
・来場者のご案内
12:05 講義スタート
-------------------------------------------------------
15:00 講義終了
・後片付け/終礼
17:00 会場撤収
□気付き・意見
■自分の気づき、やる気=成長
「セルフイノベーションのコツ」の中で、「自己成長力を鍛える!」というお話があった。
5項目中、一番印象深かった。
それは私が、ベン大の講義に参加し学んだことと関係する。
ベン大で講義して下さった方もベン大生も共通して言っていたこと
───「主体的に行動する」。
主体的に参加することで得られるものは、
嫌々やっている人よりも多く、成果につながりやすい。
自分から行動することで、周りの人が支えてくれたり色々な情報ももらえたり、
また周囲を元気づけられる。
簡単に述べてしまったが、主体的な行動をすることで、
自分も周囲もいい方向に流れていく。
それはまさに、自己成長力を鍛えるということで、
私の頭のなかで両者がイコールで結びついた瞬間、
新たな「気づき」を得られて非常に嬉しかった。
「成長しよう」「成長したい」と思っていればいるほど、
自分をより多く成長させられるのだ。
こんな嬉しいことはない。
日頃から、主体的に行動してアンテナを高く張っていれば、
人が気づけない事に気づくことができる。
当たり前と言われればそうなのだが、講義で改めて、
気づくことと自分にやる気があることが一緒だと感じることができ、
かつ、気づきを得るために、自ら率先してやるという、
逆矢印に気が付けたことは、大きな成果であった。
また「気づき」のなかには、人の経験や体験を聞いて、
自分のものにすることも含まれているので、
そういう意味でもアンテナを高く保つことが重要であると悟った。
変わった見方をしていることはよくあるが、
これからは「気づきポイント」に気づける見方をしていきたい。
■未来のビジョン
真っ白なパズルを完成することは非常に難しく、
時間ばかりが流れていき、次第にイライラも溜まってくる。
最初は熱心に取り組むばかりで、先生の意図するところが分からなかったが、
「ビジョン」と聞いて、はっとした。
今まで、なってみたいものはいくつかあったが、
「自分にはなれるわけがない」と、どこかで決めつけていた。
だから、口に出して「夢」を語ることが恥ずかしく、
イチローのように「必ずなれる」なんて言えなかった。
だがそうではなかった。
口に出して言うこと、文字にして誰かに伝えること、
誰かにアウトプットしていくことで、一番大きく変わるのは、自分自身なのだ。
「なれない」と思っていた弱虫な自分を追い出して、
「きっとなれる、あきらめるな」と思う前向きな自分を呼び込むことなのだ。
「なりたい」と思った自分に、素直に向き合うことなのだ。
そんな小さなことに、今頃気づいた。
変わり者の岡本太郎も「あきらめる」という語は使わなかった。
私も、あきらめたくない。
自分の人生、未来を、白紙のまま提出したくない。
自分がなりたいもの、やりたいことを、
もっともっと明確に考えよう。もっともっと「できる」と思おう。
亀の歩みでも、夢に向かって、ずっと歩み続けていたい。
将来のビジョンが、今の自分を輝かせてくれるように思う。 自分の未来に感謝。
これから、長い長いスケッチの始まりだ。
□今後実践すること
・正しい努力をする = 文章をたくさん書く!(執筆活動?)
現在投稿し続けている「エグゼ」を継続して進めるほか、
空き時間に、コラムのような文章を書く。
将来のためにも、フリーペーパーのためにも。
・オープンマインドでアウトプット
日頃から思っている感謝や感動、その人の良い所を、相手に伝える。
会える友人や周囲の方々には直接口で言い、
遠く離れた人たちには、メールや電話、facebookで伝える。
「ありがとう」「ごめんなさい」「嬉しい」「楽しい」「いてくれて良かった」
「一緒にいたい」「好き」「また会いたい」「話したい」「気をつけて」
□全体を通しての感想
初の学生リーダーをやらせていただいて、
つっかえながらも何とか全うすることができ、ひと安心。
(依田さん、サポートしていただき、有り難うございました!)
が、次回は依田さんに補助してもらわなくても、
1人で全てできるよう、努力します。
桑野先生のお隣の席ですごく近くて、最初は緊張しましたが、
先生の優しいオーラが伝わってきて、お話を聴いているのが、とても楽しかった。
パズルを最後まで完成できなかったことは残念だが、
普段会わない方々と一緒に作業できたことは非常に楽しかったです。
「経営学」と聞いていたので、難しい話だと考えていたけれど、
私たち学生にも解るように噛み砕いてお話して下さったので、
すんなり頭に入ってきました。
自分の実現したいことを口に出して言うのは恥ずかしかったですが、
何だか「頑張ろう」という気持ちが湧いてきたので、
アウトプットする機会を与えられて良かったです。
また桑野先生の講義、受けたいです!
どうも有り難う御座いました!!
From:横澤彩子(広島大学大学院修士2年)@JVU広島校1期生
 ○講義での気付き
○講義での気付き【お金の持つ価値】
講義の中で桑野先生より「お金の本質について」質問された。
確かにお金があれば、教育、洋服、食べ物をお金を払う事で
恩恵を受ける事ができる。
しかし、お金は行動を行う手段であって使い方は様々だと感じます。
お金と人との関係を見た時にどちらが、これから楽しい、
喜びを与えるのは人だと今回の講義を受けて感じました。
それは、お金で動く人、友情という名で無料で手伝ってくれる人との違いだという事。
【セルフイノベーションのコツ】
目標がなければ、絵のないパズルを毎日作っているんだと
作業をしている時に気付きました。
「そこに絵があれば簡単にできるなぁ」。パズルでは絵=目標という事。
コツは手順を踏んで5つに分けられるとおっしゃられた。
まず目標、気づき、正しい努力をする、他人からの評価、限界を決めない事。
まず、目標(達成したい事)を明確にしてその目標に向かって
毎日少しずつ努力したり、段階的にステップを踏んだり、
自分が達成したい事を他者の前で宣言して、
自分の中の想像が現実になるんだと、鈴木一郎さんを例に例えられた。
それの話しを聞いて講義の前に宣言している意味が理解できた。
○実行すること
日々の生活の中で自分が立てた目標に関して、正しい努力を行う事。
○全体の感想
今回は成功者と失敗者の違いで「オープンマインドとクローズマインド」
でまとめられていて、以前教えていただいた、「Open QuestionとClosed Question」
を思いだして、自分が感じた事はどちらも自分の気持ちと今をどう生きたいかと
他者への思いやりや他者への感謝が共通していると感じました。
また、僕にいつもアドバイスをしてくださる依田さんありがとうございます。
From:金山竹伯(広島工業大学4年)@JVU広島校1期生
平成24年(2012)【8月25日(土)】 『極東国際軍事裁判上映会実写DVD上映会』
2012/08/25
コメント (0)
 ~極東国際軍事裁判 実写DVD上映会をとおして学んだこと~
~極東国際軍事裁判 実写DVD上映会をとおして学んだこと~□全体の流れ(担当:司会進行)
11:00 学生集合・準備
11:30 朝礼
司会進行リハーサル/依田さんとの打ち合わせ
13:05 上映会スタート
・岡崎社長、山近社長挨拶
・学生(佐藤翔平さん)1分間スピーチ
・株式会社ガイヤソリューション代表取締役社長 田中太郎様によるDVD事前説明
13:40 DVD上映スタート
==途中15分休憩==
18:30 上映終了
田中太郎様より解説
次回イベントのお知らせなど
19:00 上映会終了
アンケート回収・後片付け
19:30 懇親会スタート
21:30 懇親会終了
スタッフ反省会
□気付き・意見
■国際法の裁くところ
「極東国際軍事裁判」では、日本の「無罪」を主張した人物として、
パール判事が有名だが、(事前学習でも「東京裁判」と入力すると、
パール判事の記事は多かったが)DVDのなかで、
ベン・ブルース・ブレークニーという、アメリカ人弁護人が登場し、
日本の「無罪」を主張していたことが、とても印象的だった。
もちろん弁護人なのだから、嫌々でも弁護するのは当然なのだが、
映像の中の彼は、冷静かつ毅然とした態度であった。
「戦争は、国際法で定められているのだから、犯罪ではない」
「戦争中に人を殺すことも、(倫理上、悪だが)犯罪ではない」
「原爆を投下した者たちも、殺人罪で裁かれるべきではないか」
「国際法が裁くのは、国家であって個人ではない」 というような、
実に「戦勝国アメリカ」の国民とは考えられない発言で、画面に釘付けになった。
この裁判で、判事の中で唯一、国際法に携わっていたのが、パール判事。
ブレークニー氏も、国際法と外交関係に詳しかった。
日本を「無罪」と主張した両名は、日本を擁護したのではなく、
「国際法」という世界共通の基準のもとで判断を下した。
他の裁判官や関係者がどういう基準で判決を下したのかは、表面上しか知らないが、
「法の公正」のもとに判断して下さったことが、非常に嬉しかった。
当時のアメリカのなかにも、ブレークニー氏のように考えていらっしゃる方が
いたのかもしれないと思うと、少しだけ心穏やかになる。
裁判成立の理由が明らかにされぬまま進行してしまったこと自体おかしさ満載だが、
「正しさ」を以て判決を下すのであれば、まずは、裁く方も裁かれる方も、
同じ土台に乗るのが当然なのに、ほとんどの者が、日本を“特別扱い"して、
同じ座標の上に乗ろうともしていない。・・そう感じられた。
映画中にあった、「戦争責任」と「戦争犯罪」について、もっと勉強する必要がある。
私もそうだが、軍や政府関係者も。
そして、義務教育のなかでも考える時間を取ってほしい。
■「サムライ」の姿
A級戦犯の方々がいたことは知っていても、どんな人物なのか、
具体的に何をしたのか、考える機会を持たず、満州事変や太平洋戦争などを
支持・指揮していたのだろう、くらいにしか思っていなかった。
今回初めて、彼らの実写映像を拝見し、
その雰囲気や口調、考え方の一部を垣間見た。
そこだけ見ていると、彼らが日本を指揮して
戦争を始めた張本人たちだとは、感じられなかった。
被告人席で、神妙に座る彼ら。
時に沈痛な面持ちを見せ、時には涙を見せていた。
ざわつく法廷の中で、彼らと、彼らの親族たちの席だけがしんとして、
まるで、いじめられている子どものようだった。
振る舞いを見ても、思った以上に礼儀正しく、
「本当にこの人たちが、あんなにもおぞましい戦争を
引き起こしたのだろうか?」と、思わされた。
上映後の解説で、田中様が「彼らの振る舞いに、今の政治家にない、
サムライの姿を感じた」と仰っていた。 私も同じ心境だ。
今の政治家の何十倍も、彼らの方が凛々しく、日本国に対する熱意や信念を感じた。
(・・その情熱が、戦争に傾いてしまったことがやるせない)
けれど、忘れてはならないのは、彼らは決して「いい人」などではない。
日本を戦争に引き入れ、国の為と言って、多くの命を捨てさせた最終指揮者たちだ。
B級、C級戦犯の人たちが、問答無用で殺されたことを考えれば、
彼らはきちんと裁判を受けて刑を執行させてもらえる立場にいたのだから、
優遇されていたと、今の私は思う。
そんな彼らでも、現代の私たちに「サムライだ」と思わせる精神を持っている部分は、
評価できるし、評価されるべき点と言える。
■正しい歴史観
田中太郎様が解説のなかでしきりに仰っていた言葉。
上映会当日は、「色々な角度から歴史を知って、
相手の立場ごとの解釈ができるようにすること」だと考えていた。
しかし、研究室の先輩に映画の話をすると、
「(その事実を見て)どう思ったの? どう感じたの?」と聞かれて気付いた。
今の自分は、起こった歴史を事実を丸呑みしているだけで、
歴史を主観的に捉えていないのだ、と。
「正しい歴史観」とは、色々な視点を知ったうえでの、
自分が「正しい」と思う歴史観なのだ、と。
(だからこそ、田中様は「信念を持つように」とも仰っていたのだ)
そこに到達するには、まだまだ足りないことの方が多い。
あの貴重な映像を、自分の「信念」なく、ただ鑑賞してしまったことが悔しい。
「歴史は奥が深い」と感じるとともに、
自分なりの意見を持たなくては、と危機感を覚えた。
□今後実践すること
・歴史を知る努力をする
「日本」という国に生まれ、その国民として生きている以上、
やはり「国の歴史」は知る必要があると、今頃実感しました。
これからは「実際の歴史」について、
なるべく現地現場に出かけて、体感して学びたい。
本も、おすすめ本は読んでおきたい。
・場数を踏む
これは司会進行をさせていただいた時の教訓。
原稿ばかりを見ていたため「自信がなさそうに見える」とのこと。
アドリブでも突然のフリでも対応きるようにするには、
場数を踏むことが一番手っ取り早い。
このため、何かのイベントや企画には積極的に参加し、
「話す」ことについて慣れたい。
□全体を通しての感想
これまで戦争関連の実写の映像を見たことがなく、
「歴史」は、高校の教科書の内容くらいしか知識がなかった。
この実写DVDで、私のなかの「歴史が動いた」。
今まで、歴史とは、もう終わってしまったこと
で、文字で読んで学ぶものというイメージが強かった。
が、ここには、今でも生き継がれる歴史があった。
全然、過去の遺物などではなく、今をつくる土台であり、
今を知る手掛かりであり、「いま」でもあると、感じた。
文字で書き連ねられた歴史より、
この4時間37分の方が、どれほど勉強になったことか。
チベットの友人に聞くと、学生時代に公園で上映されていたと言う。
一緒に鑑賞した友人も言っていたように、
この映像は、義務教育中に、絶対に見せるべきである。
殺されたユダヤ人たちが、除雪車のような大型車で押されていく光景や、
大砲を放った後の衝撃が思っていたより大きいこと、
十数階の建物がいとも簡単に崩れていくことなど、
その映像を見なければ、分からない。
協定や宣言の裏に隠された、各国の思惑も、映像を伴うことですんなり入ってくる。
本を読むことも大事だが、それ以上に、現
場を知ること・当時を知ることは重要なのだと、改めて「体感」した。
今回、学生スタッフとして参加し、司会の経験をさせていただいただけでなく、
貴重な戦争資料にも触れる好機を与えていただけたこと、非常に感謝しております。
From:横澤彩子(広島大学4年)@JVU広島校1期生
 ○講義の気づき
○講義の気づき実際、学生が経営者相手に対して、当日の司会、受付、
会場係のをする事によってイベントの流れをつかむ事ができた。
その中で来られる方に分かりやすく説明するためには
事前に何を話すかを準備し、周りの様子の事を注意してみないといけないと感じた。
【極東国際軍事裁判上映会実写DVD上映会】
講義の中で時々でてくる歴史。
真実の歴史を知る事は過去にどのような関係性から
どんな結果になったかまで知る必要があると感じた。
その点で、今回のDVDはアメリカで保管されていた
実際の映像を元にして作られていて、いつもと違う信頼性を感じる事ができた。
○実行する事
気づいたら自分から動けるように、周りの様子を見て、
今何をすべきか、どうすればうまく行くのかを考えて行動できるように心がけます
○全体の感想
広島校では初めての事であり、リハーサルから終了まで、気が抜けない状況でした。
実際に体験することでその瞬間の様子を瞬時に判断しなければならない事があり、
その後の行動がどう影響するのか先を読まなければいけないと感じる事ができた。
DVDはアメリカで保管されていたし、裁判の判決日が12月23日
つまり、今上陛下の誕生日に判決が下された事に関して
アメリカの思惑を感じる事ができた。
本来戦争の内容を裁判として裁くのは不合理だと感じます。
それは、今まで散々争いがあるはずなのにどうして東京裁判は
判決する必要性があったのかが私の中で疑問に残りました。
歴史を映像として見る事ができて戦争での相違関係を知れて、
その中で、どう日本が行動して行ったのかを
具体的に知る事ができて、大変貴重な体験でした。
また、今の日本は竹島、尖閣諸島、北方領土などの領地の問題を抱えているので、
今後これらの問題が争いにならない事を私はただ祈るだけです。
From:金山竹伯(広島工業大学4年)@JVU広島校1期生
【平成24年8月11日(土)】 渡部一之先生(株式会社プログレッソ 取締役) 『リアル経営学』
2012/08/11
コメント (0)
 本日はプロのスポーツ選手という経歴をお持ちで、
本日はプロのスポーツ選手という経歴をお持ちで、現在は経営者をされている渡辺先生のお話を伺った。
体育会出身の自分にとっては、
会社で活躍する人財をスポーツ選手に譬えたお話に、
たいへん共感の念を抱いた。
また渡辺先生はそれまで自分が一生懸命頑張ってきたことは、
次のステージで必ず活きるとおっしゃっていた。
今回の講義を通じて、私が大学で学んだことを、
社会に出て、どう活かせば良いか、という指針をつかんだ。
社会人は、苦しいことは多くあるでしょうが、
今回の講義と自身の経験を思い出しつつ、
しっかりと成長の糧へと変えていきます。
From:河本将治(広島大学)@JVU広島校1期生
 ~競輪という競技をとおして~
~競輪という競技をとおして~正直「競輪」と聞くと、ギャンブルの部類だし、
おじいちゃんがやっている所しか見たことがなかったため、
どうやって賭けるのか、どこが面白いのか、まったく分からなかった。
今回の講義を通じて、競輪という競技の面白さや、
予想の暴露やその裏を読む面白さなど、新たに知ったことも数多い。
■自分から、やる
同じ練習メニューをやるにしても、自分から進んでやる人と、
言われたからやる人とでは、習熟度合いが明らかに違う。
自分がやろうと思って取り組む人の方が伸びる。
また、そんな人を周りの人間も後押ししてくれる。
それは、弱い(精神的にも技術的にも)人が、負けた時に他人のせいにするのに対し、
きちんと練習を積んで負けた人は、「自分が弱いから負けたんだ」「またお願いします」と、
実に謙虚な姿勢で接していることにも起因する。
たとえ相手がものすごく強くても、それは、
相手がその分自分より多く練習してきただけであって、できるのは当然のことなのだ。
その分をこれから自分が頑張っていって、何とかすればいい。
そのなかでも、自分から積極的に取り組む方が、自分が育つ。
ベン大と関わるようになって1カ月余りが過ぎ、
最近やっと「自分から行動する」ことの意義を噛みしめ始めた。
これまで、心のどこかで他力本願なところがありましたが、
すべて自分次第なんだと気づかされた。
自分がやらないと、まわりは変わってくれない。
自分が動けば、まわりも変わってくれる。――いわゆる「鏡の法則」である。
そうしたら、小さいけれど、変化があった。
自分のことを「いいね」と言ってくれる方が増えて、
私のことをきちんと見てくれる方が増えた。
とても、とても嬉しかった。
自分がちょっと好きになって、自信が持てるようになった。
そういうところまでつながっていくから、
「まず、自分からやる」ことは重要なんだと、今は言える。
これからも自分で積極的に取り組んで、ちょっとずつ自分を育てていきたい。
■勝利のお裾わけ
競輪に「チーム」があると初めて知ったのだが、
遠征に行った際には、その時の最終レースで
一番成績の良かった人が皆に食事などをおごる。
地元に帰った際には、練習に付き合ってくれた人や仲間にもご馳走を振る舞う。
そうして「祝い酒」をして、皆に勝利を還元することで、また次の勝利につなげていく。
自分だけでは勝つことは出来ない。皆がいるから勝てる。
本岡くんも言っていたが、スポーツにおいて、
個人競技なのに団体で支え合う競技は非常に稀だ。
私も、お話を聞くまで競輪がチームや
仲間を大切にしているということに気づかなかった。
賭け事でもあるし、単独プレーなのだと考えていたが、
練習では、バイク誘導などで仲間に支えてもらい、
常に仲間や相手を意識して行う競技なのだと分かった。
支えてくれた仲間への恩返し。それは、自分も嬉しいし、
相手も喜んでくれるし、「win-win」の関係で素敵だなと感じた。
中国人やチベット人は、何か食べるときに必ず「食べる?」と聞いてくれる。
これは、一緒に食べた方が楽しいからなのだそうだ。
私にとっては、カルチャーショックだった。
こうして、自分の幸福をまわりの人たちと共有することで、
仲間との信頼関係も強くなるし、良きライバルとして
自分を高められる存在としていてくれれば、こんなに心強いことはない。
これからも、そんな仲間をもっと増やしたい。
■「夢」より目標
「夢を持つ」より、「目標を持て」
夢は夢のままで、終わってしまうから、達成できる目標として考える。
聞いた瞬間、とてもいい考えだなと思った。
確かに「夢」には希望や憧れが詰まっているが、ある意味、
それだけで終わってしまうことの方が多いかもしれない。
目標は達成しなければいけないものであるから、そこに辿り着くよう努力するものだ。
私も、最近「夢」だったものを「目標」に切り替えて、目指してみようと考えるようになった。
それは上記の理由もあるし、自分だけの人生をもっと楽しみたいと思うようになったためだ。
「夢」も素敵だが、私には汗臭く「目標」を達成する方が合っているようだ。
From:横澤彩子(広島大学大学院修士)@JVU広島校1期生
平成24年(2012)【8月6日(月)】 『広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式』 『JVU全国会議』
2012/08/06
コメント (0)
===========================
~平和式典とパール判事記念碑をとおして~
■「平和」を願う瞬間(とき)
8月6日 8:15 ―――広島に原爆が投下された時間
あれから67年目を迎えた昨日、この時間に、
式典にいらしていた方々が黙とうを捧げた。
しかし、蝉の鳴き声しか聞こえないと思っていたら、
遠くでデモの声が聞こえていた。
誰かも言っていたが、初めて原爆の落とされた地で
同時刻を迎えた自分も同じことを思った。
・・せめて、この時間くらい、原爆で亡くなった方の喪に服すればいいのに、と。
平和の鐘が虚しく聞こえた。
でも、彼らだって、別のところで哀悼しているかもしれない。
かく言う自分だって、これまでの24年分は、この時間を意識したことがなかった。
・・・去年の自分は何をしていただろう? その前は? さらに昔は?
ヒロシマという地に来て初めて考えさせられた、「平和を想う時間」。
6日付けの日本経済新聞の「春秋」に、
「8月ジャーナリズム」という言葉が載っていた。
「この時期だけ、思い出したように戦争だ平和だと騒ぐ、
という指摘だ」(本文抜粋)
何とかかぶれではないけれど、8月のこの時期だけ、
思い出したように戦争や平和について考える。
自分だってそうだ。他の多くの人だって、そう変わらないだろう。
ご指摘が痛く胸をつく。
一方で、「めぐる夏ごとの、社会のさまざまな試みが、あの戦争をかろうじて
「現代」に押しとどめてきた」(本文抜粋)というのも事実だと思う。
式典のなかで述べられていたが、当時を経験した人々は年々減っており、
受け継がなければならない「あの夏」は薄れている。
市長による平和宣言のなかで、3人(当時20歳の女性、
13歳の少年、16歳の少女)の方の話が挙げられていた。
聞いていて、当時の惨状が思い起こされたが、
私の思考回路ではすべてを思い描くことはできなかった。
――それは当時を知らないからだ。
知る努力を怠っているからだ。
それでも、中学生の歳で死体を運ぶ/家族がどんどん死んでいく/
自分だけ取り残される・・・・そんな現状には耐えられない。
式典に出席している人たちが、皆バタバタ死んでしまって自分だけ取り残されたら・・、
もし、今一緒にいるベン大の皆が、今この場で死んでしまったら、どうしよう・・。
考えたら怖くなった。
自分にできることが何なのか、自分はどうしたら「平和」をつくることができるのか、
どうしようもなく分からなくなって、頭がぐちゃぐちゃになった。
そんなときに読み返していた「平和への誓い」。
つらい出来事を、同じように体験することはできないけれど、
わたしたちは、想像することによって、共感することができます。
平和はわたしたちでつくるものです。
身近なところに、できることがあります。
違いを認め合い、相手の立場になって考えることも平和です。
思いを伝え合い、力を合わせ支え合うことも平和です。
なんだか「大丈夫」と言われている気がした。
一人じゃないから、大丈夫だと。
なんやかんや言っても、私は一人ではなく、
いつでも誰かに支えてもらって生きている。
平和について考えたり、平和を願うときは、人それぞれでいいような気がした。
誰かに揶揄されたり、人の嘲笑を買ったりするかもしれない。しかし、
大切なことは、絶対に「平和」を心から忘れないこと。
そうすれば、せめて私のまわりにいる人だけには「平和」を届けられる。
みんながそうなら、いつか世界は「平和」になる。
今はそう信じている。
1日をとおして、そう教えてもらった。
それが私にとって、式典に参加して得た一番重要なことだった。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
本照寺(広島市中区)にある、
ラダ・ビノード・パール氏の記念碑を皆で訪問・拝見した。
正直に申告すると、この方のことは聞いたことがある気がする・・というくらいの認識だった。
山近社長や住職さんのお話を聞き、自分でも彼自身のことをかいつまんで調べてみた。
極東軍事裁判において、日本の全面無罪を訴えた人――。
さまざまに思うところがあったが、以下に一番印象深かった点についてまとめさせていただいた。
■自分なりの判断 -パール判事の≪真理≫-
山近社長のお話のなかで、パール判事は
「(私が日本が無罪と言っているのは)日本のためじゃない。
自分なりに調べて、自分なりの判断を下したからだ」
というような内容を仰っていたと伺った。
調べると、次のような一節をパール判事が仰っていることが分かった。
わたしは1928年から45年までの18年間(東京裁判の審議期間)の
歴史を2年8ヶ月かかって調べた。
各方面の貴重な資料を集めて研究した。
この中にはおそらく日本人の知らなかった問題もある。
それをわたくしは判決文の中に綴った。
このわたくしの歴史を読めば、
欧米こそ憎むべきアジア侵略の張本人であることがわかるはずだ。
2年8カ月にもわたり、日本のあれこれを調べていただいた、その精神に感謝だが、
この数文を読んだだけでも、パール判事がどれだけ丹念に事実を調べ上げ、
他の判事たちと相対していたかが伝わってくる。
それは決して日本を擁護しようとか弁護しようとかしたわけではないのだ、と。
ただ、自分の信ずる≪法の精神≫を貫き通しただけなのだと感じる。
自分のなかに絶対に譲れない、法の在り方や国際正義があって、
それが正しいと思ったから、もしくは他国の判断が間違っていると思ったから、
主張しただけにすぎない。
真理をつかむことはとても難しく、それを主張できるパール判事は非常に凄い人だ。
今まできちんと知らなかった自分が申し訳ない。
今の自分は、正しい判断をしているのかどうか、不安になる時が時々ある。
確かめようもないのだが、人に相談したり、自分と向き合ったり、色々してみる。
そんななかで、最近気づいたのは、
「自分に自信がないなら、色々調べてぶつかってみること」。
これまでのやり方はみな、内にしか向いておらず、
外に向かって自分の正当性を主張することを避けてきていた。
それでは、いつまでも内巻きスパイラルからは抜け出せないのは当たり前だ。
写真だけ見ると分からないが、おそらくパール判事だって
「怖い」と思うことがあったはずだ。(・・と、私は思っている)
自分なりの判断をしたいなら、自分に自信を持ちたいなら、
まずは自分の姿勢をプラスに変えるべく努力して、正していかないと、
賛同や自信、ひいては自分の生き筋は得られない。
パール判事の言葉を見て、改めてそう思った。
+α)
私は、パール判事の主張は、正しいと思っている。
子どもの喧嘩は、起こってしまうとどちらが良いか悪いかなんて関係なくなってしまう。
けれど、「戦争」は違う。
もし、日本とドイツだけが悪いと言うのなら、
パール判事の言うように、正義も法律も真理もくそもない。
パール判事には、その主張から約65年後となったが、
遅ばせながらの「有り難う」を伝えたい。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~un3k-mn/0815-pal.htm
===========================
~第1回 日本ベンチャー大學・全国会議に出席して~
□内容
テーマ:①大學をとおして、自分に身についたこと・続けていること
②これからのJVUにおいて、変えていきたいこと・改善点
・出席者全員の挨拶
・今元さんによる進行・意見聴取・まとめ
・事務連絡
□気づき・まとめ
■「なんでもやってみる」
色々な方が口ぐちにおっしゃっていたこと・・それが「まずは、やってみる」。
徳島校では、校長が「死にはしないからガンガン行け」と仰っているとか。・・かっこいい。
「自分から」「行動」しなくては、意味がない。 そうして「実践する」ことに意味がある。
大人はヒントを与えて見守るだけで、やるのは自分たち。
このような内容を聞いていて、自分は口先だけじゃないかと思った。
「やってみる」とは言っても、最後の最後、尻込みして出来ていないこと、やり過ごしていること、沢山浮かぶ。
京都研修や回天研修も、ドッキリでも参加させてもらえば良かった。
徳島校の方たちが、自分たちでPV作ったり、
大学でアピールしようとしたり、とても力強い前向きベクトルを感じた。
頭で分かっていても身体で行動しないと、本当の理解ではない、と最近教えられ、
「知合同一」を目指しているが、やはり難しいし、これらのお話を聞いていて、
自分にはまだ程遠いと突き放された感覚だ。
だからこそ、こんな「自分をどうにかしたい」。
頭で考えるより、まず行動したい。
いつまでも教わってばかりの自分を卒業して、自分から行動できる人間になりたい。
やはり「人生、やってみなくちゃわからない」のだと、改めて思う。
先の日報にも書いたが、自分はなんだかんだ孤独(ひとり)ではない(はず)。
だからこそ、自分が失敗したら、その分を助けてくれる人は絶対にいるはずだ。
だから、もう少し勇気を出して、人を信じて、
その先の扉を越えて、行ってみたい。
■ 常に「相手」を意識
まずは、「相手の意見を受け止めること」
次に、「自分の意見を、相手が分かってくれるように、発信すること」
よく、「相手に分かりやすく、自分の意見を伝えなさい」と言われる。
が、この場にいた人の多くがまず受け止めることからと仰っていて驚いた。
私も「相手の意見を受け止めること」から始めたいと、常々思っている。
相手が色々聞いてきたり話しかけられたりすると、自分は大概ひいてしまう。
それで自分が失敗したこともある。
自分が言っていることを相手が分かってくれるとすごく嬉しい。
が、それは裏を返せば、相手だって同じことをされたら嬉しいはずで、そうしてほしいはずだ。
両者受け手だと先に進まないので、自分も発信しなければならないが、
やはり、まずは投げられたボールをキャッチすることが先決なのだ、と考えさせられる。
ボールに例えて気づくが、自分からボールはいつでも投げれるけれど、
受け取ることは相手が投げてくれないと出来ないし、いつ投げてもらえるかも分からない。
新訳聖書の「初めに言ありき」ならぬ、「初めに相手ありき」を、もっと意識したいと感じた。
そうしたら、今より相手のことを知ることができて、もっと好感をもてるだろう。
私は、アメリカ型プレゼン方式(相手に分かりやすく自分を伝える)より、
日本平安型和歌方式で、相手のちょっとした言動から気持ちをくみ取り、
やんわりじわじわ仲良くなっていきたいと思う。
□実践すること
・広島校改革!(・・と言っても、まだ詳細はなし汗)
とりあえず、良いと思ったことはなんでも詰め込む
・寛大で包容力のある人を目指す!
とりあえず○○○○○、まずは君の話をいっぱい聞いて、
心を包み込める大きな人間になります。
ターゲットになったが最後と思い、覚悟しときんしゃい!
□全体を通しての感想
JVU関連の会議に出席させていただくこと自体が初めてなうえ、
かつ、いきなり全体会議に出席することになって焦りました。
テーマ①で、いきなりテーマから逸れた内容を長々しゃべってしまい、
とてつもなく反省&後悔しております。
また、最大の反省点としては、広島校のまとまりの無さが目立ったことです。
かなりショックを受けました。
他校の方々は、みな自分たちがどういう活動をしていて、どういうことを学び、
それらをしっかり受け止めて自分のものにしているのに、
広島校は、まとまりが薄く、どういう人がいるかも知らず、
情報の共有がまったくできていません。
徳島校の「教え合い」(=支え合い)の精神も、熊本校のストイックなやり方も、
大阪校の方の、一人でもしっかり務めを果たしているお姿も、
東京校のバラバラな個性なのにどこかまとまりを感じる雰囲気も、
みんな素敵に見えましたし、尊敬すべき姿でした。
広島校、一歩どころか、数十歩、出遅れた感があり、本当に反省の極みです。
この気持ちを忘れず、広島校の皆と協力して、広島校を再生させていきたいです。
あと半期しかありませんが、できることは何でもやって、
後悔しないように過ごしていきます!
色々気づかせていただき、本当に有り難うございました!!
From:横澤彩子(広島大学大学院修士2年)@JVU広島校1期生
---------------------------------------------------------------
はじめて平和式典に参加し、
私がすべきことは自分の周りの小さな平和を守ることだと感じた。
「世界平和の実現」という大きな概念では、
自分が何をして良いのか分からなかったが、
今回の式典に参加することでそのことに気づくことができた。
また日本は「広島を繰り返さない」と言い、
アメリカは「パールハーバーを忘れない」と言っている。
戦争の悲惨さを忘れず、戦争を繰り返さないことは必要だが、
こういった活動には相手国に対する批判も込められていると感じる。
過去の出来事を互いに許しあうことができなければ、
心の戦争は終わらないのだと思う。
私も個人のレベルで日常における様々な出来事を許せる
心の広い人間にならなければならない。
午後からのJVU全国会議では
各校の特色を知ることができ、大変良い刺激になった。
また今回ご指摘いただいた「ほうれんそう」や基本的なマナーなど、
社会に出てからJVUの名に泥を塗らないよう、しっかりと実行していきたい。
From:河本将治(広島大学)@JVU広島校1期生
~平和式典とパール判事記念碑をとおして~
■「平和」を願う瞬間(とき)
8月6日 8:15 ―――広島に原爆が投下された時間
あれから67年目を迎えた昨日、この時間に、
式典にいらしていた方々が黙とうを捧げた。
しかし、蝉の鳴き声しか聞こえないと思っていたら、
遠くでデモの声が聞こえていた。
誰かも言っていたが、初めて原爆の落とされた地で
同時刻を迎えた自分も同じことを思った。
・・せめて、この時間くらい、原爆で亡くなった方の喪に服すればいいのに、と。
平和の鐘が虚しく聞こえた。
でも、彼らだって、別のところで哀悼しているかもしれない。
かく言う自分だって、これまでの24年分は、この時間を意識したことがなかった。
・・・去年の自分は何をしていただろう? その前は? さらに昔は?
ヒロシマという地に来て初めて考えさせられた、「平和を想う時間」。
6日付けの日本経済新聞の「春秋」に、
「8月ジャーナリズム」という言葉が載っていた。
「この時期だけ、思い出したように戦争だ平和だと騒ぐ、
という指摘だ」(本文抜粋)
何とかかぶれではないけれど、8月のこの時期だけ、
思い出したように戦争や平和について考える。
自分だってそうだ。他の多くの人だって、そう変わらないだろう。
ご指摘が痛く胸をつく。
一方で、「めぐる夏ごとの、社会のさまざまな試みが、あの戦争をかろうじて
「現代」に押しとどめてきた」(本文抜粋)というのも事実だと思う。
式典のなかで述べられていたが、当時を経験した人々は年々減っており、
受け継がなければならない「あの夏」は薄れている。
市長による平和宣言のなかで、3人(当時20歳の女性、
13歳の少年、16歳の少女)の方の話が挙げられていた。
聞いていて、当時の惨状が思い起こされたが、
私の思考回路ではすべてを思い描くことはできなかった。
――それは当時を知らないからだ。
知る努力を怠っているからだ。
それでも、中学生の歳で死体を運ぶ/家族がどんどん死んでいく/
自分だけ取り残される・・・・そんな現状には耐えられない。
式典に出席している人たちが、皆バタバタ死んでしまって自分だけ取り残されたら・・、
もし、今一緒にいるベン大の皆が、今この場で死んでしまったら、どうしよう・・。
考えたら怖くなった。
自分にできることが何なのか、自分はどうしたら「平和」をつくることができるのか、
どうしようもなく分からなくなって、頭がぐちゃぐちゃになった。
そんなときに読み返していた「平和への誓い」。
つらい出来事を、同じように体験することはできないけれど、
わたしたちは、想像することによって、共感することができます。
平和はわたしたちでつくるものです。
身近なところに、できることがあります。
違いを認め合い、相手の立場になって考えることも平和です。
思いを伝え合い、力を合わせ支え合うことも平和です。
なんだか「大丈夫」と言われている気がした。
一人じゃないから、大丈夫だと。
なんやかんや言っても、私は一人ではなく、
いつでも誰かに支えてもらって生きている。
平和について考えたり、平和を願うときは、人それぞれでいいような気がした。
誰かに揶揄されたり、人の嘲笑を買ったりするかもしれない。しかし、
大切なことは、絶対に「平和」を心から忘れないこと。
そうすれば、せめて私のまわりにいる人だけには「平和」を届けられる。
みんながそうなら、いつか世界は「平和」になる。
今はそう信じている。
1日をとおして、そう教えてもらった。
それが私にとって、式典に参加して得た一番重要なことだった。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
本照寺(広島市中区)にある、
ラダ・ビノード・パール氏の記念碑を皆で訪問・拝見した。
正直に申告すると、この方のことは聞いたことがある気がする・・というくらいの認識だった。
山近社長や住職さんのお話を聞き、自分でも彼自身のことをかいつまんで調べてみた。
極東軍事裁判において、日本の全面無罪を訴えた人――。
さまざまに思うところがあったが、以下に一番印象深かった点についてまとめさせていただいた。
■自分なりの判断 -パール判事の≪真理≫-
山近社長のお話のなかで、パール判事は
「(私が日本が無罪と言っているのは)日本のためじゃない。
自分なりに調べて、自分なりの判断を下したからだ」
というような内容を仰っていたと伺った。
調べると、次のような一節をパール判事が仰っていることが分かった。
わたしは1928年から45年までの18年間(東京裁判の審議期間)の
歴史を2年8ヶ月かかって調べた。
各方面の貴重な資料を集めて研究した。
この中にはおそらく日本人の知らなかった問題もある。
それをわたくしは判決文の中に綴った。
このわたくしの歴史を読めば、
欧米こそ憎むべきアジア侵略の張本人であることがわかるはずだ。
2年8カ月にもわたり、日本のあれこれを調べていただいた、その精神に感謝だが、
この数文を読んだだけでも、パール判事がどれだけ丹念に事実を調べ上げ、
他の判事たちと相対していたかが伝わってくる。
それは決して日本を擁護しようとか弁護しようとかしたわけではないのだ、と。
ただ、自分の信ずる≪法の精神≫を貫き通しただけなのだと感じる。
自分のなかに絶対に譲れない、法の在り方や国際正義があって、
それが正しいと思ったから、もしくは他国の判断が間違っていると思ったから、
主張しただけにすぎない。
真理をつかむことはとても難しく、それを主張できるパール判事は非常に凄い人だ。
今まできちんと知らなかった自分が申し訳ない。
今の自分は、正しい判断をしているのかどうか、不安になる時が時々ある。
確かめようもないのだが、人に相談したり、自分と向き合ったり、色々してみる。
そんななかで、最近気づいたのは、
「自分に自信がないなら、色々調べてぶつかってみること」。
これまでのやり方はみな、内にしか向いておらず、
外に向かって自分の正当性を主張することを避けてきていた。
それでは、いつまでも内巻きスパイラルからは抜け出せないのは当たり前だ。
写真だけ見ると分からないが、おそらくパール判事だって
「怖い」と思うことがあったはずだ。(・・と、私は思っている)
自分なりの判断をしたいなら、自分に自信を持ちたいなら、
まずは自分の姿勢をプラスに変えるべく努力して、正していかないと、
賛同や自信、ひいては自分の生き筋は得られない。
パール判事の言葉を見て、改めてそう思った。
+α)
私は、パール判事の主張は、正しいと思っている。
子どもの喧嘩は、起こってしまうとどちらが良いか悪いかなんて関係なくなってしまう。
けれど、「戦争」は違う。
もし、日本とドイツだけが悪いと言うのなら、
パール判事の言うように、正義も法律も真理もくそもない。
パール判事には、その主張から約65年後となったが、
遅ばせながらの「有り難う」を伝えたい。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~un3k-mn/0815-pal.htm
===========================
~第1回 日本ベンチャー大學・全国会議に出席して~
□内容
テーマ:①大學をとおして、自分に身についたこと・続けていること
②これからのJVUにおいて、変えていきたいこと・改善点
・出席者全員の挨拶
・今元さんによる進行・意見聴取・まとめ
・事務連絡
□気づき・まとめ
■「なんでもやってみる」
色々な方が口ぐちにおっしゃっていたこと・・それが「まずは、やってみる」。
徳島校では、校長が「死にはしないからガンガン行け」と仰っているとか。・・かっこいい。
「自分から」「行動」しなくては、意味がない。 そうして「実践する」ことに意味がある。
大人はヒントを与えて見守るだけで、やるのは自分たち。
このような内容を聞いていて、自分は口先だけじゃないかと思った。
「やってみる」とは言っても、最後の最後、尻込みして出来ていないこと、やり過ごしていること、沢山浮かぶ。
京都研修や回天研修も、ドッキリでも参加させてもらえば良かった。
徳島校の方たちが、自分たちでPV作ったり、
大学でアピールしようとしたり、とても力強い前向きベクトルを感じた。
頭で分かっていても身体で行動しないと、本当の理解ではない、と最近教えられ、
「知合同一」を目指しているが、やはり難しいし、これらのお話を聞いていて、
自分にはまだ程遠いと突き放された感覚だ。
だからこそ、こんな「自分をどうにかしたい」。
頭で考えるより、まず行動したい。
いつまでも教わってばかりの自分を卒業して、自分から行動できる人間になりたい。
やはり「人生、やってみなくちゃわからない」のだと、改めて思う。
先の日報にも書いたが、自分はなんだかんだ孤独(ひとり)ではない(はず)。
だからこそ、自分が失敗したら、その分を助けてくれる人は絶対にいるはずだ。
だから、もう少し勇気を出して、人を信じて、
その先の扉を越えて、行ってみたい。
■ 常に「相手」を意識
まずは、「相手の意見を受け止めること」
次に、「自分の意見を、相手が分かってくれるように、発信すること」
よく、「相手に分かりやすく、自分の意見を伝えなさい」と言われる。
が、この場にいた人の多くがまず受け止めることからと仰っていて驚いた。
私も「相手の意見を受け止めること」から始めたいと、常々思っている。
相手が色々聞いてきたり話しかけられたりすると、自分は大概ひいてしまう。
それで自分が失敗したこともある。
自分が言っていることを相手が分かってくれるとすごく嬉しい。
が、それは裏を返せば、相手だって同じことをされたら嬉しいはずで、そうしてほしいはずだ。
両者受け手だと先に進まないので、自分も発信しなければならないが、
やはり、まずは投げられたボールをキャッチすることが先決なのだ、と考えさせられる。
ボールに例えて気づくが、自分からボールはいつでも投げれるけれど、
受け取ることは相手が投げてくれないと出来ないし、いつ投げてもらえるかも分からない。
新訳聖書の「初めに言ありき」ならぬ、「初めに相手ありき」を、もっと意識したいと感じた。
そうしたら、今より相手のことを知ることができて、もっと好感をもてるだろう。
私は、アメリカ型プレゼン方式(相手に分かりやすく自分を伝える)より、
日本平安型和歌方式で、相手のちょっとした言動から気持ちをくみ取り、
やんわりじわじわ仲良くなっていきたいと思う。
□実践すること
・広島校改革!(・・と言っても、まだ詳細はなし汗)
とりあえず、良いと思ったことはなんでも詰め込む
・寛大で包容力のある人を目指す!
とりあえず○○○○○、まずは君の話をいっぱい聞いて、
心を包み込める大きな人間になります。
ターゲットになったが最後と思い、覚悟しときんしゃい!
□全体を通しての感想
JVU関連の会議に出席させていただくこと自体が初めてなうえ、
かつ、いきなり全体会議に出席することになって焦りました。
テーマ①で、いきなりテーマから逸れた内容を長々しゃべってしまい、
とてつもなく反省&後悔しております。
また、最大の反省点としては、広島校のまとまりの無さが目立ったことです。
かなりショックを受けました。
他校の方々は、みな自分たちがどういう活動をしていて、どういうことを学び、
それらをしっかり受け止めて自分のものにしているのに、
広島校は、まとまりが薄く、どういう人がいるかも知らず、
情報の共有がまったくできていません。
徳島校の「教え合い」(=支え合い)の精神も、熊本校のストイックなやり方も、
大阪校の方の、一人でもしっかり務めを果たしているお姿も、
東京校のバラバラな個性なのにどこかまとまりを感じる雰囲気も、
みんな素敵に見えましたし、尊敬すべき姿でした。
広島校、一歩どころか、数十歩、出遅れた感があり、本当に反省の極みです。
この気持ちを忘れず、広島校の皆と協力して、広島校を再生させていきたいです。
あと半期しかありませんが、できることは何でもやって、
後悔しないように過ごしていきます!
色々気づかせていただき、本当に有り難うございました!!
From:横澤彩子(広島大学大学院修士2年)@JVU広島校1期生
---------------------------------------------------------------
はじめて平和式典に参加し、
私がすべきことは自分の周りの小さな平和を守ることだと感じた。
「世界平和の実現」という大きな概念では、
自分が何をして良いのか分からなかったが、
今回の式典に参加することでそのことに気づくことができた。
また日本は「広島を繰り返さない」と言い、
アメリカは「パールハーバーを忘れない」と言っている。
戦争の悲惨さを忘れず、戦争を繰り返さないことは必要だが、
こういった活動には相手国に対する批判も込められていると感じる。
過去の出来事を互いに許しあうことができなければ、
心の戦争は終わらないのだと思う。
私も個人のレベルで日常における様々な出来事を許せる
心の広い人間にならなければならない。
午後からのJVU全国会議では
各校の特色を知ることができ、大変良い刺激になった。
また今回ご指摘いただいた「ほうれんそう」や基本的なマナーなど、
社会に出てからJVUの名に泥を塗らないよう、しっかりと実行していきたい。
From:河本将治(広島大学)@JVU広島校1期生









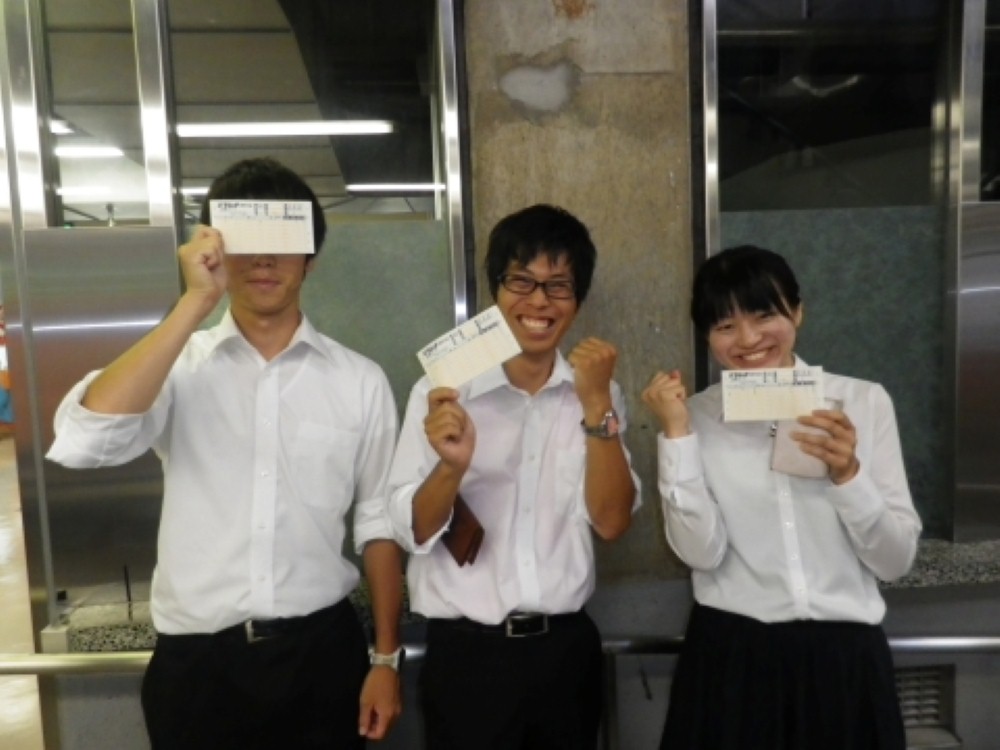
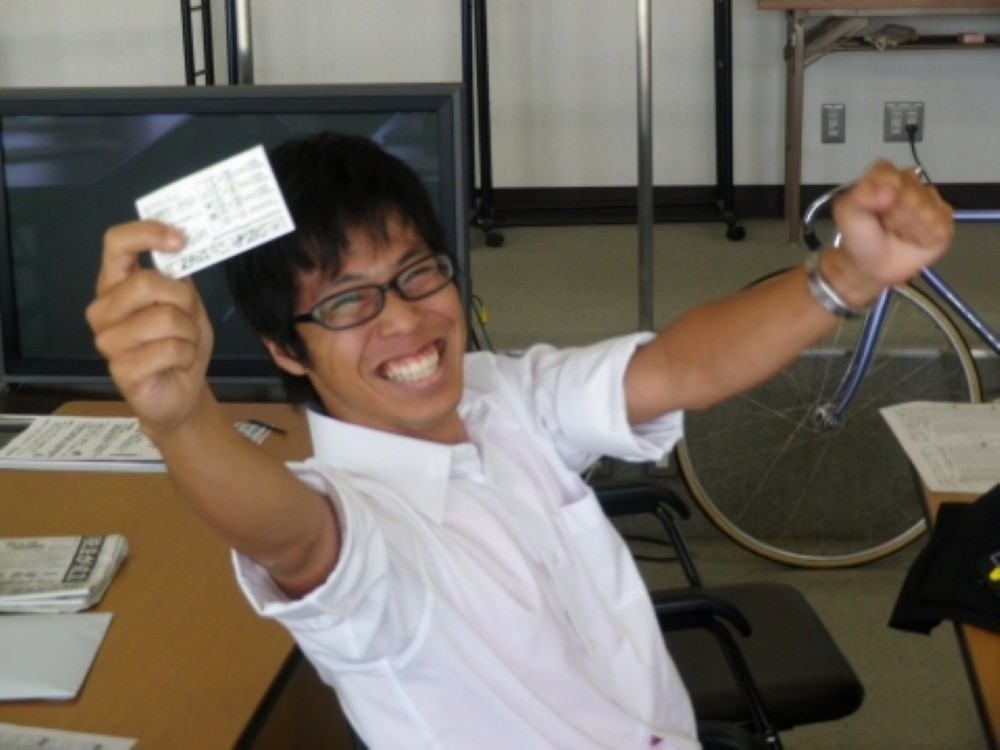
 RSS 2.0
RSS 2.0












